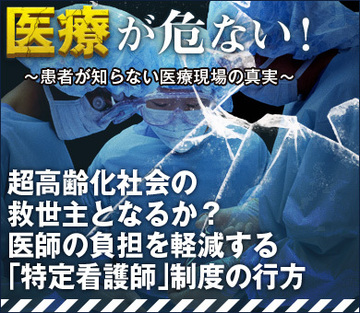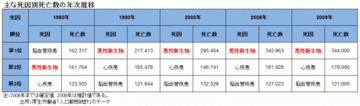多くの患者が誤解しがちな
「がん拠点病院」の役割
一般的に、がん診療連携拠点病院と聞けば、がんに関するあらゆる治療が揃っており、患者や患者の家族からすれば、有名な拠点病院で診てもらいたいと思うのが当然だろう。しかし、急性増悪を含む発症まもない急性期の患者ともう治す手段がないと診断された末期の患者にとっては、拠点病院で治療を行う意味が変わってくる。
がん診療連携拠点病院とは、平成18年に制定された「がん対策基本法」や、政府が定める「がん対策推進基本計画」に基づいて、全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるように、各地域におけるがんの治療や教育の拠点となる病院を厚生労働大臣が指定した病院である。原則として、都道府県がん診療連携拠点病院」は各都道府県に1カ所、地域がん診療連携拠点病院」は各2次医療圏に1カ所ずつ整備されている。
現状では5大がん(肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん)のすべてに関して手術療法、化学療法、射線療法のいずれもが実施可能な体制が整っていることや緩和ケアを提供できること、外来化学療法を実施しつつも入院できる環境にあること等一定の条件を満たしていることが必要である。
 土屋了介(つちや りょうすけ)/慶応義塾大学医学部卒業。日本鋼管病院外科、国立療養所松戸大学病院外科を経て、国立がんセンター病院外科。2006年より国立がんセンター 中央病院病院長を歴任。2010年4月から財団法人癌研究会顧問。行政刷新会議の規制・制度改革に関する分科会WG主査 専門は胸部外科学、特に進行肺がんの手術、集学的治療、周術期管理、および胸部診断学。
土屋了介(つちや りょうすけ)/慶応義塾大学医学部卒業。日本鋼管病院外科、国立療養所松戸大学病院外科を経て、国立がんセンター病院外科。2006年より国立がんセンター 中央病院病院長を歴任。2010年4月から財団法人癌研究会顧問。行政刷新会議の規制・制度改革に関する分科会WG主査 専門は胸部外科学、特に進行肺がんの手術、集学的治療、周術期管理、および胸部診断学。
がん診療連携拠点病院に指定されれば、国の補助金や診療報酬上の評価などの優遇があるため、収益性は変わってくる。しかし何よりもがんの専門病院としてのブランド力により、より多くの患者が集まる。そうした患者や周辺住民は、がん拠点病院がどのような目的で整備されているかどうかなど、詳細は知らされていないので、「がん拠点病院ならば、がんにかかったとしても、何でもやってもらえる」というイメージを抱くのは当然だろう。
しかし、元国立がんセンター中央病院の病院長で、今年4月から癌研究会の顧問に就任した土屋了介氏は一般の方が陥りがちな“誤解”についてこう語る。
「一般の方は、専門家ががん拠点病院についての情報を判り易い話として出してこなかったこともあり、急性期と末期の患者さんの話を混同している場合が多い。拠点病院の最も大きな役割の1つが急性期の治療である。急性期で治療法が分からないときは拠点病院で良いが、積極的な医療としてはもう治す手段がないと診断された場合、拠点病院で行う緩和ケアと在宅で行う緩和ケア医療は差がない。介護はどちらが良いか。自分が末期と診断されたらどこで最後を迎えたいかを考えるべきである」