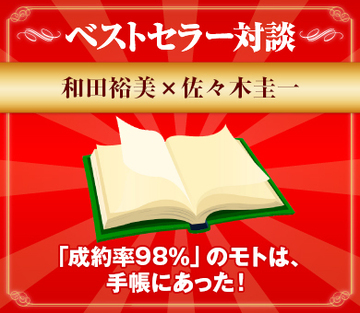会議資料の悲劇
――私はこの会社の営業部長。今日は月に1度の経営会議で販売状況を報告する。営業部門のスタッフは昨晩遅くまでかけて足元の状況をまとめてくれた。エクセルの表はもちろん転記ミスがないかダブルチェック済み。各支店の売り上げをグラフにまでしてくれた。力作だ。なにより全体の販売の数字が悪くない。今日は自信をもってプレゼンができそうだ。
さて、会議が始まりいよいよ私の説明の番だ。好成績だが浮かれた印象を持たれたらいけない。あくまで数字を中心に説明することにする。社長はじめ幹部もこの結果には満足だろう…。終わった。
…と思ったところで、突然社長が私に質問をしてきた。「○○君、全体はいい。ただ先月の大阪支店の販売が落ち込んでいるようだが、今の状況はどうなっているのか?」 確かに大阪の数字は悪い。だがそれが今どうなっているのかは報告を受けていない。だいたい、手元には集計に使った2週間前のデータしか持ち合わせていないのだ。「至急確認して、1週間以内に共有させていただきます」としか言えなかった。この質問に答えるためだけに、また部下に残業を頼まなければいけないのは気が重い――。
特徴は「描画の速さ」
ビジネスの現場で、このような会議資料にまつわる作業負担は日増しに大きくなっている。IoTだビッグデータだと、集められるデータの量だけは膨大になってきたが、それを扱うのは結局「人」。そのうえ、いったんまとめた資料を同じように作り直すのもたいへんだ。もっと簡単にデータを見極める方法はないものか。
Tableau(以下・タブロー)は、そのようなニーズに応える1つのソフトウェアだ。エクセルなどの数表を即座にグラフに変換し視覚化することで、ビジネス分析を高速にする。CG(コンピュータ・グラフィックス)アニメーションスタジオである「ピクサー」の設立メンバーの1人が、グラフィックスの力をビジネスに役立てたいという思いから2003年に創業した。
ピクサーといえば、スティーブ・ジョブズが1980年代の後半にアップルを追われた際に作った企業で、後にCG映画の代表格である「トイ・ストーリー」「モンスターズ・インク」などを制作し、現在はディズニーの子会社となっている有名スタジオだ。今も同社のロゴに採用されている「電気スタンド」は、創業当時に作った宣伝用アニメーションの主役。当時のコンピュータの処理速度としては圧倒的な表現力を見せつけ、その技術力の高さは世界を驚かせた。