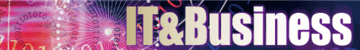ダイヤモンド・オンラインplus
高齢者の住宅市場が大きな盛り上がりを見せている。中心となるのは、2011年に制度がスタートした「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」だ。不動産活用と同時に社会貢献にもつながる、サ高住経営の概要を紹介する。

日本は言わずと知れた世界有数の地震大国。「30年以内の発生確率は99%」と警告されてきた宮城県沖地震は東日本大震災として、想定をはるかに超える規模で現実となった。今後も直下型や海溝型の大地震発生が高確率で懸念されており、それらの被害額は史上空前規模に達するとみられる。地震の発生自体を回避することは不可能だが、被害を最小限に抑えることは可能だ。そのための建物の耐震化について、東北大学大学院の前田匡樹教授に話を聞いた。

JFEシビルが開発した、耐震安全性を実現する鋼管ブレースは、教育施設や集合住宅など多様な建物の耐震改修技術として、またデザイン性に優れた「魅せる建築」の耐震要素として多くの建築物に使われている。

215万戸を超える住まいづくりの実績と医療・介護分野での豊富な実績を持つ積水ハウス。サービス付き高齢者向け住宅事業にも力を入れ、立地環境や市場ニーズ、事業者の運営方針に応じて最適なプランを提案している。同社が特に首都圏で力を入れている最新の事例と共に紹介する。

豊かな将来や夢の実現を目指す人々に注目されている「投資信託」と、投資を応援する制度「NISA」。その仕組みや魅力について、布川敏和さんと、ご子息の布川隼汰さんが、生活経済ジャーナリストの和泉昭子さんと語り合いました。

家計における見直し効果が大きい生命保険料。特に40~50代は加入時と今の状況が大きく異なっている場合もあり、大胆な見直しも視野に入れたいところ。保障は確保したいが、保険料は抑えたい──そんなジレンマを解消する商品がそろう楽天生命を取材した。


クロスボーダーM&Aでは、デューデリジェンスから交渉、そしてPMIに至るまでのプロセスの全体像を熟知したアドバイザーの存在が、成否を握っている。プライスウォーターハウスクーパース(PwC)が、注目される理由もそこにある。

新興国を中心にグローバル展開を積極的に推進している韓国企業の国際訴訟事情と、その対策についてUBIC副社長の池上成朝氏とUBIC Korea, Inc. CEOのチョ・ヨンミン氏に聞いた。

訴訟に関係する文書、そうでない文書を仕分けるレビューは、データ量の増加に伴い、ITを活用したアプローチが主流になりつつある。日本において、この分野をリードしてきたのがUBICだ。

米国の裁判において、訴訟を有利に運ぶポイントは、訴訟案件に関係する文書を必要十分なレベルで開示すること。そのためには、日本語の処理にたけた事業者を選定する必要がある。
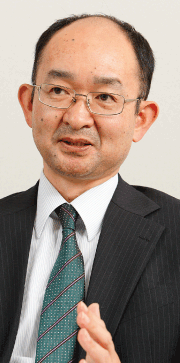
海外で訴訟を提起されたり当局の調査を受けた場合、特に米国においては、日本にはない「ディスカバリ」と呼ばれる証拠開示の手続きがある。すべての関連文書・データの提出が求められ、日本企業は膨大な作業およびそれに伴う費用等の対応に苦慮している。
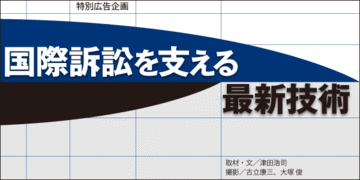
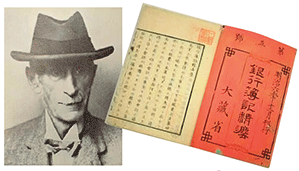
ビジネスの現場で必要とされる英語力は、日常の英会話におけるものとは異なる。相手を納得させられるよう、明確にポイントを伝える、説得力ある話し方が求められるのはもちろんのこと、相手の文化・歴史的な背景を知り、相互理解を深める努力も大切になる。特に高度なコミュニケーション力が必要なエグゼクティブが、効率的に英語を習得する新しいプログラムがスタートした。
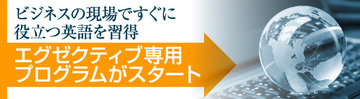
第3回
今年も「年末年始を海外で」というニュースが流れる季節になった。観光では、国内から海外へ出かけるものをアウトバウンドと呼び、海外から国内へはインバウンドと言う。アウトバウンドが盛んになると、「景気がよい」とされる。一方、国は政策として今後、インバウンドを増やそうとしている。インバウンドなら国内にお金が落ち、貿易としては「輸出」扱いになるからだ。

世に先駆けて「環境経営」を提唱したリコーでは、自社の事業活動によるCO2排出の削減はもちろん、顧客に販売する製品、サービスによる環境負荷削減の取り組みも加速している。今日まで主力事業である複合機やプリンターの省エネ性能を飛躍的に向上させ、グローバルに高い評価を得てきた。2012年にはLEDランプを発売。工事不要の利点を活かし、従来はLED導入が難しかったテナントビルや店舗などでの導入も広がっている。

CSR(企業の社会的責任)の捉え方が変化しつつある。単なる寄付や社会貢献を超えて、社会的な課題への働きかけを意識する積極的なCSRに乗り出す企業が増えた。また、社会問題の解決と企業の利益を両立させるCSV(共有価値の創造)という新たな潮流も広がりつつある。その最新の動きを追った。

企業の人事担当者を中心に、現場でのOJTによる若手社員の育て方を、講演やワークショップを通じて学んでもらおうと開催されたセミナー「進化するOJT~経験から学ぶ仕組みづくり~」。セミナー内容をレポートする。


ビッグデータがクローズアップされてから数年が経過したが、いまだ多くの企業が、戦略を描けずにいる。マーケティング・アナリストの三浦展氏は、「企業側の都合が優先されたビッグデータ解析では、本当の答えは得られない」と言う。