米国(9) サブカテゴリ
第15回
オバマでアメリカの外交が大きく変わることは間違いない。それはイデオロギーの変化というよりは、オバマの生い立ちから滲み出た世界観と倫理観から発する変化と呼ぶのが正しいように思う。

第17回
米長期金利上昇が続く中、円安が進行。この状況はいつまで続くのか?
米長期金利上昇が続く中で、ドル/円もクロス円も上昇傾向が広がって来ました。これは、米国債が買われ続けて来た「安全資産バブル修正の動き」に他なりません。この傾向は、まだしばらく続くと見られています。
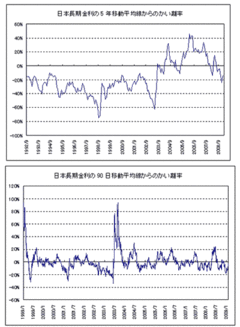
第64回
金融改革法案の準備を進めるオバマ米国新大統領だが、実現には苦労を伴いそうだ。その行く手には、ブッシュの「パッチワーク政策の残骸」や「バブルの酔いから醒めない金融経営者」などの問題が立ちはだかっている。
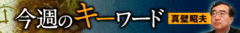
第90回
政府支援後も危機的状況続く米ビッグスリーの“泥船”
「ビッグスリーが本当に再生できると信じている米国人は、いないのではないか」こんな辛らつな発言をしたのは、日本人ではない。米国系サプライヤーの米国人幹部だ。ビッグスリーには明るさが見えない。
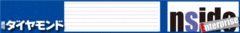
第9回
アメリカの住宅バブルの崩壊によって輸入が減少すると、日本は2重の意味で影響を受けることになる。アメリカに対する直接の輸入が減少するだけでなく、中国を経由する分も減少するのだ。
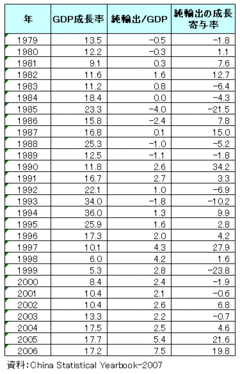
第67回
「金融危機への過程で行なわれた6つの過ち」というエッセイを、元FRB副議長のアラン・ブラインダー・プリンストン大学教授が「ニューヨークタイムズ」誌に寄稿した。米国では、それを巡って論争が起きている。 その過ちとは、野蛮なデリバティブの放置、レバレッジの規制緩和 、サブプライム貸し出し急増の黙認、不十分な差し押さえ抑制策、リーマン・ブラザーズの破綻、TARP(不良資産救済プログラム)の使い方の迷走といったもの。ブラインダー教授は、「当局者が6つの過ちを犯さなければ、金融市場や経済は今日の姿ほど恐ろしいことにはなっていなかった」と主張するのだ。

第61回
先週、「銀行国有化できぬゆえに米国の金融危機は長期化する」という題名のコラムを掲載したら、批判を含むさまざまな意見をいただいた。そのなかで最も考えさせられたのは、「銀行国有化は社会主義的政策の到達点ではないか」という指摘だった。「銀行国有化」を持ち出した私の論理を、もう一度整理しておこう。
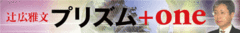
第16回
逆張りの2月でいったん100円に戻すか?100年に一度の危機で80円へ向かうか?
米長期金利の急上昇は、FRBがリスク回避に伴う米国債シフトに「不満」を持っており、米国債購入の具体化を見送った可能性が高いと言われている。これが「安全資産バブル崩壊」につながれば、為替にも影響が出る。
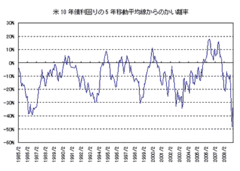
第31回
1月、IBMは立て続けにビジネス界を驚かせた。最初は、2008年第4四半期の業績発表。この不況でIT業界を含むほぼ全産業で企業収益が悪化する中、IBMは純利益が前年同期の40億ドルから12%増の44億ドルになったと発表、2009年の見通しも明るいと強気に出たのだ。しかし、その数日後、2800人とも4000人とも言われるレイオフが同社で行われているという報道が世界を駆け巡った。好調な業績の中でなぜ?このふたつのニュースは実は無関係ではない。

第26回
中国のアンケートでは「今後の米中関係はどうなるか」の質問に対して5割以上が悪化すると答えている。また、「オバマ氏は貿易問題で中国に圧力をかけ、波乱が生じるだろう」という意見が3割以上もいる。

第66回
田舎に住む77歳の母は東京の佃煮が好きなので、時々だが宅配便で送っている。先日電話で「また送ろうか?」と話したら、「100年に一度の危機のときにそんな出費はしなくていい」と止められた。日本経済の悪化は深刻だが、佃煮はそんなに無謀な出費ではないような……。マインドがずいぶんと悲観的ではないか。こんな話に象徴されるように、「100年に一度の危機」という煽り文句が政府やマスコミによって宣伝され過ぎた結果、日本人の消費マインドが急速に冷え込んでいる感は否めない。過去の世界大恐慌時と比べて急増している「貯蓄の多い中高年層」を、市場に呼び戻す努力も必要ではないか?

第30回
米国のブロガーやギークたちの間で、パーム社の新型スマートフォン「Pre(プリー)」が注目を集めている。iPhoneやブラックベリーを超えたという前評判は本当なのか。

第5回
加藤寛 嘉悦大学学長 「日本の政治を立て直せ」
政策提言集団、ポリシーウォッチによる緊急討論会「2009年の政治経済の行方」の模様を引き続き動画にてお伝えする。第5回は、加藤寛 嘉悦大学学長。
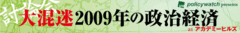
第60回
金融危機を打開する最も有効な方法は、銀行国有化である。だが、自由主義経済の盟主たる米国では、民主党政権でも、それは唾棄すべき政策であり、それゆえに出口が見えない。
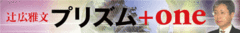
第62回
米国と世界の命運を担って登場したオバマ新大統領の“現代版ニューディール政策”には、当初から大きな期待がかかっている。だが、理想と現実のあいだには少なからずギャップがあることも、事実なのである。
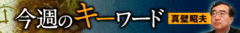
第260回
シティ分割にバンカメ資本再注入それでも遠い金融危機の抜本解決
シティグループの分割、バンカメへの公的資金再投入。1月16日に発表された大手米銀の再建・救済策も金融危機の抜本的解決策にはほど遠いものだった。「不良資産の損失確定」にまで踏み込めなかったからだ。

第24回
オバマ大統領就任の日をアメリカで過ごした筆者は、彼の地の熱狂を直接垣間見ることができた。そこで強く感じたのは、危機感と問題意識の彼我の差だった。

第61回
世界はオバマ大統領の就任に沸きかえった。しかし、この歓喜の渦とはあまりにも対照的なことに、同じ日、ニューヨークの株式市場はダウ工業株30種平均が前週末に比べて300ドル以上も急落する事態に陥った。
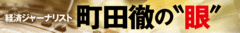
第5回
遂に幕を開けた「責任を果たす新時代」で人々はオバマに何を期待しているのだろうか。ごく普通のアメリカ人はどんな思いで新大統領を迎えたのだろうか。就任式で沸いたワシントンからの現地レポート。

第65回
バーナンキFRB議長は、銀行システムへの追加資本注入の必要性や不良資産を買い取る「バッドバンク」構想に言及した。だが、FRBの超過準備は8000億ドルを超えており、抜本的な治療の必要がある。
