米国(11) サブカテゴリ
第248回
リスク資産購入増にドル安覚悟景気後退歯止めに必死のFRB
FRBは政策金利であるFFレートの誘導目標を1%から0~0.25%に引き下げた。これまでもCPなどリスク資産を買い入れてきたが、それをさらに拡大する姿勢を見せており、資産膨張に拍車がかかるのは必至だ。

第25回
新旧のメディアが等しく広告収入の激減に喘ぐ中、ひとり気を吐くインターネット新聞がある。ギリシャ生まれのセレブがアメリカでおこした「ハフィングトン・ポスト」だ。

第61回
リーマン・ブラザーズ破綻以降、金融市場を救済するために資金供給を増加させてきたFRBだが、ここに来て財政難に陥っている。「非常事態」に際してなりふり構わない米国に比べ、ECBは若干冷静だ。

第58回
ブッシュ米大統領に、靴を投げつけるという「ゲーム」が世界中で流行っているという。早速、筆者もトライしてみた。イラク人記者のように逮捕されたりすることもなく、大統領の顔面に靴を命中させることができた。
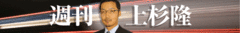
第49回
例年、「新春相場」で年の始めは株高になると言われている。しかし、米クリスマス商戦の好不調によって相場の強弱が二極化するという事実もあるため、一概に判断はできない。果たして、今年はどうなるのか?
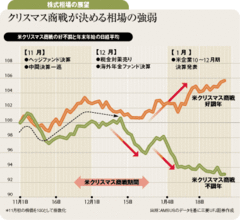
第10回
「FOMC大相場」が起こる理由、起こらない理由
16日に発表される今年最後のFOMC(米連邦公開市場委員会)の結果は、目先のドル/円の運命を左右するでしょう。金利政策いかんで、下がり過ぎの米長期金利がさらに下落し、為替に影響を与える可能性もあります。
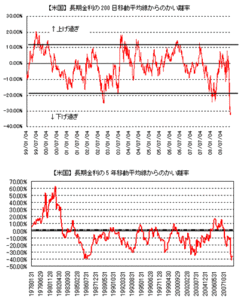
第37回
手塚治虫原作の「鉄腕アトム」がCG映画となって、全米で来年公開される。製作を率いるイマジ・インターナショナルのダグラス・グレンCEOに、日本アニメの魅力を聞いた。

第24回
インターネットを使って政治を変える。これは、先の大統領選でバラク・オバマがしっかりと証明したコンセプトである。数多の“小さな市民”が草の根運動を起こし、少額の寄付をする。「塵も積もれば山となる」アプローチで、オバマは最終的に7億5000万ドルの選挙資金を得た。スタンフォード大学教授のローレンス・レッシグも今、ギーク(オタク)たちの協力を得て、同じような動きを起こして注目されている。その運動の名称は「チェンジ・コングレス(議会を変えろ)」。目的は、政治から腐敗をなくすこと。その手始めは、議員たちが怪しいロビイストや政治圧力団体から政治資金を受け取らないようにすることだ。

第9回
なぜ「最悪の雇用統計」でも円安になったのか?
5日発表された米11月雇用統計では、何と50万人超もの雇用激減となりました。ところがこの日、米株と米金利は上昇し、そしてドルも対円で反発に転じました。なぜでしょうか?
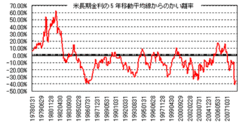
第240回
金融危機による損失は21兆ドル甘過ぎるIMF予測の“15倍強”
IMFが10月に損失予測額を発表したが、実態はその約15倍の21兆ドルという有様だ。なぜ、かくも開きが生じるのか。予測対象には米国のローンと証券しか含まれていないうえに、その損失予測自体の基準が甘いからだ。

第55回
ビッグ3からデトロイト3と見下される立場に凋落した米自動車大手3社は2日、米議会に“再建計画”を提出した。それらに共通する特色は、なんとか政府の救済を受けようとして、あの手この手の媚びを売った点だろう。
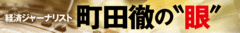
第23回
アメリカでは、あのYouTubeをそっちのけにして、1年前に登場したビデオ・サイト「Hulu.com」が話題になっている。Hulu.comとYouTubeの大きな違いは、YouTubeがユーザー投稿によるビデオが中心になっているのに対して、Hulu.comはテレビ局のニュースやドラマ、映画会社の人気作品などプロが製作したビデオが無料で見られるという点だ。著作権問題やDVDなどの二次的ビジネスでがんじがらめになっているはずのこうしたビデオが、Hulu.comの登場ですんなりと見られるようになったことに最も驚いているのは、実は一般ユーザーだろう。

第59回
米国では、オバマグッズが飛ぶように売れている。しかし、気になるのはそのあまりにも大きすぎるオバマへの期待だ。今後、景気対策などの政策に失敗して失望感が広がれば、その反動が一気にで出かねない。

第8回
ドル/円は一気に90円割れに向かうのか? それとも!?
いまだ混乱が収束していない為替相場。長期移動平均線からのかい離率で見ると、主要通貨の中長期的な下落余地はまだ残っています。対円でドルが下がる一方、ユーロは対ドルで大きく下落する可能性もあります。
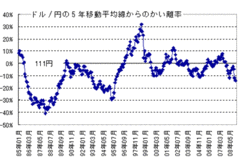
第56回
不況に喘ぎ、消費が見る見る落ち込み始めた米国は、このまま行けば「デフレスパイラル」に陥る懸念がある。バブル崩壊後の日本を苦しめた「忌まわしきデフレ」が、今度は世界規模で到来するかもしれないのだ。
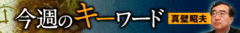
第13回
GMは9月24日に創立100周年を祝った。アメリカで始まった産業革命の象徴に自動車産業がある。その歴史を体現してきたGMが倒産することになれば、アメリカ自動車業界の歴史は第二幕に進むことになる。
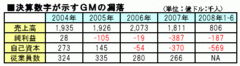
第11回
PayPal共同設立者ピーター・シエル「金融危機の遠因は科学技術の停滞」
信用バブルはなぜ繰り返されるのか。ネット決済サービス「PayPal」の共同設立者で、現在ヘッジファンドを運営するシエル氏は、科学技術の停滞にその遠因があるとの大胆な説を披露する。

第54回
前例の無い大規模な金融機関の救済策を相次いで米金融当局が打ち出したにもかかわらず、米国市場の動揺は収まる兆しがない。市場の関心は、次に経営危機が表面化するのはどこかという話題に集中しているという。
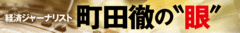
第22回
ジェリー・ヤンのヤフーCEO辞任で、マイクロソフトが再びヤフー買収交渉のテーブルに戻ってくるとも期待されたが、それもマイクロソフトのステーィブ・バルマーCEOが言下に否定した。あれだけのインターネット・ブランドがすっかり路頭に迷っているとは……。だが、ここでは敢えて明るい材料だけを並べてみよう。実はアナリストらの間でも、ヤフーは十分なリソースを持っているにも関わらずそれをマネタイズ(換金化)する術に欠けているだけ、という声が多い。

第58回
クリスマスを控えたニューヨークでは、現在「ギフトカード(商品券)に気をつけろ」という報道がなされている。経営危機に陥る量販店が少なくない昨今、ギフトカードが無効になる恐れがあるというのだ。
