dw-special(57) サブカテゴリ
13/06/29号
共に経済の専門家であり、投資家としても豊富な経験を持つ山崎元氏と小幡績氏。株式市場に大きな影響を与えている「異次元の金融緩和」に対し、相反する意見を持つ論者でもある。乱高下相場の行方と投資家が取るべき行動を聞く。「賢い株の売り方&買い方」とは?

13/06/22号
京セラ、KDDIを創業し、日本航空では会社更生法の適用から2年で営業利益2000億円というV字回復をやってのけた稀代の名経営者、稲盛和夫氏。中小企業の経営者を中心に信奉者は多い。稲盛流「心の経営」はいかにして生まれたか。氏の経営哲学を徹底解剖する。

13/06/15号
歯医者数が10万人を突破した。明らかな供給過剰であるため患者争奪戦が激化し、保険診療だけでは食えない歯医者たちが、保険外の自由診療で患者争奪を繰り広げている。単価の高さがうまみだった自インプラントなどの由診療は、競争激化の中で今や値引き合戦に陥っている。

第203回
先進国で実行された金融緩和。日本など各国の経済にどうした影響をもたらすのか。以前から日本経済の構造改革を訴えているアレン教授に聞いた。

第202回
12年3月期、13年3月期と2期連続で7000億円超の巨額赤字に陥ったパナソニック。そのパナソニックを長年見つめ続け、最新刊『パナソニック・ショック』を上梓したノンフィクション作家・ジャーナリストの立石泰則氏の目には、同社はどう映るのか。話を聞いた。

第201回
本サイト連載でもおなじみ野口悠紀雄教授が最新刊『「超」説得法』を上梓した。「一撃で相手を仕留める」ことこそが説得の極意とする本書には、“使える”テクニックが満載。同時に、昨今の経済政策論争を読み解く上でも示唆に富む。野口教授にそのエッセンスを聞いた。

13/06/08号
日本銀行の黒田東彦総裁が打ち出した“異次元緩和”をはじめとする日米欧の大規模な金融緩和によって、“中央銀行バブル”が発生している。日本でも株式市場は乱高下、金利も不気味な上昇を続ける。投資マネーはどこに向かい、何を引き起こすのか。そしてその果ては……。

13/06/01号
志望校に進学できる「大学合格力」を子どもにつけてくれる中高一貫校や高校はどこか。本誌の独自分析と取材で、子どもが成長する学校を判別する。国公立大学、特にその医学部に進学するなら、中高一貫校に通うのが有利。ランキングを見ると、この傾向は年々高まっている。

第200回
いまや子どもの数より多いペット。家族の一員となり、飼い主は惜しみない愛情を注ぐ。一方、市場の拡大をにらむ企業も次々と参入するが、ペットにまつわるおカネには相場がなく不透明。かかる費用から、ペットとの付き合い方に至るまでをみてみよう。

13/05/25号
市場を動かす経済ニュースはどうやって生み出されているのか。特ダネから他紙の後追い記事、決算の観測記事まで、あなたが絶対知らないであろう経済ニュースの裏側を明かす。横行する企業からメディアへのリーク──。その背景には経済メディアを取り巻くいびつな環境がある。

13/05/18号
100周年を目前にして巨額赤字を計上し、過去最大の危機に瀕しているパナソニック。そのさなかに就任した津賀一宏社長は、テレビをはじめとする脱家電を推し進め、黒子に徹して実利を狙うB to B事業への大胆なシフトを掲げる。パナソニックの最後の賭けは成功するか。

第199回
2期連続で7000億円を超える巨額の最終赤字を計上したパナソニック。赤字の元凶となったテレビなど消費者向け家電から、事業の核をBtoB(企業向けビジネス)にシフトするという方針を打ち出している。一方で、かつてパナソニックの家電販売を支えてきた全国の地域販売店は、こうした状況にどう立ち向かっているのか。

13/05/11号
企業が“本気”のリストラに乗り出した。大企業で退職勧奨プログラムを受けさせられる社員が増え、ミドル世代(30代後半~54歳)の再就職市場が活性化している。もはや、政府も行政も企業も守ってくれないのだ。あなたは、「仕事消失時代」に生き残ることができるか?

13/4/27
有料老人ホームなどを凌ぐ勢いで、「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」と呼ばれる賃貸住宅の戸数が急増している。介護施設とサ高住のどちらが老後の住まいにふさわしいか。玉石混交とされるサ高住物件をどう選べばいいか。高齢者の住まいと介護を徹底調査した。
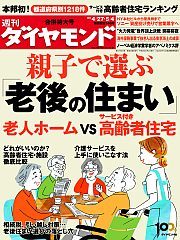
13/04/20号
リーマンショック以降、地味な動きだったマンション市場が、久々に盛り上がりを見せている。アベノミクスの効果を先読みした富裕層がいち早く動き、サラリーマン層も追随する展開だ。マンション販売の最前線をリポートし、「今、買うべき物件」の条件を指南しよう。
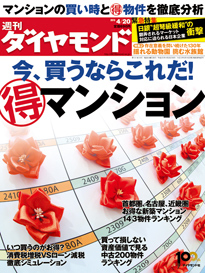
13/04/13号
豊かな国内需要に応えて世界5位の農業大国、日本。味覚や安全性に厳しい消費者に鍛えられた農産物の品質競争力は高い。今、最大の課題である耕作放棄地を資源、TPP(環太平洋経済連携協定)を生産拡大のチャンスとみて農業を成長産業とする人々がいる。
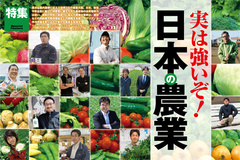
第198回
経営再建中の半導体大手、ルネサスエレクトロニクスの社長に2月22日に就任した鶴丸哲哉氏が報道各社のインタビューに応じ、ルネサスの赤字体質について「環境の変化に迅速に対応できなかった」と振り返った。サプライズ登板となった鶴丸氏に、今後のかじ取りを聞いた。

13/04/06号
今年の春闘では、一時金の満額回答や昨年実績を上回る回答が相次ぎ、“賃上げラッシュ”への期待が高まっている。安倍首相の発言がマジックのように浸透し、一連の賃上げを引き起こしたように思えるが、そこには誤解もある。「安倍マジック」のタネ明かしをしよう。

13/03/30号
難しい数式や記号並びがちな統計学。一般のビジネスマンにはとっつきにくい学問の1つだが、使いこなせれば、あらゆる分野で通用する強力な“武器”となる。統計家の西内啓氏と駒澤大学経済学部准教授の飯田泰之氏が、統計学が“最強”である理由について語り合う。

第197回
事業では三菱重工業と日立製作所が統合を発表した火力発電システムに関心が集まる。今まで三菱重工と一心同体で火力事業を運営してきた三菱電機だが、方針転換は視野に入っているのか。
