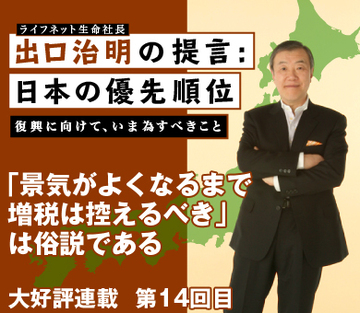出口治明
第34回
国の発展度合いを測定する方法には、GDPの他にもHDI(人間開発指数)やGNH(国民総幸福度)など多様にあるが、人間が動物である以上、GDPを中軸に据えるべきである。このGDPを上げるには、労働生産性を上げるか、労働者を増やすかのいずれしかない。
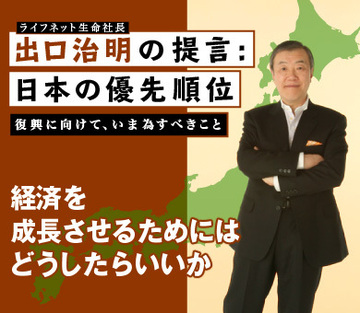
第33回
1990年代以降、かつての成長が見込めなくなった日本。しかし、いまだに高度成長期の残像からの議論が多い。低成長を認めることは心地いいものではないが、置かれた現実を正しく認識することからしか、これからの日本の施策について考えられないのではないだろうか。
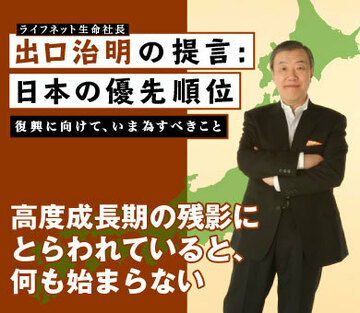
第32回
厚生労働省は2013年度から、定年退職者の中で65歳までの就労を希望する従業員全員の雇用を企業に義務づける方針を明らかにした。はたしてこれで高齢者の雇用は促進されるのだろうか。
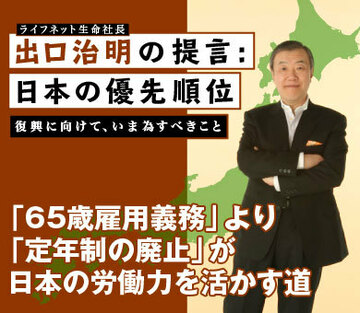
第31回
政府は12月10日の閣議で、2012年度税制改正大鋼を決定した。そこには、消費税の引き上げへの意欲を強く感じる。もしこれで消費税問題がうやむやにされるようでは、野田内閣の求心力は一気に低下するのはないか。いまや税制の改革なくして、日本の未来は開けないと言っても過言ではない。
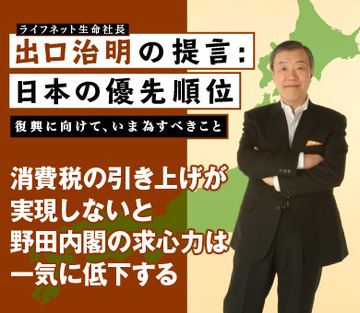
第30回
東京、大阪の両証券取引所は、11月22日、経営統合を正式に発表した。これによって世界で第3位の株式取引所になるが、これで何がどう変わるのか。取引所の力とは、魅力的な商品が揃うことであり、魅力的な投資家を集まることである。そのための課題はまだまだ残されている。
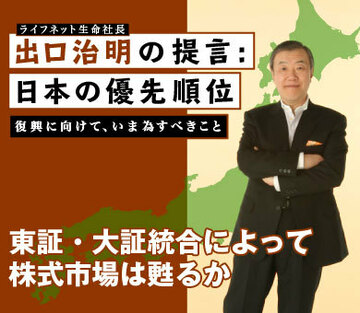
第29回
国語ではなく算数で考えることが問題解決の近道
マスコミの記事で気になるのが、国語での議論が先行し算数での議論が欠けていることだ。つまり、主張の根拠となる具体的な数字やデータを伝えず論じている場合が多い。こうして語られる問題を一つひとつ算数に置き換えていくと、解決への近道が見えてくるものだ。
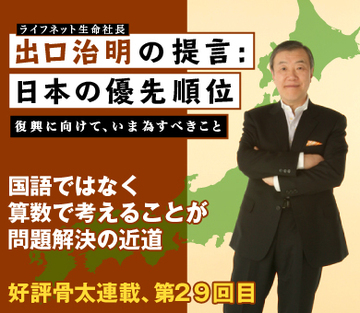
第28回
ウッドフォード元社長が日本人だったらオリンパスの損失隠しは発覚しただろうか
多額の損失隠しが発覚したオリンパス。この問題の発覚は、ウッドフォード元社長が突然解任されたことがきっかだ。この問題は、同質性をもとめる日本企業の弱さを如実に語っていると言わざるを得ない。
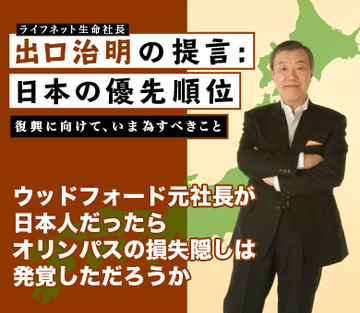
第27回
TPP反対派の意見は根拠に乏しい。交渉への参加は実益で判断すべき
TPP交渉への参加問題が大きな話題となっているが、反対派の意見をつぶさに検証してみると大半が根拠に乏しいことは明らかだ。交渉への参加は実益で判断すべきだが、それがなぜできないのであろうか。それは、数字やデータを前提とした議論が欠落しているからだ。
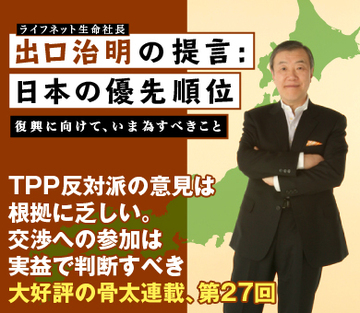
第26回
食料自給率の低下は、TPP反対の主因となるほど悪いことなのか
TPP反対派の意見で必ず出てくるのが、「食料自給率の低下」であるが、これははたして大きな問題だろうか。食料安保の問題の一環にするにしても、他に優先すべき課題はいくらでもある。
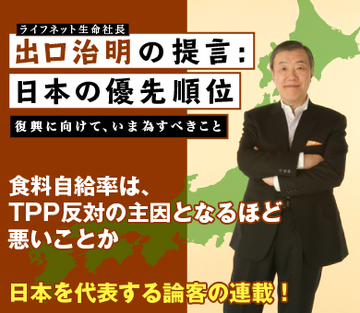
第25回
義務教育は12年で「飛び級」を認め成人年齢は18歳に引き下げよ
少子高齢化の日本では、中長期的な国の発展にとって教育の重要性はますます高まるであろう。その中で中学・高校は一貫教育の6年を義務教育として、かつ「飛び級」を認めるのが望ましい。そして成人年齢も18歳に引き下げる。これはグローバルで見ても決しておかしくはないだろう。
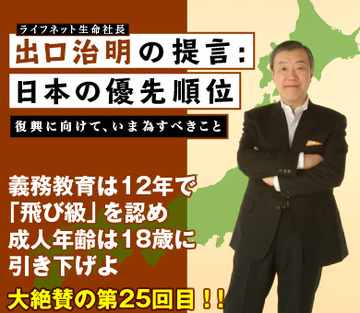
第24回
教育改革は、企業や社会が取り組むべき課題である
わが国の教育については、まさに百家争鳴。「ゆとり教育の弊害」を声高に叫ぶ人もいれば、「教育の格差」に焦点を当てる人もいる。多くの深刻な問題を抱えているが、改革は「需要」サイドである企業や社会から始めるべきだ。
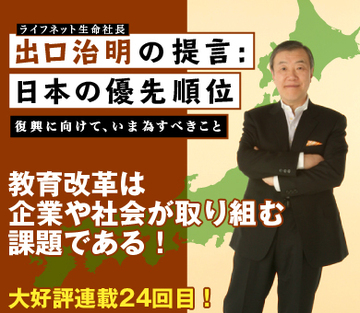
第23回
鉢呂前経産相の不適切発言では報道にも違和感あり。新聞はすべてを署名記事にせよ
先日の鉢呂前経産相の「死の町」発言は軽率の極みだが、それをまるで「言葉狩り」のように一斉に糾弾したマスコミの姿勢にも違和感がある。事実を正しく伝えるために、新聞はすべてを署名記事にすべきではないか。新聞の影響力が大きいだけに、その健全な姿勢を求めたい。
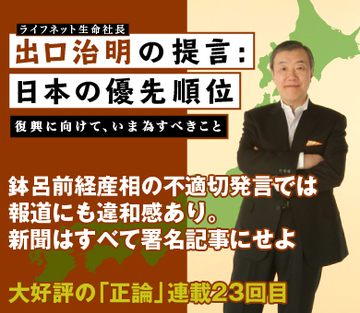
第22回
すでに日本の世帯構造は一人暮らしが主流。公共住宅はすべてコレクティブハウスに
今年の国勢調査で、初めて単独世帯(一人暮らし)の割合が3割を超えた。かつての「4人家族」が基本であった時代は遠い昔の話である。しかし、いまだに日本の住宅政策は、高度成長・終身雇用を前提とした持ち家政策を維持している。少子化が著しい日本では時代錯誤も甚だしい。これからの公共住宅は、コレクティブハウスが主体になるべきだ。
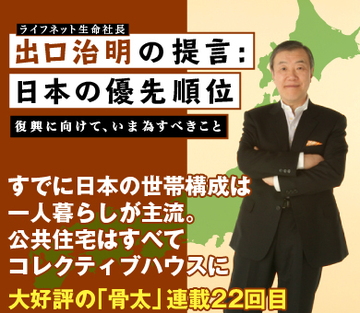
第21回
なぜ円高で大騒ぎするのか。そこに財界の時代遅れの発想が見え隠れする
急激な円高が進行するなか、メディアも財界も政界もこぞって、円高是正を叫んでいる。しかし、そもそも自国通貨の価値が上がることは好ましいことではないか。円高是正を叫ぶ背景には、産業構造の転換への無意識の抵抗が見え隠れする。
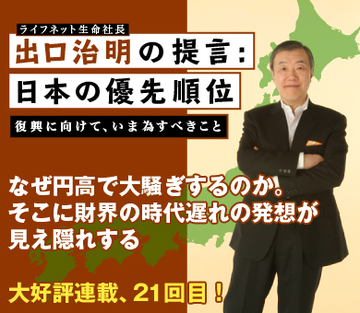
第20回
野田新内閣に期待することはできるか?「人事」と「政策」からその実力を測る
菅内閣の総辞職を受けて、9月2日に発足した野田新内閣は、支持率等を見ると、一先ず順調なスタートを切ったと言えるだろう。世論調査の結果に照らし合わせながら、「人事」と「政策」を評価し、野田内閣の実力を測る。
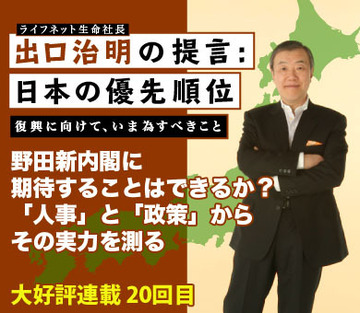
第19回
失われた15年で明らかになったリーダー不在は政界だけの問題ではない
「失われた10年」もしくは「15年」と言われる。だが実際何が失われたのか、総括がされてこなかったのではないだろうか。それは国の責任なのか企業の責任なのか。しかし問題は明らかだ。それはリーダーの資質に問題があるのだ。
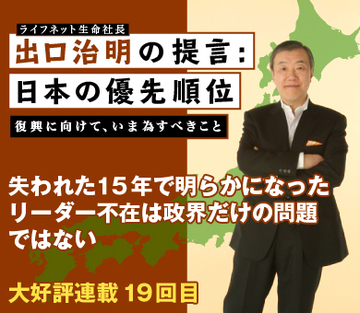
第18回
メディアが民主党代表選の争点だと煽る「大連立」は、政策遂行の手段に過ぎない。争点は「政策」のはず
菅首相が退陣を明言し、民主党代表選は月内にも行われる見通しとなった。代表選で先行する野田財務相は、自民・公明両党との大連立を目指す考えを明らかにし、メディアも「大連立が代表選の焦点になる」とはやし立てている。しかし、大連立は、円滑な政策遂行のための一つの手段に過ぎない。一国のリーダーを以上、争点は政策であるべきだ。

第16回
企業に雇用を義務づければ、長期的に雇用機会は減少する
日本で若者の所得が低い原因は、俗にフリーターと呼ばれる非正規雇用労働者の存在にあると言われている。この問題を解決する一番の早道は、若者を家から追い出すことである。さらに、企業に若者の雇用を義務づけても意味がない。同一労働同一賃金の原則を守り、雇用の流動性を高めることだ。
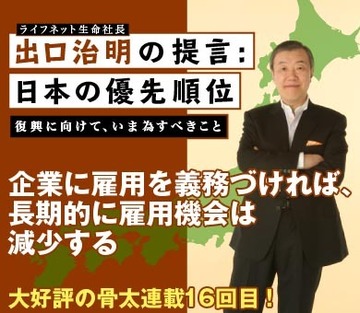
第15回
本当の社会的弱者は誰か。社会保障の改革に、所得水準の視点を
税改革について論じた前回に続き、今回は社会保障改革について私見を述べる。そもそも社会保障は社会的弱者を救済するためのものである。現代における弱者は、高齢者とは言い切れず、若い世代への配慮も必要である。
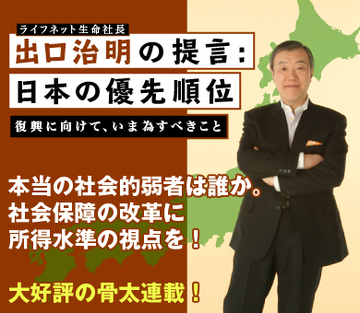
第14回
「景気がよくなるまで増税は控えるべき」は俗説に過ぎない
増税が不人気の政策であることは百も承知だが、わが国の財政状況を見ると、消費税の増税は避けて通れない。それでも俗説を持ち出して増税を阻止しようという議論がある。その最たるものが、「景気がよくなるまで増税は控えるべき」というもの。それは、景気後退の本当の理由を無視した議論である。