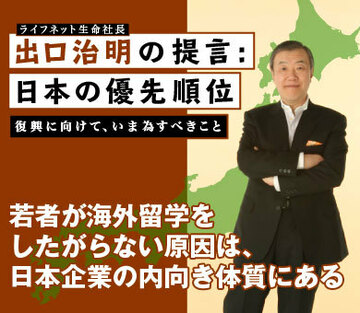出口治明
第54回
今年のわが国の株主総会集中日は、6月28日(木)だった。総会日の分散は進んでいるらしいが、大手メディアが総会集中日を、「まるで当然のこと」のように取り扱う風潮には、強い違和感を禁じ得ない。
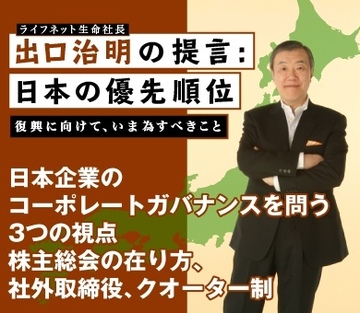
第53回
前回のコラムで、シングルペアレントの困窮対策が焦眉の急である旨を述べた。実は、わが国はもう1つ、喫緊の課題を抱えている。それは、年間で3万人を下らない自殺対策の問題である。今回は、この問題を取り上げてみたい。
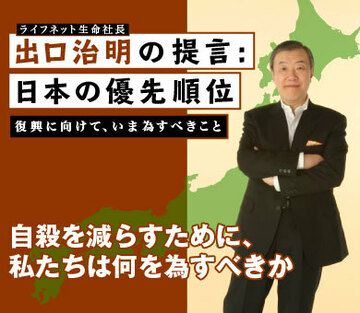
第52回
私たちの未来であるわが国の子ども・若者は、現在、どのような状況に置かれているのだろうか。今回は、内閣府が6月6日に公表した、2011年度「子ども・若者白書」を紐解いてみたい。
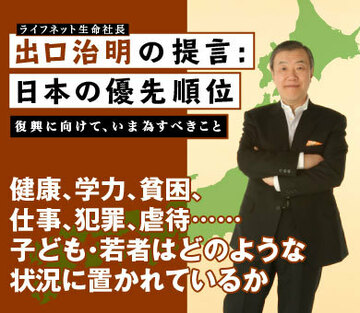
第51回
わが国では1人で暮らす「孤住」が最大のグループとなってしまったが、この不自然な生活様式は、人間を少しずつむしばんでいくのではないだろうか。では、どうすればいいのか。1つの解は、コレクティブハウスであると考える。
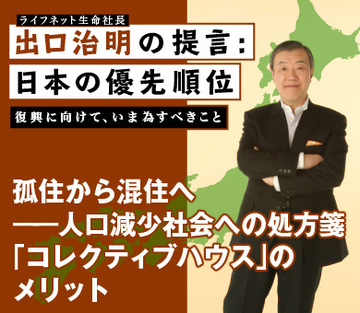
第50回
スイスの著名ビジネススクールが発表した2012年の世界競争力ランキングによると、日本の総合順位は昨年より1つ下がり、59ヵ国・地域中27位となった。国の競争力は、「大きな政府、小さな政府」と何らかの因果関係があるのだろうか。
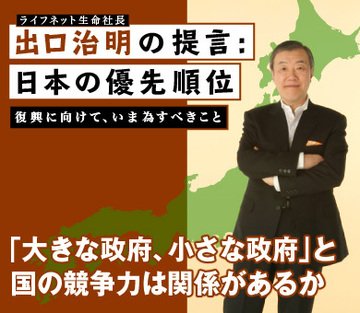
第49回
わが国では、1961年に国民皆年金、国民皆保険制度が完成した。当時と今とを比べると、平均寿命の伸長に伴い、年金支給・高齢者医療サービス支給期間は実に男子が3.25倍、女子が2.45倍に伸びた。また、勤労世代1人あたりの負担は、制度設計時の3.95倍まで増大している。
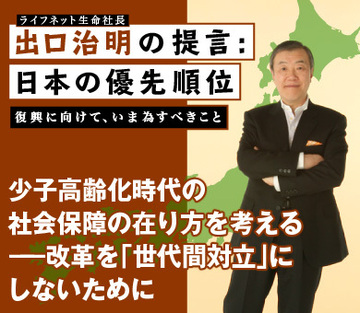
第48回
4月27日、与野党の合意の下に改正郵政民営化法が成立し、小泉郵政改革は、その終焉を迎えたように思われる。なぜかと言えば、改革の中心であったゆうちょ銀行とかんぽ生命保険の完全民営化路線がほぼ放棄されたように見えるからである。
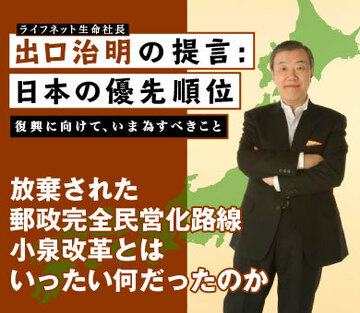
第47回
朝日新聞(5月3日朝刊)の世論調査によると、「一票の格差」が解消されずに総選挙をすることについて、「してもよい」を「するべきではない」が大きく上回った。改めて、市民の常識が健全であることが、裏付けられたように思われる。

第46回
およそどのような制度・仕組みであれ、抜本的な改革を行う上では、そもそもの原点に立ち戻って考えてみることが、最も有効な方法である。今回は社会保障改革を考える視点について考察してみたい。
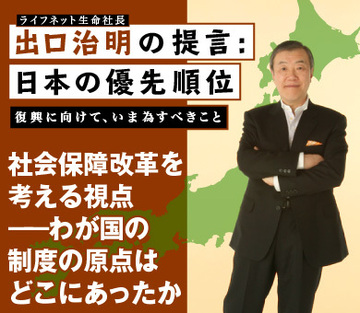
第45回
英誌エコノミストの調査部門とアメリカのシティグループが世界120都市の競争力レポートを発表した。東京は、総合ランキングで6位に入ったが、同じ東アジア経済圏に属するシンガポールや香港は東京より上位にランクされている。
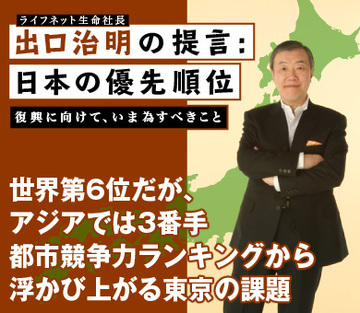
第44回
前回、人間は「人から学ぶ」「本から学ぶ」「旅から学ぶ」以外に学ぶ方法を持たないと指摘した。自分自身、この中では「本から学ぶ」ウェイトが一番高かったような気がする。そこで、今回は、本から学ぶことの効用、即ち「読書のすすめ」について私見を述べてみたい。

第43回
桜の季節が巡ってきた。今年もたくさんの新社会人が誕生する。ところで、社会人になるとはどういうことなのだろうか。原点に戻って考えてみよう。
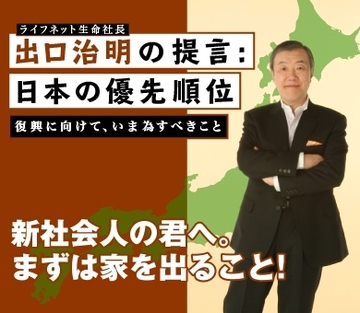
第42回
メディアでは、相も変わらず「就活」特集が組まれ、事あるごとに就職難が喧伝されている。こうなると、大学3年生は、自らの就職について、気もそぞろになるのは仕方がないことかも知れない。しかし、そもそも就活とは一体何だろうか?一度、原点に戻って、自らの頭でよく考えてみるべきだ。
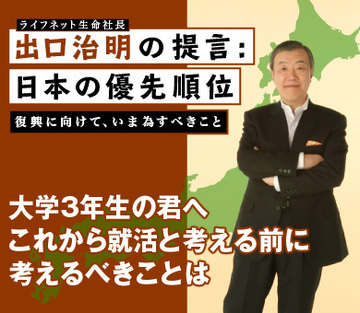
第41回
東日本大震災から1年が経過した。被害状況の数字を眺めてみると、わが国を襲った東日本大震災の被害の大きさに、改めて慄然とせざるを得ない。亡くなられた方のご冥福を心からお祈りすると共に、避難生活が一刻も早く終結することを願ってやまないものがある。
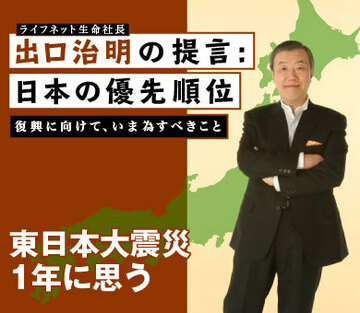
第40回
衆院小選挙区の一票の格差是正をめぐる与野党協議は合意に至らず、何の是正処置も講じないまま、首相への区割り案勧告期限(2月25日)を越えてしまった。平たく言えば、立法府が法を守らず、前代未聞の違法状態に突入してしまったのだ。この政治を変えるには何を変えなければいけないのだろうか。
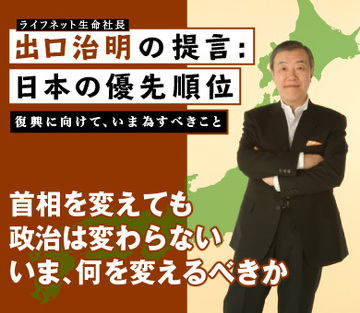
第39回
先日、AIJ投資顧問会社が運用受託していた約2000億円の資金が消失していることが判明した。AIJの顧客の大半は、地域の中小企業が作る厚生年金基金とされ、直接の被害者は中小企業の従業員だ。なぜこのような事件が起きたのか。そして、再発を防ぐには何をすればいいのだろうか。
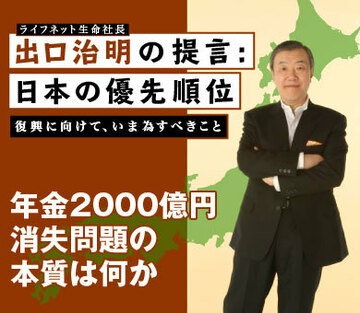
第38回
財政赤字や少子高齢化など日本には問題が山積みだが、大いなるポテンシャルのある産業もある。それは観光である。本来の観光資源と比較すると、現在の外国からの観光客は圧倒的に少ない。カギは産業のシステム化である。
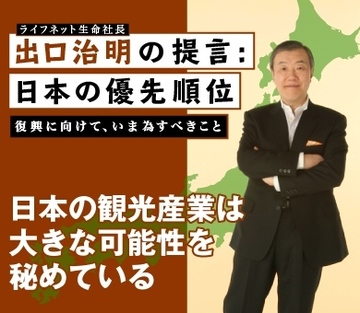
第37回
先日の財務省の発表により日本は、昨年31年ぶりの貿易赤字に転落したことが明らかになった。経常収支が黒字基調であり、貿易収支の赤字は当面大きな問題とは言えないだろう。ただし、これは単年度に限った話である。将来に向けた日本の課題の多くが、今回のデータから読み取れる。
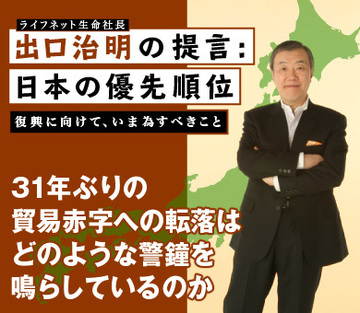
第36回
今回発表された「日本の将来人口推計」の結果を見ても明らかだが、日本はこれから人口半減社会を迎える。このような状況で、なぜ人口を増やす政策を総動員しないのか。現実を直視すれば、これは議論の余地はない。
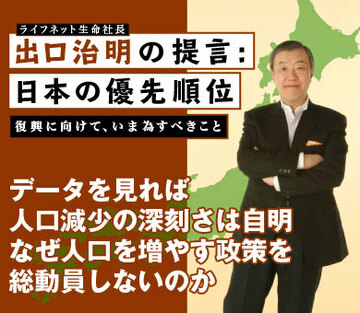
第35回
日本人の海外留学生が減少している。これに対し若者の意識の低さを嘆く声が多いが、問題はそこではない。海外経験者を活用しない企業の内向きな体質こそ、根本原因だ。社会として海外に行くインセンティブを高めなくてはいけない。