
門間一夫
日銀の2026年の金融政策は「利上げなし」から「3回程度の利上げ」まで幅広い可能性を考える必要がある。政策金利が未知の領域に入ってきたこと、日本経済が「ミニスタグフレーション」の状況にあること、そして物価に大きく影響する為替相場が円安にも円高にも振れる可能性があるからだ。

日本銀行は10月の金融政策決定会合で政策金利据え置きを決めたが、植田総裁の発言からは12月あるいは来年1月会合で利上げを決める可能性が高い。高市政権との関係も円安やインフレ加速が困る点では一体であり、追加利上げで政府と日銀が衝突する事態はないと考えられる。

消費者物価の3%以上の上昇が続くにもかかわらず日銀が「年内利上げ」をしそうにないのは、食料品の値上がりは一時的とみる一方でトランプ関税による景気減速リスクがあるからだ。それでも米国の利下げ期待後退などで150円台半ばまで円安が急進行すれば、早期利上げに動く可能性はある。

「骨太の方針2025」は賃上げを起点にした成長戦略を掲げ、今後5年間で実質賃金の1%上昇を定着させるという。だが民間が行う賃上げを政府の成長戦略にする違和感は否めず、実現の手段も従来の小粒メニューの寄せ集めだ。中小企業の省力化支援のように賃金抑制につながりかねない、効果が怪しい政策も混じる。

トランプ関税は部分的な見直しはあっても大枠は維持されると考えた方がいい。「米国への輸出」ビジネスモデルは特別な競争力を持つ分野に限られる。内需中心に稼げるモノづくりの競争力強化のほか、海外からも企業の研究開発拠点や人材が集まる「R&D立国」など新たな成長戦略が必要だ。

日本銀行幹部の利上げへの強気な発言も目立つようになったが、足元の物価上昇はコストプッシュ要因が大きく、利上げ到達点の中立金利の水準も内部の見解は定まっていないとみられる。「半年に1回程度の利上げ」ペースは崩さず、一部に浮上する5月利上げの可能性は低い。
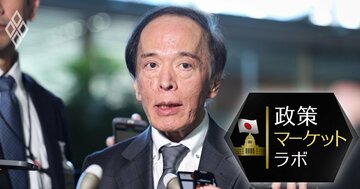
日本銀行による大規模緩和策の「多角的レビュー」は国債買い入れなどの国債市場への「副作用」を認めたものの、全体としてはプラス効果を強調。一方で批判も多かった財政規律や円安への影響評価は「完全スルー」し、政府との“縦割り”の下での限界を露呈した。

10月の金融政策決定会合で政策金利を据え置いた日本銀行だが、米国景気の下振れリスクが弱まるなど「12月利上げ」もありうる情勢だ。再び150円台前半と円安が進行していることや国民民主党の「政策協力」も利上げを後押しする要因になる可能性がある。
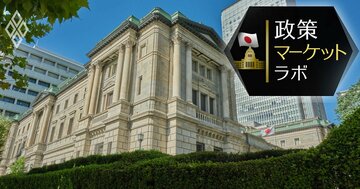
金融市場の不安定化はまだ落ち着いたとはいえず、日本銀行の金利正常化は当面、様子見の可能性が高い。今年後半から来年にかけての利上げペースはドル円相場と利下げ開始後の米国経済次第だ。

2年半で45円の円安が望ましくないのは明らかだが、現状の円安の原因や政策の枠組みでは追加利上げや財政出動で円安のトレンドを反転させるのは難しい。インバウンド活況に象徴されるように円安のメリットを最大限に活用、デメリットを小さくする政策発想に切り替えるのが現実的だ。

日経平均株価は一時史上最高値4万円台を付けて株式市場は活況だが、実質GDPは低調で個人消費は3四半期連続マイナスだ。大手企業は「稼ぐ力」を強めたが国内の中小企業の収益力や家計所得が伸び悩んでいるからだ。乖離を埋めるには新たな「成長ストーリー」を作り企業の国内への投資を活発化させることが鍵になる。

マイナス金利の解除など金融政策の正常化が始まったが、政府の財政中長期試算の「成長実現ケース」の長期金利の前提は今後、数年は名目成長率や物価上昇率を下回る。財政の持続性をチェックするにはあまりに都合の良過ぎるシナリオであり、金利上昇に備えて現実的なものに見直す必要がある。

植田日銀の2024年の金融政策正常化の取り組みを展望すると、マイナス金利やYCC、オーバーシュート型コミットメントの「トリプル解除」を4月に行う可能性が高い。その後、年内に1~2回追加利上げはできそうだが、政策金利は0.25~0.5%程度でとどまり、それ以上引き上げるかは疑問だ。

日銀が来年4月にマイナス金利解除に踏み出すかどうかの鍵を握るのは個人消費の回復だ。今のインフレ下で家計は実質賃金下落と金融資産目減りで二重の打撃を受ける。2%物価目標実現で緩和を続ける金融政策自体も家計消費にはマイナスに働いている面がある。

インフレとの戦いが長引くが金融政策だけで「物価の安定」の実現は難しい。財政が総需要に影響を与える経路は無視できないし、大きな政府債務の下では利上げが効きにくくなるという見方もできる。物価安定への財政の役割が重要だ。

日銀の「多角的レビュー」の主眼は異次元緩和の総括だ。レビュー結果が果たす役割には物価情勢に応じて3つが考えられる。可能性が高いのは2%物価目標が達成できずにYCCやマイナス金利を解除し持続性の高い金融緩和へ移行する際だろう。

今春闘は30年ぶりの賃上げ率で、来春闘次第では2%物価目標が実現される可能性がある。しかし、本当に望まれるのは「物価(上昇)に勝てる」賃金の上昇、つまり実質賃金の上昇だ。

植田新日銀総裁の下では異次元緩和策の修正が主要課題になるが、YCCはできるだけ早く撤廃されるべきだ。ほかにも固執し過ぎた2%物価目標の検証と見直し、グローバルな情報発信や政府との対話などやるべきことは多い。

YCCの修正は、その構造的欠陥が物価や金利情勢の変化のもとで露呈したものだ。YCCに固執することで金利形成だけでなく日銀の情報発信もゆがみ、市場との対話が成り立たなくなっている。すぐにも撤廃すべきだ。
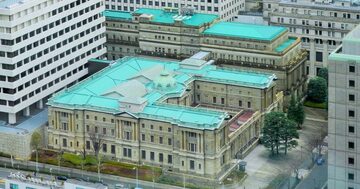
歴史的な円安・物価上昇でも日銀は利上げをしない、できない状況だが、財政には防衛費増額など歳出膨張圧力が強まる。物価目標達成の可能性も皆無とはいえなくなってきた中でインフレ下の財政政策をどうするかの新たな課題が浮上する。
