竹田孝洋
新型肺炎の感染拡大が止まらない。市場は世界経済の見通しの悪化を織り込み、主要国の株価が大幅に下落した。内外の逆風が強まる中、早期抑制に失敗した日本経済の先行きはどうなるのか、著名エコノミストに緊急アンケートを実施した。終息までの期間が長期に渡れば、2020年度のマイナス成長が現実味を帯びてくる。

米イラン武力衝突本格化なら原油は75ドルへ、中国経済減速にも拍車
米軍によるソレイマニ司令官殺害の報復として、イランはイラクの米軍基地を攻撃。原油価格は急騰、株価も下落した。米国がさらなる報復に出れば、本格的な武力衝突の恐れもある。その場合、原油価格は北海ブレントで1バレル=75ドル前後へと上昇するだろう。原油価格上昇は中国経済の減速に拍車を掛けることにもなる。

第4回
経済学者や経営学者、エコノミスト107人が選んだ2019年の「ベスト経済書」をランキング形式でお届けする「ベスト経済書2019」(全4回)。最終回は、第4~10位にランクインした経済書を、選者の「推薦の言葉」とともに紹介。学者やエコノミストの評価ポイントを知ることができれば、各書籍の要点を知ることができる。また、最後には第11〜20位の書籍を網羅したランキング表を用意した。
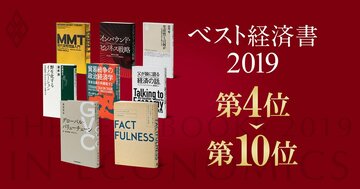
第3回
経済学者や経営学者、エコノミスト107人が選んだ2019年の「ベスト経済書」をランキング形式でお届けする「ベスト経済書2019」(全4回)。第3回は、第3位にランクインした『生産性 誤解と真実』を紹介。内容の解説や著書に込めた思いなどを著者自らに語ってもらった。
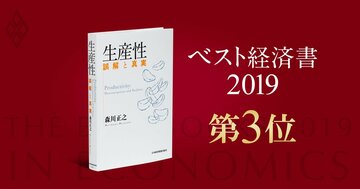
第1回
経済学者や経営学者、エコノミスト107人が選んだ2019年の「ベスト経済書」をランキング形式でお届けする「ベスト経済書2019」(全4回)。第1回は、栄えある第1位に輝いた『「家族の幸せ」の経済学 データ分析でわかった結婚、出産、子育ての真実』を紹介。内容の解説や著書に込めた思いなどを著者自らに語ってもらった。
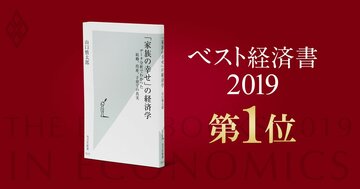
予告編
「ベスト経済書2019」トップ10!学者・エコノミストら107人が厳選
経済学者や経営学者、エコノミスト107人が選んだ2019年の「ベスト経済書」をランキング形式でお届けする「ベスト経済書2019」。厳選した良書を、選者による解説付きでお届けする。全10冊の中身をざっくり理解する「ブックガイド」として使うもよし、書籍のおすすめリストとして使うもよし。大人の教養を身に付けよう。
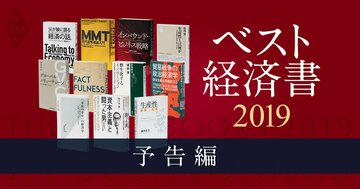
3年後の「割安株」ランキング!9位日本郵船、4位ワールド、1位は?【決算報19秋】
PER(株価収益率)は割安、割高の判断に使われることが多い株価関連指標だ。足元のPERが高くても、将来の利益水準で見て割安であれば、投資対象として魅力があるといえる。「ダイヤモンド 決算報の「19秋」の企業業績・全体像編の第6回では、証券アナリストの予測を集計し、PERに基づいた3年後の割安株(予想低PER)ランキングを作成した。
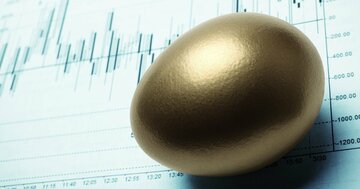
PER(株価収益率)は割安、割高の判断に使われることが多い株価関連指標だ。足元のPERが高くても、将来の利益水準で見て割安であれば、投資対象として魅力があるといえる。「ダイヤモンド 決算報の「19秋」の企業業績・全体像編の第6回では、証券アナリストの予測を集計し、PERに基づいた3年後の割安株(予想低PER)ランキングを作成した。

営業利益が3年後に伸びる企業ランキング!2位オリンパス、1位は?【決算報19秋】
企業が業績予想を発表するのは、足元の今期の決算についてのみ。できればその先の決算期の予想も知りたいところ。連載「ダイヤモンド 決算報」の「19秋」企業業績・全体像編の第5回では、「19夏」に引き続き、最新決算を基に証券アナリストの予測を集計し、3年後に伸びる企業ランキングを作成した。

企業が業績予想を発表するのは、足元の今期の決算についてのみ。できればその先の決算期の予想も知りたいところ。連載「ダイヤモンド 決算報」の「19秋」企業業績・全体像編の第5回では、「19夏」に引き続き、最新決算を基に証券アナリストの予測を集計し、3年後に伸びる企業ランキングを作成した。

企業業績・上方修正期待度ランキング!1位は牛丼大手【決算報19秋】
株式投資の観点からすれば、業績予想を上方修正した企業よりもこれから上方修正しそうな企業の方に魅力がある。企業業績全体が減益基調でも、今後上方修正が期待できる企業はある。通期予想利益に対する中間期での実績利益の比率、いわゆる進捗率が高い企業がそれだ。連載「ダイヤモンド 決算報」の「19秋」企業業績・全体像編の第4回では、進捗率の高い企業を取り上げる。

株式投資の観点からすれば、業績予想を上方修正した企業よりもこれから上方修正しそうな企業の方に魅力がある。企業業績全体が減益基調でも、今後上方修正が期待できる企業はある。通期予想利益に対する中間期での実績利益の比率、いわゆる進捗率が高い企業がそれだ。連載「ダイヤモンド 決算報」の「19秋」企業業績・全体像編の第4回では、進捗率の高い企業を取り上げる。

企業業績・下方修正率ランキング!1位は違法建築問題に揺れる企業【決算報19秋】
企業業績が曲がり角を迎えつつある現在、業績が下降気味の企業が目立ってきている。業績予想を上方修正した企業より下方修正した企業の方が圧倒的に多い。連載「ダイヤモンド 決算報」の「19秋」企業業績・全体像編の第3回では、業績予想を下方修正した企業を取り上げる。

企業業績が曲がり角を迎えつつある現在、業績が下降気味の企業が目立ってきている。業績予想を上方修正した企業より下方修正した企業の方が圧倒的に多い。連載「ダイヤモンド 決算報」の「19秋」企業業績・全体像編の第3回では、業績予想を下方修正した企業を取り上げる。

企業業績・上方修正率ランキング!4位KADOKAWA、1位は?【決算報19秋】
ほとんどの上場企業は本決算発表後に次の通期決算の業績予想を発表する。その後、業績が一定の基準を超えて予想を上回ったり下回ったりしそうな場合は、予想を修正しなければならない。企業業績の全体像をお伝えする「ダイヤモンド 決算報 秋」の第2回では、企業業績が曲がり角を迎える中で業績を上方修正した企業を取り上げる。

ほとんどの上場企業は本決算発表後に次の通期決算の業績予想を発表する。その後、業績が一定の基準を超えて予想を上回ったり下回ったりしそうな場合は、予想を修正しなければならない。連載「ダイヤモンド 決算報」における企業業績の全体像をお伝えする第2回では、企業業績が曲がり角を迎える中で業績を上方修正した企業を取り上げる。

「ダイヤモンド 決算報 秋」では、これまで注目企業の決算をお伝えしてきたが、決算発表も一段落した。今回から企業業績の全体像をランキングを通してお伝えする。第1回は全体の利益水準が落ち込む中で、増益を続ける企業を一挙掲載する。(ダイヤモンド編集部編集委員 竹田孝洋)

営業増益率ランキングトップ10!4位東芝、1位は?【決算報19秋】
個別企業の決算発表も一段落した今、企業業績の全体像をランキングを通してお伝えする。今回は全体の利益水準が落ち込む中で、増益を続ける企業を一挙掲載する。

5月中旬以降、円の対ドルレートは1ドル=105円から109円の間で推移している。円安の材料が出ても110円を超えることはなく、円高の材料が出ても105円を割り込むこともない。それはなぜなのか。背景と理由を分析した。

FRB(米連邦準備制度理事会)による10月の利下げは、市場混乱を避ける配慮が大きく影響しているとみられる。一方、FOMC(米連邦公開市場委員会)は利上げ反対派を抱えている。今回のFOMCには双方への配慮の跡がうかがえる。
