篭島裕亮
#4
個人投資家が好きな「テーマ株」だが、その実態は玉石混交。業績に貢献しない話題先行のテーマも多いのが現実だ。そこで今回は「一時的に盛り上がる材料株」ではなく、新NISAで狙いたい「中長期の骨太テーマ」について、人気ストラテジストに緊急取材した。併せて注目企業も紹介する。

#1
新NISAの「成長投資枠」では日本株の個別株投資も検討したい。インフレ転換、東証の市場改革、ROEの向上……、日本株には追い風が吹いているからだ。ただし、全体相場が堅調でも株式投資でもうけるのは簡単ではない。新NISAの概要と、税制優遇のある「新NISA特有の落とし穴」について解説する。

注目度の高い業界や企業の最新決算を分析する『最新決算 プロの目』。今回はコニカミノルタなど事務機器セクターを取り上げる。オフィス市場が縮小する中、各社とも複合機に変わる次の一手を模索しているが、足元は残酷なほどに明暗が分かれている。直近の四半期決算の分析に加えて、各社の中長期の展望について岡三証券の島本隆司シニアアナリストに聞いた。

#4
アナリスト予想を活用して「利益が伸びる株」「割安度がアップする株」など4種類の「お宝株」候補を選抜。来期以降も業績の拡大が期待できる中長期保有向けの440銘柄をリストアップしたので、新NISAでの銘柄選びの参考にもなるはずだ。

#33
御三家や早慶付属と比較して情報が少ない中堅校だが、教育内容が魅力的な学校はたくさんある。本命校候補としても併願校候補としても注目したい、プロが厳選した偏差値50台前半以下で狙える「ボリュゾ」にお薦めの中高一貫校を一挙に紹介する。

#30
中学受験マニアの父親4人が熱く語った200分の中で濃密な部分を4回に分けて紹介。シリーズ最終回は「低学年からの通塾」や「全落ち」問題に加えて、中学受験の平均的な学力ゾーンである「ボリュゾの戦い方」や「教科別の勉強のポイント」など雑誌版では紹介し切れなかったテーマも掲載。具体的学校名も挙げながら、拡大版でお届けする。

#28
中学受験マニアの父親4人が熱く語った200分の中で特に濃い部分を、雑誌版の3倍超のボリュームで4回に分けて紹介する第3弾。今回はわが子に合った志望校の見つけ方や「地頭問題」を取り上げる。中学受験を12歳の成功体験にするヒントが見つかるはずだ。
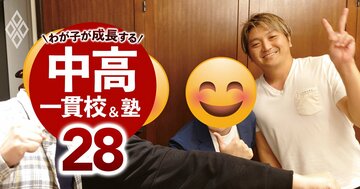
#27
受験生の子どもにとって夏休みが天王山ならば、親にとっては11月が正念場といっても過言ではない。ここでうまく自分の中の「内なる魔物」を手なずけられるかどうかが、残り3カ月の道のりの風景を変える。『中受離婚』が話題の著者が、中学受験を親子共に笑顔で終えるための、残り3カ月の親の関わり方について考察する。

#26
合格体験記は読んだことがあっても、塾側の目線で併願戦略を解説した記事は少ない。そこで今回は、希学園首都圏学園長の山﨑信之亮氏に、偏差値帯が異なる6人の生徒の併願戦略について分析してもらった。特別に実際の面談資料も公開する。第3弾は「埼玉受験」で進学先を確保した女子の2月1日、2日の受験校の選択や、最上位層の男子の併願戦略を紹介。子どもの性格に合わせた1月校の選択や、「万が一」があった際の親の心構えについても解説する。

#24
過去最高レベルで激化している中学受験だけに、子どもや家庭への負荷も増している。「中受撤退」や「中受回避」という4文字が頭をよぎった家庭も少なくない。選択肢を増やす意味でも、最新の高校受験事情や公立高校の大学合格実績を正しく押さえておこう。中学受験の中堅校と都立高校の大学合格実績の比較も公開する。

#19
合格体験記は読んだことがあっても、塾側の目線で併願戦略を解説した記事は少ない。希学園首都圏学園長の山﨑信之亮氏に、偏差値が異なる6人の生徒の併願戦略について解説してもらった。実際の面談資料も公開して3回に分けて解説していく。第2弾は2月1日夜に本人の強い意志で受験パターンを変更した男子や、1月の渋幕不合格から2月のチャレンジ校をつかんだ男子のケースをお届けする。
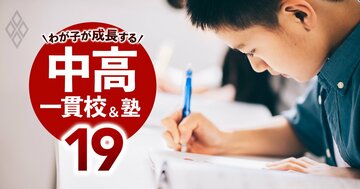
#17
中学受験マニアの父親4人が熱く語った200分の中で、特に濃い部分を雑誌版の3倍超のボリュームで4回に分けて紹介する第2弾は、わが子の合格を願うからこそ勃発する家族間のトラブルとその解消法を取り上げる。さらに、学校見学のポイント、SNS活用法、「女子こそ中学受験をした方がいい」問題についても語る。
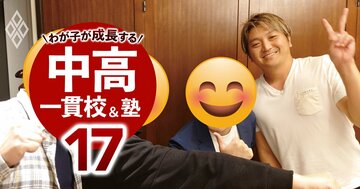
#14
働き方改革の影響で、わが子の中学受験に積極的に参加する父親が急増しているが、父親の参戦はプラス評価だけでなく、夫婦間の新たな火種になるケースもある。中学受験マニアの父親4人が熱く語った200分の中で、濃密な部分を4回に分けて紹介する。今回は「PDCA父さん問題」など、中学受験をビジネス的に捉える是非や、使えるウェブサービスなどについてお届けする。

#10
そもそも志望校はどうやって決めればいいのか。わが子に向く学校とは――。子どもの希望に寄り添いつつ、保護者や塾がむちゃはさせない併願戦略を組む極意について、希学園首都圏学園長の山﨑信之亮氏に聞いた。
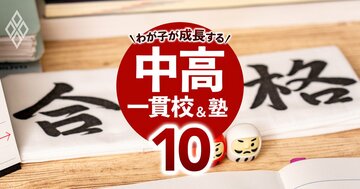
#9
合格体験記は読んだことがあっても、塾側の目線で併願戦略を解説した記事は少ない。難関校に強い中学受験塾である希学園首都圏学園長の山﨑信之亮氏に、偏差値が異なる6人の生徒の併願戦略について解説してもらった。実際の面談資料も公開して3回に分けて解説していく。第1回は平均偏差値40未満ながら中学受験をやり切って、持ち偏差値より10以上も上のチャレンジ校を狙う女子や、きっちり弱気シナリオも組みつつ御三家にチャレンジした男子のケースを紹介する。

#6
中学入試本番まで残り100日。直前期は志望校に向けた対策的な学習になりがちだが、入試本番当日まで“地力”を伸ばすことの大切さを強調するのが難関校に強い中学受験塾、グノーブルだ。残り3カ月の教科別の勉強法や、期待値を最大化する志望校戦略を講師4人に聞いた。

#5
自宅学習において頼りになる家庭教師だが、その質は玉石混交だ。キャンセル待ちが続く家庭教師の齊藤美琴氏に、上手な家庭教師の活用法や、志望校合格から逆算した勉強法について聞いた。

少子化加速でも24年入試は激化必至!「中学受験」最前線!
『週刊ダイヤモンド』10月28日号の第1特集は「わが子が成長する中高一貫校&塾」。2024年の中学入試は、首都圏、関西圏共に受験率の上昇により、過去最高レベルの激戦となる見込みです。そして、この空前の中学受験ブームは、今後数年間は続くことが予想されています。それだけ中高一貫校への期待は大きいわけですが、競争が激化するほど子どもや家庭への負担も増していきます。偏差値やブランドだけではない、わが子が伸びる「中高一貫校」や「塾」の情報など、低学年から直前期まで役に立つコンテンツを忖度なくお届けします。(ダイヤモンド編集部 篭島裕亮)

#14
前期は三菱商事と三井物産の純利益が1兆円を突破。瞬間風速という声もあるが、専門家は資源バブルがなくても総合商社の「実力値」が底上げされてきていると指摘する。資源に強い三菱商事、三井物産と非資源で利益を伸ばす伊藤忠商事など各社の戦略は異なるが、果たして今後5年間の勢力図とは。各社の株主還元策やダークホース候補についても紹介する。

#13
東京証券取引所の「PBR1倍割れ」企業への改善要請もあり、割安株や高配当株が注目されている。とはいえ単純なスクリーニングでは、業績が伸びない「万年割安株」をつかんでしまう可能性もある。アナリストの業績予想に複数のスクリーニング条件も追加して、5年後の業績に対する「割安株」を選抜した。
