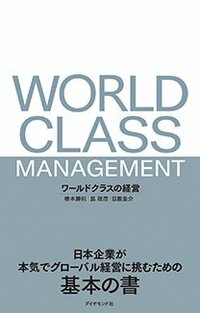日置圭介
アサヒ、資生堂、日清食品と、日本を代表する企業のエキスパートが「グローバル時代の組織と経営システム」について活発な議論を繰り広げました。そこから抽出された3つのポイントとは?

日本企業の全部が全部、世界に向かう必要はないと、私は考えています。国の産業ポートフォリオと企業の事業ポートフォリオはつながっており、国としてのポートフォリオにおいて、個々の企業には役割分担があって当然だからです。
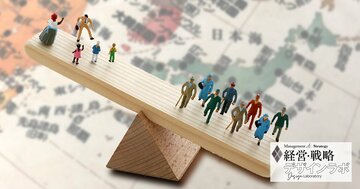
「解体」などとセンセーショナルに取り上げられがちな「事業の分離」ですが、老い縮み続けるこの日本に軸足を置く以上、会社分割や事業売却は極めて重要な打ち手ともなり得ます。

多角化そのものは悪ではありません。しかしながら、うまくマネジメントできなければ、いくら稼ぎ頭ががんばっても、全体の利益率を引き上げるのは困難です。一方で「解体」などとセンセーショナルに取り上げられがちな「事業の分離」ですが、やり方次第でハッピーセパレートにすることが可能です。

(1)世界中のキャッシュが数えられる、(2)世界中のタレントが見えている、(3)自社の方向性を明確に示せている――。こうした3つの「基本行動」を実践し、そして結果を出し続けているグローバル企業を、著者らは「ワールドクラス」と呼んでいます。

(1)世界中のキャッシュが数えられる、(2)世界中のタレントが見えている、(3)自社の方向性を明確に示せている――。こうした3つの「基本行動」を実践し、そして結果を出し続けているグローバル企業を、著者らは「ワールドクラス」と呼んでいます。

(1)世界中のキャッシュが数えられる、(2)世界中のタレントが見えている、(3)自社の方向性を明確に示せている――。こうした3つの「基本行動」を実践し、そして結果を出し続けているグローバル企業を、著者らは「ワールドクラス」と呼んでいます。

#3
日本経済が低迷を抜け出すために、日本企業はもう一度世界から学びつつ、新しい企業像を模索する必要があるのではないか。そうした視点に立ったウェブセミナー「ワールドクラスの経営」が開催された。同名の書籍の共著者の一人であるボストン コンサルティング グループの日置圭介氏と早稲田大学大学院の入山章栄教授の特別対談を、3回にわたって動画でご紹介。最終回は、ワールドクラス企業の「あうんの仕組み」と「価値観」に焦点を当てる。

#2
日本経済が低迷を抜け出すために、日本企業はもう一度世界から学びつつ、新しい企業像を模索する必要があるのではないか。そうした視点に立ったウェブセミナー「ワールドクラスの経営」が開催された。同名の書籍の共著者の一人であるボストン コンサルティング グループの日置圭介氏と早稲田大学大学院の入山章栄教授の特別対談を、3回にわたって動画でご紹介。第2回は、ワールドクラス企業の「キャッシュ感覚」と事業の「起こし方とたたみ方」に焦点を当てる。

#1
日本経済が低迷を抜け出すために、日本企業はもう一度世界から学びつつ、新しい企業像を模索する必要があるのではないか。そうした視点に立ったウェブセミナー「ワールドクラスの経営」が開催された。同名の書籍の共著者の一人であるボストン コンサルティング グループの日置圭介氏と早稲田大学大学院の入山章栄教授の特別対談を、3回にわたって動画でご紹介。第1回はワールドクラスの経営の5つの経営行動に焦点を当てる。

第15回
2021年6月11日に施行されたコーポレートガバナンス・コード改訂版では、サステナビリティ重視の姿勢が見られる。日本企業のこれまでのサステナビリティに関する活動の多くは、きれいな言葉でぼんやりとした目標を掲げた「本業に付加的な」活動にとどまる。そこに欠けているのは「どこで、どう稼ぐか」というストラテジック・インテント(戦略的意図)だ。200年企業デュポンで、事業ポートフォリオやリソース配分の大胆な組み替えにあたった橋本勝則・前副社長に、持続可能な経営について聞く。

第14回
2021年6月11日、コーポレートガバナンス・コードの改訂版が施行された。サステナビリティ、取締役会の機能発揮、ダイバーシティなどの企業課題への対応において、ワールドクラス級の水準を要求しているが、世界の常識からすれば日本の状況は後れを取っており、「稼ぐ力」の向上を掲げたガバナンス改革は道半ばにすぎない。世界水準の経営を熟知する前デュポン副社長の橋本勝則氏に、コーポレートガバナンスの本質を聞く。

第13回
ワールドクラスに後れを取るといわれる日本企業だが、一部は猛スピードでマネジメントを進化させている。変革の起爆剤となったのは、意思と行動力、そして経験値を備えたマネジメント人材だ。一方、多くの企業は平成時代の経営を引き継いだままで、変化やチャレンジは絵に描いた餅である。そして、両者ともに意志あるマネジメントは苦悩している。企業戦略が専門の松田千恵子・東京都立大学教授に、日本企業の「マネジメント不在」について聞いた。

第12回
ワールドクラスの屋台骨を支える“中核”人材の戦略思考や多様なキャリアをアマゾン、ユニリーバ、タタの例で見てきたが、従来のビジネス形態に大きな変化が起きるなか、みな一様に、秀逸な適応力を発揮している。変化の速い環境で、彼らのように組織に貢献する中核人材となるには、20代、30代でどういう経験を積めばいいのか。インド最大の製薬企業、サンファーマの田中伸一ファイナンス本部長が、一つの業界でプロフェッショナルとしての力量を備えるために30代で考えたキャリアのフレームワークは参考になる。

第11回
グローバル市場において圧倒的な強さを見せるワールドクラスだが、業種によって顧客、競合、技術、あるいは規制などの環境は異なる。日本企業でキャリアをスタートし、グラクソ・スミスクライン、ノバルティスなどの欧米系ビッグ・ファーマを経て、現在、インド最大の製薬企業、サンファーマのファイナンス本部長を務める田中伸一氏に、国籍による企業マネジメントの違いについて聞いた。

第10回
新興国市場の視点で製品、サービスの開発を実現する「リバース・イノベーション」が注目を浴びてから早10年。当時、アジア企業のグローバル化の手本として称えられたタタ・グループは、いまやワールドクラスの一角で独自の存在感を示すまでに成長した。傘下のタタ・コンサルタンシー・サービシズ(TCS)は変革の拠点を東京に定め、ワールドクラスとは一味違う手法を猛スピードで展開する。日本TCSの中村哲也専務に、タタ流グローバル経営について聞いた。

第9回
ビジネスモデルのイノベーションや組織変革が求められるいま、企業経営の任に当たるのはだれにとっても難しい。実際、方法ははっきりしないし、変革の多くは失敗している。経営者は時節の不運を嘆きたくなるかもしれない。しかし、忘れてはならないのは、どこの国、いつの時代にも「個別の事情や特殊性」はあるということだ。ワールドクラスも、大きな環境変化を経験し、それを乗り越えて、現在がある。では、日本企業の現状はどうか。世界水準の経営に追いつく可能性はあるのだろうか。

第8回
個人とチームが変化を創り出し、その力を伸ばし続ける組織はメンタリングとコーチングが機能している。これは、「学習する組織」の考え方と手法を確立したアメリカの経営学者、ピーター・センゲがイノベーションを実現するための要素として提示した「5つのディシプリン」のキーコンセプトでもある。その実践のプロセスについて、NECでグローバル組織への変革を牽引するグローバルビジネスユニットCFOの青山朝子さんに聞いた。

第7回
グローバル活動が進展するほど、経営層は自分の思想やリーダーシップをグローバル組織に行き渡らせることが難しくなる。どうすれば国をまたいで文化の違いを超えて、「ワン・カンパニー」を実現できるかーー。それにはさまざまな仕掛けと行動が必要になってくる。今回、そのチェックシートを用意した。これについて、ユニリーバとアマゾンのマネジメントに聞いた。

第6回
リーダーがリーダーであるための要件に、「フォロワーがいること」を挙げたのは、マネジメントの父ピーター・ドラッカーだ。彼の死後、世界は不確実性を増す一方で、いかに卓越したリーダーであっても、1人でパーフェクトストーム(究極の嵐)のなかを進むことは不可能になっている。見通しのきかない道を進むには、経営のプロフェッショナルで構成されたチームが欠かせない。CFOやCLOの育成に携わってきた日本CFO協会の谷口宏専務理事との対話を通じて、新たな経営チーム像を探る。