橘慶太
#6
相続税を節税するテクニックとしてよく利用される不動産。しかし、過度な節税に税務当局が目を光らせている。加えて相続ルールの改正で、不動産を巡る新たなトラブルも生じ始めた。相続専門税理士の橘慶太氏に、最新の相続の不動産事情について解説してもらった。
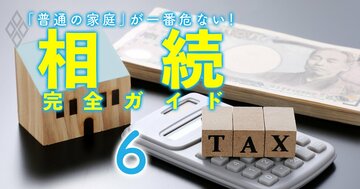
#5
相続税の税務調査ではいったい何が狙われるのか。相続専門税理士の橘慶太氏は、税務署の調査官が疑いの目を向ける「通帳」には共通点があると指摘する。税務署の調査官が税務調査で目を光らせるポイントを橘氏に指南してもらった。
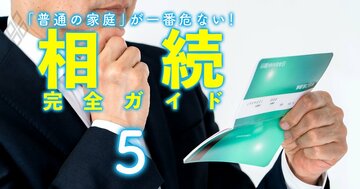
#4
税務署にタンス預金はバレますか?相続専門税理士の橘慶太氏にはこんな相談がよく寄せられるという。しかし、「高確率でバレる」と橘氏は断言する。税務署がタンス預金を見抜く理由と狙われるターゲットについて橘氏に解説してもらった。

#3
相続税はいくらかかるのか。遺産は自由に分けられないのか。相続は断片的な知識で準備をすると痛い目に合う。相続税と遺留分という相続トラブルを招きやすい超重要な2大基礎知識について、相続専門税理士の橘慶太氏に解説してもらった。
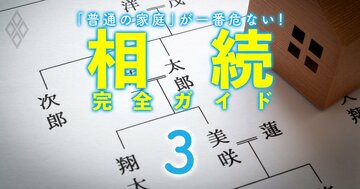
#2
「7月中旬」の税務調査に要注意!?相続税対策で欠かせないのが税務署対策だ。税務署は何を狙っており、いつ来るのか。「税務調査を絶対に甘く見てはいけない」と警鐘を鳴らす相続専門税理士の橘慶太氏に税務調査の裏事情を解説してもらった。
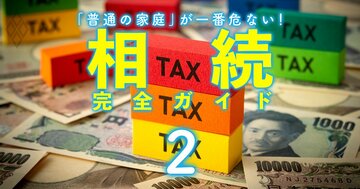
#1
親の死を巡る相続で、遺族に亀裂が生じることは珍しくない。相続で最も重要なことは事前の準備だ。絶対に知っておきたい相続の基本について、相続専門税理士の橘慶太氏に解説してもらった。
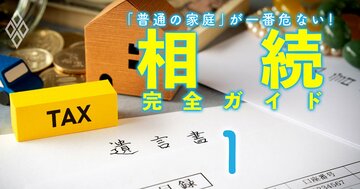
税務署が厳しくチェックする「自宅売却の特例」
税務署が厳しくチェックする「自宅売却の特例」とは? 3000万円の特別控除が受けられる特例ですが、使用するにはさまざまな条件があり、税務署はそこを厳しくチェックします。

「ゴルフ会員権を売るなら春か秋」その意外な理由とは?
ゴルフ会員権を売るなら、春か秋がオススメ! その理由は? ゴルフ会員権の相続手続を徹底解説!

「身近な人が亡くなり、誰も知らない遺産が見つかったら?」トラブル回避策2選
身近な人が亡くなったとき、誰も知らない遺産が出てきたら? 2つの対策をご紹介します。

「貸金庫を勝手に開けてはいけない!?」身近な人が亡くなったときの注意点
「身近な人が亡くなったとき、貸金庫があったらどうする?」手続の流れとポイントを見てみましょう。

75歳以上の人が亡くなったら、「保険手続」は14日以内に!
75歳以上の人が亡くなったときの「保険手続」を解説します。手続の流れと必要書類を見ていきましょう。

身近な人が亡くなったら、スマホはどうする? 解約のポイントを解説!
身近な人が亡くなったら、スマホや固定電話の解約等を行う必要があります。手続の流れとポイントをお伝えします。
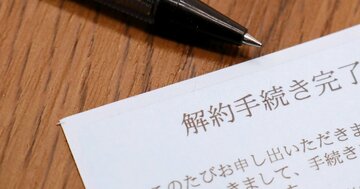
自営業者が亡くなったときの「保険手続」、残された家族がすぐやること
自営業者が亡くなったときの「保険手続」を解説します。手続の流れと必要書類を見ていきましょう。

「不動産を相続したけど放置」は危険! 3年放置でペナルティ!?
相続登記が義務化されます。過去に不動産を相続して名義変更をしないまま放置しているすべての人が、罰則の対象になる予定です。詳しく見ていきましょう。

「故人の確定申告」をやさしく解説! 期限に気をつけて!
準確定申告(故人の確定申告)のやり方を解説します。必要書類、申告書の書き方、期限など、やさしく解説します!

身近な人が亡くなったら、生命保険金はどう受け取る? NG行動も解説!
身近な人が亡くなったときの「生命保険金の受取手続」を解説します。基本的な流れと「やってはいけないNG行動」も説明します。

身近な人が亡くなったら、「準確定申告」に要注意!
故人が生前中に得ていた収入については、相続人が代わりに確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。手続のポイントを解説します。
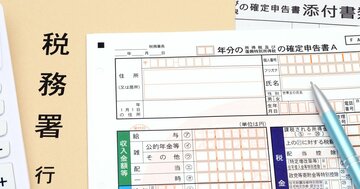
「家族仲が悪いから、遺産は寄付しよう」は危険!? 寄付トラブルに注意!
「遺産の一部を寄付したい」と考えている人は意外と多いのですが、寄付に反対する相続人が多いのも事実です。トラブルを避けるための考え方を紹介します。

身近な人が亡くなったら、免許証やパスポートは放置OK? リスクは?
身近な人が亡くなったとき、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードはどうすればいいのでしょうか? 手続のポイントを解説します。

身近な人が亡くなったら、水道・ガス・電気の放置は厳禁です
公共料金は、ご家族が亡くなられた後、誰も使わないなら解約をし、残されたご家族が使うなら契約者変更手続が必要になります。ポイントを見ていきます。
