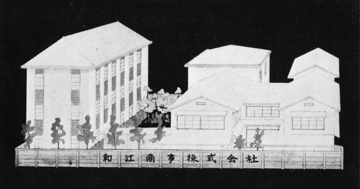黒船の襲来
時代の波に乗って大きな飛躍を夢見ていた幸一の前に、大きな壁が立ちはだかろうとしていた。
アメリカを代表する下着メーカーであるラバブル・ブラジャー社の技術指導の下、日本ラバブル・ブラジャー社が設立されたのである。幸一たちにとって、それはまさに“黒船”であった。
 昭和27年から東京出張所が入っていた人形町のビル。東京銀行の看板が見える
昭和27年から東京出張所が入っていた人形町のビル。東京銀行の看板が見える
この情報は、昭和28年(1953年)の9月下旬ごろ、東京出張所のはいっていたビルの1階にある東京銀行の支店長がこっそり耳打ちしてくれたものだった。東京銀行は外為専門銀行であるため外資系企業と関係が深い。藪中の訴えで無理してこのビルに出張所を移した甲斐はあったと幸一は思った。
聞くと、すでに同社は8月に設立されているという。いつも機先を制してきた幸一が、逆に奇襲をかけられたのだ。
国内メーカーはどこも自社生産率が低く下請けに依存している。
この当時、糸や布を作るメーカーは大企業がたくさんあっても縫製業者は中小企業と相場が決まっていた。
庶民の多くはみな生地を買ってきて、自分で寸法を測って自分で仕立てるか、仕立て屋に頼んで着物を仕立てていたからだ。一反の布地を使い切ることを“反つぶし”というが、縫製業者は“つぶし屋”という一種の蔑称でよばれていたほどだった。
(これから日本女性が洋装化することで市場は急拡大する。それだけではない。手先の器用な日本人にとって、繊維加工産業は世界と十分太刀打ちできる重要な産業だ)
幸一は、これからは縫製業者の時代が来る。そしてそれこそがこの国を支えるのだと信じて疑わなかった。
そんな矢先の「黒船来襲」であった。
下請けの一社でも彼らと提携して押さえられたら、商品の供給がとどこおってしまう。当時の日本人の欧米崇拝と彼らの巨額な宣伝費を考えれば、日本市場がまたたく間に席巻されてしまうことも十分予想される。
幸一はかつてない激しい緊張感に襲われていた。