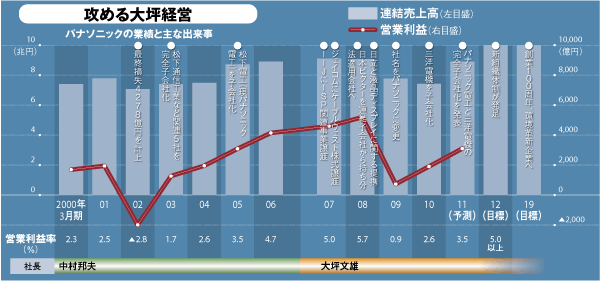パナソニックは子会社のパナソニック電工と三洋電機を4月1日付で完全子会社化。そして、パナソニックを含む3社を事業ごとに解体して、新たな事業ドメインに再構築し直す。目指すは、創業100周年を迎える2018年に、環境とエナジーを軸にした「環境革新企業」に変貌することだ。巨艦パナソニックはどのように変革しようとしているのか。その姿を追った。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 藤田章夫)
※本稿は「週刊ダイヤモンド」2011年3月19日号に掲載されたものです。
2月22日に発表された役員人事。パナソニック社内に衝撃が走った一方で、完全子会社化され、事業ごとに解体されて各事業ドメインに組み込まれるパナソニック電工と三洋電機社内には安堵のため息が広がった。
その人事とは、長榮周作・パナソニック電工社長と佐野精一郎・三洋電機社長が揃ってパナソニックの専務役員に就任することに加え、松蔭邦彰・パナソニック電工常務取締役がLED照明などを扱うライティング社社長に、伊藤正人・三洋電機取締役専務執行役員が、電池事業を営むエナジー社社長に就任して、共にパナソニック役員に名を連ねることだ。
とりわけ、パナソニック社員にとって衝撃的だったのは、エナジー社のトップに三洋出身者が就いたことだった。もっとも、よく知られているとおり、繰り返し充電して使える2次電池や太陽電池事業は、三洋がパナソニックを圧倒している。パナソニックが巨費を投じて三洋を買収したのも、電池事業が欲しかったからにほかならない。であれば、三洋が電池事業のトップとなるのも理にかなう話だが、事はそう単純ではない。
エナジー社といえば、旧松下電池工業のことで、乾電池や2次電池などを製造・販売する社内分社の一つ。その歴史は1918年の創業時にまでさかのぼる。創業して数年後に自転車に取り付ける電池内蔵型のランプを発売し大ヒット。その収益が屋台骨を支えたという。この電池こそが、エナジー社の起源であり、パナソニックにとって「電池事業は当社の“祖業”」(パナソニック幹部)というほど思い入れの強い事業なのだ。
しかも、である。現在エナジー社を率いる野口直人・エナジー社社長は、大坪文雄・パナソニック社長と同じオーディオ畑出身で、シンガポールで子会社の経営を行った経歴も同じ。大坪社長の信任が厚い人物なのだ。その野口氏を降ろし、三洋の伊藤氏をエナジー社のトップに据えたのは、「野口氏の性格ではパナソニック側を守ろうとし、融合に時間がかかると見たのだろう」(前出の幹部)。三洋の電池事業を速やかに進めるため、大坪社長が合理的な判断を下したものと見られる。