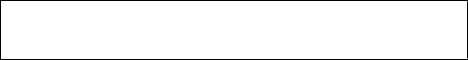競馬の世界は3歳馬の伝統レースが行われる春のクラシックシーズンの真っ盛りだ。第1弾の桜花賞では、ディープインパクトの初年度産駒マルセリーナが優勝した。このディープインパクトの父が、日本の競馬史で空前の大成功を収めたサンデーサイレンスだ。吉沢譲治氏の新刊『血のジレンマ』(NHK出版)を読むと、サンデーサイレンスを中心に競走馬の種牡馬をめぐる経済がよくわかる。じつに深くて、かつおもしろい。
競馬は、馬券の世界が株式市場のような資本市場と多大な共通性を持っている点で研究対象として興味深いが、不確実性を抱えた巨額の投資と経営が絡む生産の世界も企業の投資活動に似ている。
サンデーサイレンスは1989年の米国の年度代表馬となった名馬だが、日本の社台ファームが全権利を取得して輸入し、1株4150万円×60株の総額25億円でシンジケートを組んだ。
種牡馬は産駒が走ってみなければその成否がわからないリスクの大きな投資対象だ。現に、サンデーサイレンスを意識して輸入され総額44億円強でシンジケートを組まれたラムタラはまったくの期待はずれに終わった。シンジケートは、株式会社のようなリスクの分散保有の仕組みになっている。
サンデーサイレンスは種牡馬として12世代の産駒を送り出したが、この中からダービー馬を6頭輩出した。ダービーで5割とは想像を絶する高勝率だ。シンジケートの配当は毎年1億円前後に上ったらしい。空前の高収益だ。
しかも、初年度産駒のフジキセキ以下の実績馬が相次いで種牡馬入りすると、次々と活躍馬が出た。サンデーサイレンスの血を引く競走馬が次々と競馬場に現れ、レースの賞金をさらっていった。
産業にたとえると、IT関連業が突然現れたような快進撃であった。サンデーサイレンスおよび、サンデー系の種牡馬の産駒に人気と需要が高まり、この傾向がサンデー系の種牡馬に種付け料の高水準をもたらすことになった。