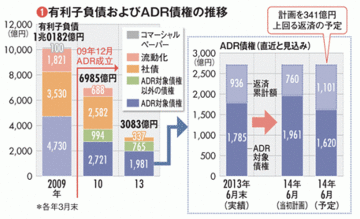本連載では、『入門 社債のすべて』より、具体的なケーススタディを挙げながら、社債投資で注意すべき視点を紹介していきます。3回目はアイフルです。武富士はじめ業界中が過払金問題で大揺れのなか、倒産するかしないか、いかに見極められたのでしょうか。
2009年9月18日、産業活力再生特別措置法所定のADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続き)を利用した経営再建方針を発表したアイフルは、クレジット市場において、社債もローンも随分と話題になりました。参加者も多岐にわたり、価格も大きく動きました。金額が大きかったこともあり、今後も語り継がれることになるでしょう。当時、世界中の投資家が注目し、実際に取引も活発に行われたアイフル債権投資について振り返ります。
 分析しやすくスプレッドが上乗せされているのが特徴だった消費者金融セクター
分析しやすくスプレッドが上乗せされているのが特徴だった消費者金融セクター
クレジット分析の世界において消費者金融業は、そのシンプルな事業構造からくる分析のしやすさが特徴のセクターでした。さらに、業態を理由に投資対象としていない投資家も相応に存在したことから、格付対比では恒常的にスプレッドが上乗せされて発行されていました。
債券運用では運用成績を評価する基準として、高格付銘柄を平均的に買った場合の運用利回り(インデックス)が使われることが多いのですが、そのインデックスよりも良い運用成績を上げようとすると、同じ格付でも上乗せスプレッドの厚い銘柄を多めに組み入れる必要があります。その意味で不可欠だったのが、消費者金融セクターの組み入れ比率を高くすることでした。
過払金返還請求を機に業界のクレジット評価が急落
業績も絶好調で、この世の春を謳歌していた消費者金融業界に異変が起きたのは、事業者金融会社シティズが、最高裁判所でみなし弁済に関して敗訴してからです。業界全体をまさに震撼させた判決であり、それ以来、過払金返還請求の嵐が吹き荒れることになります。
以来、消費者金融業者に対するクレジット評価も一変しました。
計算上では過払金の返還請求がすべてきてしまえば、全業者が債務超過になり、そもそもそれだけの払い出しをするだけの現金を用意することは不可能でした。理屈のうえではすべての消費者金融業者が倒産してしまうことになります。実際に過払金の嵐は消費者金融業者を直撃して、数千社あった消費者金融業者が次々と倒産していきます。そして市場の関心は大手の倒産リスクへと移り、業界最大手の武富士の信用不安がどんどん高まっていきました。
どんなに状況が悪くても、さすがに大手4社の倒産は当局が認めないのではないかという意見もありました。しかし、武富士のクレジットリスクテイクに慎重だった投資家層は、武富士の調達が外資系に偏重しており、国内有力金融機関がメイン行としてついていないことを重要視していました。
最終的に武富士は法的処理へと進みましたが、その場合の回収率に重大な影響を与える過払金請求に関して、市場の予想を裏切る動きが発生します。倒産手続きのルール上、知れたる(判明している)債権者に対して、過払金として請求できる金額を債務者(武富士)側から通知しなければなりません。ただプライバシー保護の観点から、消費者金融ではそういう通知はなされないだろうと思われていました。にもかかわらず、通知が実施されてしまったのです。
この結果、武富士向け無担保債権の回収率は大幅に低下することが見込まれ、ディストレスト投資家間での武富士向け破綻債権価格は急落しました。結果的に、武富士無担保向け債権の回収率はわずか3%にしかなりませんでした。100円で買ったものが3円しか返ってこないのですから、まさに紙くずの状態でした。
特徴的だったADRの採用
武富士が倒産したことにより、もう一つの独立系であるアイフルも倒産してしまうのではないかという思惑が市場に一気に広がり、債券価格もさらに下がりました。この時点でアイフルが最終的に倒産しないと予想できたなら、巨額の利益をあげられますが、倒産してしまえば損失も巨額になります。決して簡単ではないが大儲けのチャンスが訪れました。
アイフルのリスクをとる方法は、基本的に2種類でした。ひとつは、公募債を流通市場で購入することであり、もうひとつは、金融機関がアイフル向けにもっていた貸付債権を債権譲渡によって譲り受けることでした。公募債は発行済のものが多く残っていましたし、貸付債権については、CDS(クレジットデフォルトスワップ)の精算手続きの中で、市場に貸付債権が放出されました。
さらにアイフルの特徴として挙げられるのは、ADR(裁判外紛争解決手続き)の対象とされたことでした。
ADRは私的整理の枠組みで行われるため、融資の条件変更などはすべての債権者の全員一致でなければなりません。融資であればお金を貸している銀行等を全て集めて合意を取ることは不可能ではありませんが、だれが持っているかもわからず、一人あたりの額が少額たりえる債券では全員一致で何かを決めるのは実務的に不可能です。
そういった事情から、ADRによるアイフルの再建計画では、公募債は無傷で金利の減免や額面の減額、期間の延長もなく、償還日に全額償還すると決めざるを得ませんでしたが、ADRは銀行借入の満期の延長(リスケジュール、通常「リスケ」)を伴うものであったため、格付会社は格付を選択的債務不履行とし、社債の格付も大幅に格下げされました。
ところが、消費者金融業の場合は毎月貸付金からの弁済金収入があり、その資金を新たな貸出に使わなければ、自己の債務の返済資金を捻出できる、というビジネスの構造から資金ショートが発生難い状態でした。ここで格付けの意味するところと実際の倒産リスクに乖離が発生し、公募債に高い投資妙味が発生したのです。
当時のアイフルクレジットに投資していた中心的主体は、海外ヘッジファンド、外資金融の自己勘定部門、海外の富裕層でした。投資家の関心は「いつになったら過払金請求が減速し、年間の利益の範囲内で収まるようになるか」の一点でした。過払金に関しては、基本的に有限であること、対象者全員が申請する可能性は非常に低いと思われていたこと等から比較的早く鎮静化すると思われていました。ところが、過払金の申請は、想定よりも明らかに減少ペースが遅く、いつまでたっても減る気配を見せませんでした。
その理由はいろいろと報道されていますが、一番多く指摘されていたのは、過払金請求ビジネスが、弁護士・司法書士にとって収益的に極めて魅力的であったことでした。弁護士・司法書士による過払金請求者の掘り起こしは執拗に続き、テレビや電車の広告等にも過払金請求に関する広告が後を絶ちませんでした。
また、倒産した武富士や三洋信販の顧客リストが流失したという噂もありました。消費者金融からお金を借りる人は1社に限らない場合が多く、大手の顧客リストを不正入手できれば宝の山を手にしたのも同様です。かくして、アイフル向け債権価格は、過払金申請件数の推移にリンクする状態が続きました。
アイフルがその後、最終的にADRを卒業するまでは長い道のりでした。ADR最終局面における外資系金融機関やヘッジファンドとの交渉も熾烈を極めますが、最終的に無事にリファイナンス(借り換え)に成功し、途中でアイフル向け債権や公募社債を額面以下で売却した投資家や金融機関以外は損失を被らずに終了したのです。その意味では、アイフルに関するクレジット投資の収益の源泉は、額面で購入した投資家や融資を提供した金融機関が売却時に被った大幅な損失が、額面を大きく下回る価格で購入した投資家に移転したものでした。
損失を被った投資家や金融機関の多くは、同社のキャッシュフローや過払金の状況を十分に調査・分析したうえでの判断ではなかったのでしょう。社内ルールに従うなど、クレジットリスクとは別次元の理由により実損を伴う処分を選択したと思われます。したがって本件に関しても、信用リスク分析力で投資リターンに差が出たのではなく、組織的なルールや人事評価システムの歪みをついた、いわば制度のアービトラージ(裁定取引)が行われたと考えるのが妥当ではないかと思っています。
独立系であることとリスク評価の関係
アイフルが、同業のアコムやプロミスと決定的に異なったのは、独立系であった点です。アコム、プロミスは大手メガバンクの傘下に入ったことから、信用リスクも流動性も、まったく問題がないものと見なされました。一方のアイフルは、あくまで独立維持を貫き、かえってその点がクレジット評価にはマイナスにとられました。
経営の独立性を維持できれば、今後復活した後に高い株式の価値が発生し、経営権も維持できるため、苦しくても独立を維持することには現経営者にとっては大いに意味があります。しかし、倒産してしまっては株式の価値はゼロとなってしまいます。もし、そこまで追い詰められてしまったら、そのときに売却すれば経営権は失ってしまうかもしれませんが、売却代金をもらうことができます。倒産なら、すべてを失うだけです。
アイフルは、本業の収益力低下に苦しむ銀行にとっても格好の買収対象であり、海外のファンドも含めて、売却しようと思えばいつでも売却できる状況でした。つまりクレジットリスクの観点からは、アイフルが独立にこだわっているから倒産リスクが高いと考えるのは誤りなのです。
もちろんアイフルの場合、投資家も金融機関も信用リスクの低い、安全な投資対象だと思ったから取引を始めたので、クレジットが悪化した場合の対応が十分でなくなってしまったことに関しては責められない部分も多いでしょう。しかし、もったいない展開になったことは確かです。過払金の負担や武富士の倒産に惑わされず、同社の資金繰りを冷静かつ精緻に分析した投資家が大きな利益をあげました。
※本連載の内容および意見は筆者個人によるもので、筆者の所属する企業・団体などの意見を代表するものではありません。