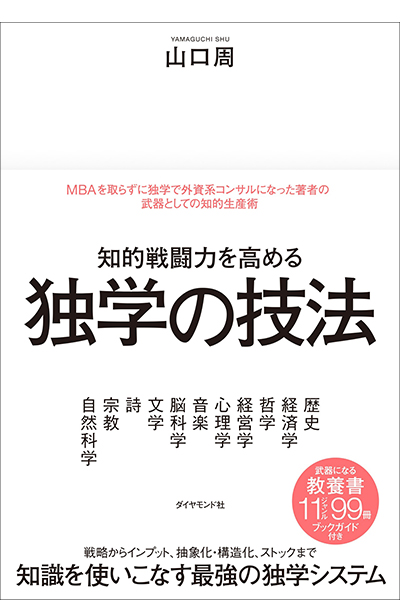日本ではあまり馴染がないが、欧州のエリート養成機関では昔から哲学が必須とされてきた。「自分で考える力」を養うには、ルールやシステムそのものを疑える哲学思考が必要だからだ。では、哲学という「疑いの技術」をどう学べばいいのだろうか? MBAを取らずに独学で外資系コンサルタントになった山口周氏が、知識を手足のように使いこなすための最強の独学システムを1冊に体系化した『知的戦闘力を高める 独学の技法』から、内容の一部を特別公開する。
いまのルールに疑問を感じ、自分の頭で考える力を鍛える
――哲学には必ず大きな「否定」が含まれている
多くのビジネスパーソンにとって、哲学という学問はもっとも「縁遠い」ものに感じられると思います。しかし、実は一方で、欧州のエリート養成機関では18世紀以来、哲学は歴史と並んで、もっとも重要視されてきた学問でもあります。
たとえば英国のエリートを多く輩出しているオックスフォード大学では、長いこと哲学と歴史が必修でした。現在、エリート政治家養成機関としてオックスフォードの看板学部となっているのは「PPE=哲学・政治・経済」です。
日本の大学システムに慣れ親しんだ人からすると、なぜに「哲学と政治と経済」が同じ学部で学ばれるのかと奇異に思われるかもしれませんが、これはむしろ「世界の非常識」である日本の大学システムしか知らないからこそ感じることで、哲学を学ぶ機会をほとんど与えずにエリートを育成することはできない、それは「危険である」というのが特に欧州における考え方なのです。
たとえばフランスを見てもわかりやすい。フランスの教育制度の特徴としてしばしば言及されるのが、リセ(高等学校)最終学年における哲学教育と、バカロレア(大学入学資格試験)における哲学試験です。
文系・理系を問わず、すべての高校生が哲学を必修として学び、哲学試験はバカロレアの1日目の最初の科目として実施されます。バカロレアに合格する学生は、将来のフランスを背負って立つエリートとなることを期待されるわけですが、そのような試験において、文系・理系を問わず、最重要の科目として「哲学する力」が必修の教養として位置付けられているわけです。
では、哲学を学ぶことにはどんな意味があるのか?一言でいえば、それは「自分で考える力を鍛える」ということです。この「考える」という言葉は本当に気安く使われる言葉なのですが、本当の意味で「考える」ということは、なまなかなことではありません。
よく「一日中考えてみたんだけど……」などと言う人がいますが、とんでもないことで、こう言う人がやっているのは「考える」のではなく、単に「悩んでいる」だけです。
これは拙著『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』にも書いたことですが、現在、この「自分で考える力」は極めて重要な資質になりつつあります。なぜかというと、これまでに依拠してきた「外部の基準やモノサシ」がどんどん時代遅れになっているからです。
知的戦闘力を高めるという文脈で考えてみた場合、与えられたルールやシステムを所与のものとして疑うことなく受け入れ、その枠組みの中でどうやって勝とうとするかを考える人よりも、与えられたルールやシステムそのものの是非を考え、そもそもルールを変えていこうとする人の方が、圧倒的に高い知的パフォーマンスを発揮するのは当たり前のことです。
もっとわかりやすく言えば、哲学というのは「疑いの技術」だとも言えます。哲学の歴史において、哲学者たちが向き合ってきた問いは基本的に二つしかありません。それは、(1)この世界はどのようにして成り立っているのか?(2)その世界の中で、私たちはどのようにして生きていくべきなのか?という問いです。
そして、古代の中国、あるいはインド、あるいはギリシアからスタートした哲学の歴史は連綿と続くこれら二つの問いに対する答えの提案と、その後の時代に続く哲学者からの否定と代替案の提案によって成り立っています。
哲学の提案には必ず大きな「否定」が含まれていなければなりません。物理の法則と同じで、なにか大きな「肯定」をするためには、何か大きな「否定」が必ずつきまとうのです。
つまり、世の中で主流となっているものの考え方や価値観について、「本当にそうだろうか、違う考え方もあるのではないだろうか」と考えることが、「哲学する人」に求められる基本的態度だということになります。
さらに付け加えれば、この「本当にそうだろうか」という批判的疑念の発端となる、微妙な違和感に自分で気づくこともまた、重要なコンピテンシーです。
昨今、世界中で瞑想を中心としたマインドフルネスに関する取り組みが盛んです。マインドフルネスと哲学というと、あまり結節点はないように思われるかもしれませんが、「自分の中に湧き上がる、微妙な違和感に気づくのが大事」という点で、両者は共通の根っこを持っているのです。