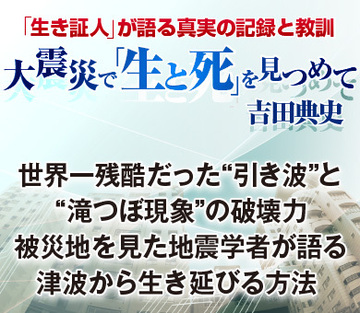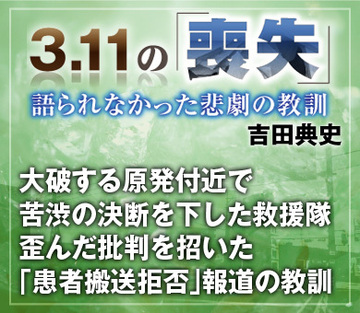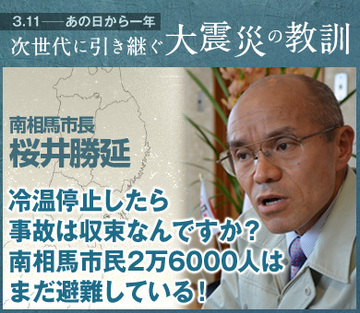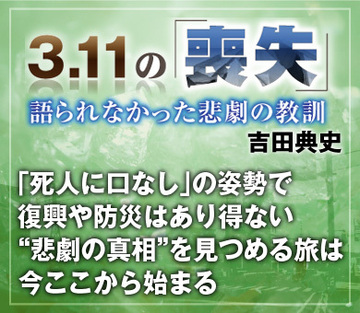3月11日、「震災発生1年」という節目に様々なイベントが行なわれた。その多くは、「お祭り」のような内容に筆者には見えた。少なくとも、1年前の震災の実態を冷静に見据え、教訓を生かすものではなかった。
今回は、津波の研究を第一線で長く続けてきた研究者に取材を試みることで、改めて震災の実態を浮き彫りにし、今後の危機管理を考える。
集落が海と化した石巻市の長面地区
“切ない”を通り越して悲劇に思えた
 (上)東京大学地震研究所の都司嘉宣・准教授。(下)東京大学地震研究所(東京・文京区)。
(上)東京大学地震研究所の都司嘉宣・准教授。(下)東京大学地震研究所(東京・文京区)。
「あの光景を見ると、復興に向けて政治が機能していないことがよくわかる。その意味では、人災とも言える」
東京大学地震研究所の都司嘉宣(つじ・よしのぶ)准教授は、こう切り出した。今回は、前連載「大震災で『生と死』を見つめて」の取材(昨年11月)の続編となる。
都司氏は、私が訪ねた日の数日前に、被災地から戻ってきた。ロシアで津波を研究する著名な学者が視察のため来日したので、案内することが目的だった。昨年3月の震災直後から、これで14回目の視察となる。今回もいくつかの地域を訪ね歩いたという。
私は前回に続き、今まで訪れた中で「最も切なくなった場所」を尋ねた。前回の取材では、都司氏は東松島市の野蒜小学校を挙げた。今回は、石巻市の長面(ながつら)地区について語った。
「この地域の実情は、一連の震災報道ではあまり伝えられていない。震災前は、広々とした水田地帯だった。今は見渡す限り、集落は水没し、海になっている。震災による地盤沈下と、堤防が決壊し、津波が押し寄せたことによるものだ。あれでは農業は当分、できないだろう。住民らの今後を思うと、“切ない”という思いを通り越し、悲劇に思えた」
宮城県警によると、この地区には震災前は150前後の世帯があり、520人ほどが住んでいた。震災により76人が死亡し、30人ほどが行方不明のままである(今年2月末時点)。