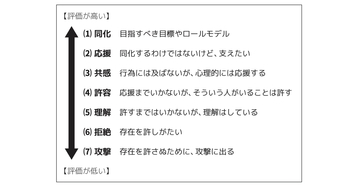人間は、結果を推測して、それが正しかったどうかを検証するトライアル&エラーを本能的に行っている生物です。
そして、ストーリーの中で推測して「正解」していくことに自己肯定という「正」の感情を持つとともに、予想を裏切る「不正解」にも「新たな知見を得た」という「正」の感情を持つのです。
このバランスを、視聴者がウザいと感じない比率で配分することが大切なのですが、そのさじ加減はまさに職人技ですし、そのバランスこそがコンテンツの個性にもつながります。その「職人技」をどうやって修得すればいいかということは、「常に視聴者の気持ちを意識する技術」で培われます。
ぼくは、歴史番組を長くやってきた経験がありますが、歴史番組の中で、もっとも視聴率を持っているのが、「本能寺の変」です。
もはや「本能寺の変」はコスられすぎて「裏切り」が予測できてしまうのに、ワクワクする。もはや「裏切り待ち」。
「明智光秀、早く!」という1周も2周も回った構造ですが、やはり人間は本能的に「本能寺の変」、つまり裏切りが好きなのでしょう。
では、この「裏切り」をどうやってストーリーの中に作っていくのか。
実は、フィクションの世界では、この「裏切り」は古くから意識され、視聴者・読者をひきつける技法として意識的に多用されています。サスペンスドラマもそうでしょうし、ミステリー小説なんてわかりやすくそうです。
というか、フィクションのほぼすべては、どう視聴者・読者の想像を「裏切る」か。あるいは、さらにその一枚上手をいって、「裏切ると思わせて、裏切らない」という「裏切り」をみせるか。その連続だといっても過言ではありません。
その技法を学ぶ上で最近もっとも解りやすかったのが、ディズニー映画の『ズートピア』です。
草食動物と肉食動物が一緒に暮らす世界で、草食動物という非力な立場ながら警察官になったウサギが、そのハンデに負けずに頑張る。そして、肉食動物ばかりが次々消えていくという事件が発生し、その解決に挑むストーリーなのですが、この映画は、本当にすごいです。フィクションにおけるストーリー作りの教科書のような作品です。
何がすごいのか。裏切りが発生するテンポが凄まじく早いのです。YouTubeなど、短尺の動画になれた若年世代でも飽きない、強烈なテンポでの裏切りの連続です。あまりに「裏切る技法」が露骨なのですが、露骨とわかっていても人々を「ストーリー」に引き込ませるすごさがあります。
このテンポの速さは現代的かもしれませんが、フィクションの世界では、こうした「裏切り」を作りだすために、意図的に視聴者・読者に「ミスリード」を与えるという手法をとります。真犯人をあたかも善人かのように描いたり、あるいは、犯人ではない人物にあえて犯人かもと思わせるささやかな描写を少しずつ与えたりする技法です。
これは、「燻製ニシンの虚偽」という古典的な技法です。
燻製ニシンとは、英語の「レッド・へリング」の訳。猟犬の鼻を鍛える際、その燻製ニシンの強烈な匂いで、キツネなど本来の獲物の匂いをあえて紛らわせてわからなくし、その中から本物の匂いを嗅ぎ分けさせる訓練があるという逸話から、「レッド・へリング」という言葉は、慣用表現としてミスリードという意味で使われます。
しかし、フィクションならば、この「燻製の虚偽」は、「裏切り力」の1つとして多用してもいいと思いますが、ノンフィクションにおいては、その用途は限定されるべきだと思います。意図的すぎる「燻製ニシンの虚偽」は、ノンフィクションの根本的な魅力である「リアリティ」を損なうからです。
どういう場合にだけ「燻製ニシンの虚偽」がリアリティを損なわないか。それは、取材時に取材者が実際に体感したミスリードを編集で尊重する、という場合です。
でも、それだけじゃ「奇跡待ち」になってしまいます。「奇跡待ち」とは、なにも頭を働かせず、何か起きるんじゃないかと、根拠なく期待するポンコツ演出を揶揄する業界用語です。
「奇跡」は「待つ」のではなく「起こす」。
これが、ノンフィクション・ストーリーテリングのキモ。これができずに待つだけなら、そんなもん誰が撮ったって同じです。それこそAI(人工知能)にやらせればいい話です。
フィクションでは、これが突き詰められているにもかかわらず、ノンフィクションに関しては、この視点に無頓着なことが多い。なぜなら、あまりに「演出」というものに対する根本的・本質的な、突き詰めた洞察が不足し、「仕掛け」といえば、「ヤラセ」というイメージしか思い浮かばない作り手も多いからです。
だからこそ、チャンスです。
リアルな世界の中に「裏切り」を発見する技法を、新たに発見すればいいだけなのです。
そして、それを見つけられれば、「見たことないおもしろさ」を持ち合わせながら、かつ本能的な「裏切りニーズ」に訴求する、大きな武器になります。