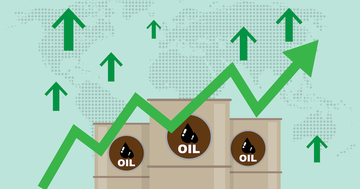原油相場は乱高下の後、やや持ち直しているが、上値の重さも感じられる展開となっている。
9月中旬にはサウジアラビアの石油施設が無人機などによる攻撃を受け、米国産のWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)が1バレル当たり63.38ドル、欧州北海産のブレントが同71.95ドルまで急騰した。それまで安定供給元と認識されていたサウジが攻撃され、地政学リスクに対する原油の脆弱性を意識せざるを得なくなり、イランとサウジ・米国との対立も厳しさを増した。
その後、サウジ施設の修復が予想以上に迅速だったことや、地政学的な対立も懸念されたほど激化しなかったことから、相場は落ち着いた。10月上旬には、米国景気指標の悪化などを背景にリスク資産全般とともに原油も売られ、8月上旬以来の安値を付けた。
しかし、10月11日には、米中両政府が農産物や為替など特定分野で部分的に暫定合意する公算が大になったことで、同月15日に予定されていた米国による対中制裁関税第1~3弾の引き上げは延期された。米中貿易協議の進展への期待が高まり、エネルギー需要の減退懸念が和らぐ流れになった。
APEC(アジア太平洋経済協力会議)首脳会議がキャンセルされ、米中協議進展への期待はいったん萎んだものの、11月に入って米中当局者の前向きな発言などにより再び期待が持ち直した。
もっとも、主要消費国の景気指標は、底堅さや下げ止まりの兆しを示すものもあるものの、まだ弱めの推移を続けているものが多く、石油需要の先行きを慎重にみる傾向が続いている。
一方、供給面を見ると、米国のシェールオイルの増勢は一時に比べれば鈍化しているが、依然として増産傾向が続くと見込まれる。油田開発の先行指標である石油掘削リグの稼働数は、2017年4月以来の水準にまで低下しているものの、開発効率の向上などから産油量減少につながっていない。
12月5~6日にはOPEC(石油輸出国機構)総会やロシアなど非OPEC産油国も加えたOPECプラスの閣僚会合が開催される。減産幅が拡大されるとの見方や、減産強化はあっても期間延長にとどまり、減産幅拡大は行われないとの見方などが出ている。現時点では、現行の協調減産の期限である20年3月まで、各産油国の減産目標の順守を徹底しつつ、需給バランスの状況を注視するといった判断になりやすいだろう。
原油相場は、サウジへの攻撃で変動幅が大きくなった場面もあったが、その後は、上値も下値も限定されている。当面、相場を取り巻く環境は大きく変わらず、狭いレンジで推移すると見込まれる。
(三菱UFJリサーチ&コンサルティング調査部主任研究員 芥田知至)