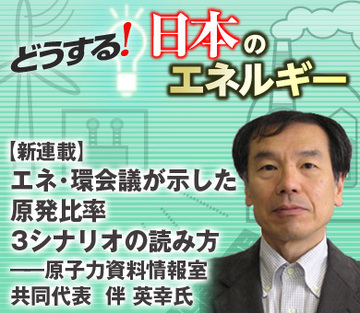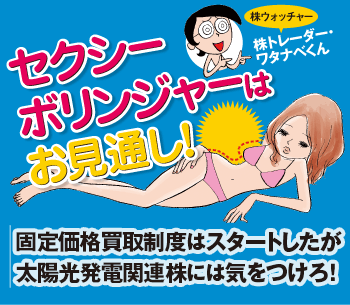東日本大震災の後、日本には復興に向けた新たな絆を手にするかもしれないという期待があった。しかし、今、原子力発電を巡る意見の対立は社会に深い溝を刻もうとしている。そして、新しくできる管理の仕組みも国民の納得感を得るには至っていない。その理由は、日本がエネルギーシステムという社会の基盤をいかにガバナンスするか、という視点が欠けているからだ。
産業革命が現代社会の豊かさに通じる発展の転機となったのは、社会を動かす基盤となるエネルギー革命としての側面があったからだ。エネルギーを自由に操れるようになったことで、社会の発展のスピードは飛躍的に向上した。一方で、エネルギーに対する国際的な利権は幾度となく大きな争いの種となった。だからこそ、エネルギーシステムをいかにガバナンスするかは、国にとっての重大なテーマとなるのである。ここでは、三つの点から日本が直面している問題について論じることとする。
決定のプロセスと
政府の責任とは
現在、政府は2030年段階での原子力発電の位置づけに関する国民的議論を進めている。まず、国民の声に耳を傾けようとしている姿勢自体は、東日本大震災以前の閉鎖的な議論よりは、はるかに進歩したものと受け止めなくてはならない。テレビや公開討論会等の場での議論そのものを批判する向きもあるが、エネルギーという重要な社会基盤の在り方について、広く国民の声に耳を傾けるのは当然である。
その上で問題なのは、議論が原子力発電の是非という点に矮小化されていることと、実現性の異なる選択肢を提示していることだ。
政府が提示している選択肢について考えてみよう。高温高圧に加え放射能にさらされる原子力発電設備の稼働年数を制限することには妥当性がある。仮に、政府が示しているように原子力発電所の稼働年数の上限を40年とすれば、2030年には原子力発電の設備容量は概ね半減する。また、仮に国民が安全な原子力発電所の再稼働を受け入れたとしても、活断層の存在、安全対策の不備、老朽化、などにより再稼働を断念せざるを得ない原子力発電所がある程度出てくる。100%復帰はもはや選択肢にはないと考えるべきである。そうなると、原子力発電のシェアは現状の3割弱から10%台前半まで低下する。