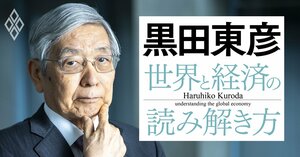Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
フレームワークとは「思考の枠組み」のこと。元マッキンゼーで、現在は経営者へのエグゼクティブコーチング、人材戦略コンサルティングを行う大嶋祥誉氏が、新刊書『超速フレームワーク』を上梓。本書からの抜粋で、本当に使える実用性・汎用性の高い鉄板フレームワークをわかりやすく紹介していく。今回は、問題の本質をあぶり出し、真の原因を明らかにする問題解決の手法「So What?」の使い方をレクチャーする。
真の問題をあぶり出すために
「イシュー」を特定する
ビジネスに限らず、世の中で起こっている現象には必ず何らかの原因があります。ところが、その現象をもたらしている本当の原因を探らずに、目の前にある問題や、現象だけで判断してしまうと問題は解決しません。かえって問題を深刻化・複雑化させてしまう可能性もあります。
問題解決で必要なのは、ある現象の解釈について、「本当に、そうなのか?」と疑うことです。
「そもそも真の問題は何か?」「そもそも何が原因なのか?」「そもそも、どうしたいのか?」
このように自分自身に問いかけながら、創造的かつ論理的に「真の問題」をあぶり出さなければいけません。そして「イシュー」(issue)を特定する必要があります。
イシューとは、一般的には「論点」「課題」「問題」などと訳されますが、問題解決においては、論理を構造化する際に、その場で「何を考え、論じるべきか」を指します。ここでは問題解決のカギとなるという意味も込めて「もっとも重要な課題」と定義します。
「イシューを特定する」場合は、「何を考えるべきか?」「相手の関心事は何か?」を熟考し、「考え、論じる目的」を押さえる必要があります。