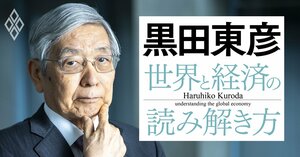Expect the unexpected(予測できないことを想定する)の原則
2000年9月、当時筆者は豪州の某金融機関とともに、世界でも先駆けとなるCRMのプロジェクトを担当するためにオーストラリアに赴任していた。メルボルンの高層ビルにあるオフィスとホテルを行き来するだけの生活で、ホテルについてテレビをつけ、CNNを流すのが日課になっていた。ある日そこに飛び込んできたのは、日本の緊急ニュースだった。豪雨で決壊した河川の映像で、なんと見慣れた筆者の故郷が水没していた。
両親の安否が気がかりになって、ようやくつながったのは父の携帯電話だった。
「ああ、お前か。隊員から聞いたが、母さんは冠水した2階から救出されて無事らしい。それよりロジスティクスの装備品調達ミスで現場が混乱し、水上の救援活動がほぼ機能停止している。西部方面対策指揮官になって自衛隊と連携して家に戻る時間はないし、忙しいから切るぞ」と電話は一方的に切られてしまった。
地元の消防署長をしながら、ボーイスカウト師団の団長も務めていた父*1は、筆者に幼い頃から、「Be Prepared!(備えよ常に!)」*2と繰り返し言い聞かせていた。それがゆえに、装備品の想定が甘く、人名救助活動で足(ボート)が不足し、ロジスティクス戦術の出鼻を挫かれるという状況を、指揮官として被災地で目の当たりにした父の焦りは、電話の口調からも聴き取れた。
*1 天皇陛下より内閣府の叙勲旭日小綬章を授与されたこともある父は、分野が違えど、世界の職業人(もう退任したが)の中で、筆者が尊敬する人物の一人で、アナリティクスの素地と人のために尽くすという奉仕の精神は彼から学んだ。
*2 “眠らない狼”と敵軍から敬意を持って恐れられたベーデン・パウエル卿の言葉。
別の機会に、「基本的な装備品の所要量展開と予測ができておらず、初動が取れなかった。可能性を捨てきれないなら、次回からは備えておくべきと思う」と悔しそうに猛省する父に、当時の筆者は生意気にも「可能性を捨てきれないなんて、数%の確率に全量備えるのは全く税金の無駄遣いだよ」と反発した。
経済効率を考えればそれで正しいのかもしれないが、その考えは根本的に間違っていた。公共政策とビジネス戦略の違いを実践レベルでは駆け出しだった筆者は、父の言葉の重みをまだ理解できていなかったのだ。
「ビジネスとは違うよ。二つ救うべき命がそこにあるなら、二つとも救うのが公共政策に携わる者の使命だ。選択と集中とかいう考えはあるが、だからといって見過ごすわけにはいかない。今回内陸で水害が及ぶ予想はほとんどないとされていたが起こってしまった。発生の可能性が捨てきれない以上、備えるのがわれわれの使命だ」と彼は力説した。