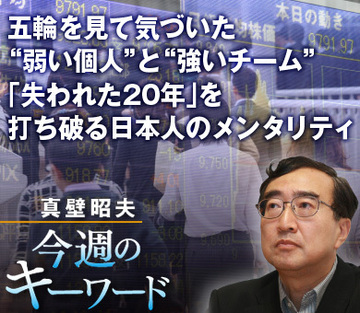スポーツ界をビジネスの視点から見る「スポーツと経営学」。第6回は、先日ロンドン大会の幕を閉じたオリンピックを題材に、巨大な組織や活動のあるべき姿や理念と、時代変化に合わせたその変更の必要性について考える。
無事終了したロンドンオリンピック
時差の関係で多くの日本人を寝不足に追いやったロンドン夏季オリンピックが先日終了した。日本選手団は、金メダルの数こそ前回の北京オリンピックより大幅に減らしたものの、金銀銅合わせたメダル数は38個と過去最高を記録した。男子柔道の不振(史上初の金メダルゼロ)や、宿敵韓国に敗れ44年ぶりのメダル獲得を逃した男子サッカーなど、やや残念に感じる結果もあったが、サッカーは王者スペインに勝っただけでも十分に凄いわけで、概ね多くの日本人は、日本選手団の健闘を評価しているのではないだろうか。
日本人以外でも、ウサイン・ボルトの100メートル走、200メートル走、400メートルリレーでの圧倒的実力を見せつけた金メダル、最後まで接戦を演じたアメリカドリームチーム対スペインの男子バスケットボール決勝戦、全英ウインブルドンの再現となった男子テニスの決勝戦など、見どころは多かった。筆者個人としては、撮影・再生技術の進化のおかげで、高解像度のスローモーションで演技を再確認することができた男女体操が印象的であった。
開催国のイギリスについていえば、懸念されていたテロがなかったというのが、まずは関係者としてはほっとしたことだろう。過去最高レベルの厳戒態勢を敷いたイギリス政府の面目は保てた格好である。一方で、空港が大混雑し、期待された観光客による経済効果も思ったほどではなかったというのは、悔いの残るところかもしれない。大会直前にはシティ(ロンドンにある世界的金融街)でLIBOR不正操作疑惑が持ち上がるという間の悪い事件も起こった。
開会式では、日本選手団が誘導ミスで退出を促されたり、インド選手団の行進に関係者ではない人間が紛れ込んで問題となるという珍事も発生した。しかし、世界的有名アーティストが勢ぞろいした閉会式などはやはり圧巻で、かつての世界の覇者イギリスの国力はまずまず誇示できたのではないだろうか。
さて、このようにオリンピックは単なるスポーツの大会ではなく、世界中の人々が注目する巨大イベントであり、開催国にとっては国のメンツをかけたデモンストレーションの場にもなっている。企業にとっての絶好のプロモーションの場としての位置づけも大きく増している。一方で、そうしたナショナリズムの発露や、商業化の拡大に対する批判も根強い。かつてのような「アマチュアの祭典に戻すべき」という声も小さくはない。足掛け3世紀目を迎えた近代オリンピックはこの先どのような姿となるべきなのだろうか?
そのことを議論する前に、まずは近代オリンピックの歴史を振り返るとともに、その活動の基本理念、ルールとなっているオリンピック憲章について見ておこう。
オリンピックの歴史とアマチュアリズム
近代オリンピックは、よく知られているように、フランスのピエール・ド・クーベルタン男爵が、古代ギリシャのオリンピアの祭典にインスピレーションを得て開催を提唱したものであり、1896年にギリシャのアテネで第1回大会が開催された。第1回大会は参加者はすべて男性(女性の参加は第2回大会より)の245名であり、開催期間は1週間、参加国は14ヵ国にすぎなかった。
途中、2度の大戦による中止や、モスクワ大会(1980年)、ロサンゼルス大会(1984年)の大量ボイコットなどの紆余曲折はあったものの、オリンピックの規模は基本的に拡大基調を描き、今年のロンドンオリンピックでは204の国・地域が参加(ちなみに2012年1月時点で日本が承認している国の数は日本を含め195ヵ国)、出場者は1万931人に達している。