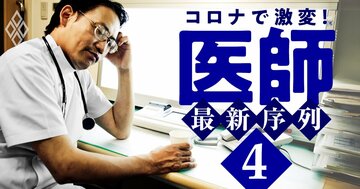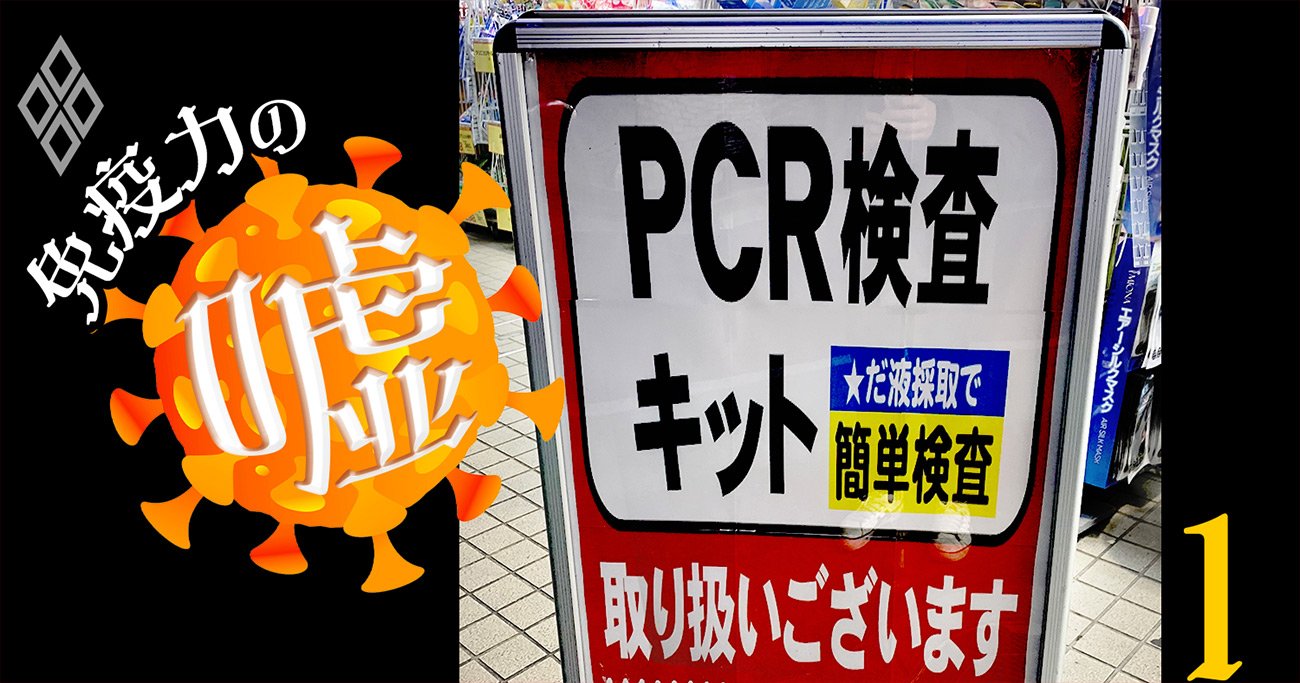 Photo by Seiko Nomura
Photo by Seiko Nomura
止まらぬコロナ感染拡大に2度目の緊急事態宣言を余儀なくされた日本。有症状者や濃厚接触者(感染対策なしに、検査陽性者と接触した者)に限って検査を行ってきた政府の戦略に、再び批判の目が向けられている。特集『免疫力の嘘』(全13回)の#1では、第1波からくすぶってきた「国民全員PCR検査」で感染拡大を食い止めることはできるのかを検証する。(ダイヤモンド編集部 野村聖子)
無症状者が多く感染者の可視化が困難
全員検査で隔離すれば「ゼロコロナ」にできる?
新型コロナウイルス第3波を迎え、昨年の第1波以来、「PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)論争」が再び勃発している。「国民全員に検査」VS「有症状、濃厚接触者など必要な人を対象とすべき」といった構図である。
日本がコロナ対策としてクラスター(感染者集団)追跡に検査のリソースを絞る方針を採ったこと、そして第1波では、症状があったり濃厚接触者であったりしても、大都市圏を中心に検査を受けるまでに数日かかってしまう事例が続出したことで不安が広がり、それがメディアやSNSで盛んに取り上げられるようになったからだ。
確かに、国民全員にPCR検査をして陽性になった人を他人に感染させなくなるまで隔離すれば、他の人はこれまでと同じ生活を送れるし、隔離施設の中でコロナウイルスも撲滅できて一石二鳥のように思える。
しかも、感染すると症状が現れる確率の高いインフルエンザと異なり、コロナは無症状の感染者が多く、コミュニティーの中で感染者を可視化しにくい厄介な性質を持っている。だから無症状者も含め、広く検査をしようというのは単純明快で分かりやすいロジックだ。
「簡単に受けられない」となれば「何としても受けたい」と思うのが人情。検査を受けたいというニーズともマッチして、世論も一時期は「国民全員PCR検査」に大きく傾いた。とはいえ、その後は行政の検査のキャパシティーも充足し始め、PCR論争は下火となっていった。
そこへ、第3波。各地で連日過去最高の新規感染者数を更新する事態となり、再び検査のリソースが逼迫している。ここで「全員にPCR検査をすれば感染拡大を防げた」という論調が息を吹き返してきた。しかし東京大学公共政策大学院の鎌江伊三夫特任教授は「国民全員PCR論は、大規模検査の“わな”を見落としている」と指摘する。そのわなとは何だろうか。