 スマホに依存すると、集中力が低下し、孤独感が強まり、心の不調に陥る危険性があるのは明らかだ(写真はイメージです) Photo:PIXTA
スマホに依存すると、集中力が低下し、孤独感が強まり、心の不調に陥る危険性があるのは明らかだ(写真はイメージです) Photo:PIXTA
レビュー
何か調べごとをしようとしてスマホを一度手に取って、ついでにメールチェックをし、SNSのタイムラインやトレンドワードを確認していたら、当初の目的とは全然関係のないことに没頭してしまっていた――そんな経験をしたことがある人は多いのではないだろうか。
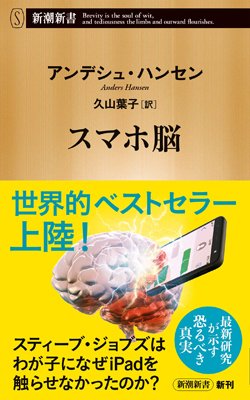 『スマホ脳』 アンデシュ・ハンセン著 久山葉子訳 新潮社刊 1078円(税込)
『スマホ脳』 アンデシュ・ハンセン著 久山葉子訳 新潮社刊 1078円(税込)
人類は歴史上、危険な動物や他人の襲撃、食料不足といった脅威に怯え、身を守ることを最優先させて生き延びてきた。そのため脳は、カロリーをできるだけ欲すようになった。また、危険をいち早く察知するため、一つのことよりも複数の対象に関心を分散させるように進化してきた。だがそのような脳の機能が、まさに現代社会で不具合を生じさせている。それを加速させているのがスマホだ。実際にiPhoneやiPadを世に出したスティーブ・ジョブズは、スマホの依存性や悪影響を認識し、子供の利用時間に制限を課していたという。
スマホに依存すると、集中力が低下し、孤独感が強まり、心の不調に陥る危険性があるのは明らかだ。この問題への対策として本書『スマホ脳』で提案されている方法は、一見するとシンプルである。だが生物進化の観点から脳の機能について解説しており、たしかな説得力を感じさせる。
本書を読めば、スマホに依存する生活を送っている人でも、集中力を高め、心の不調を予防できるようになるだろう。(大賀祐樹)







