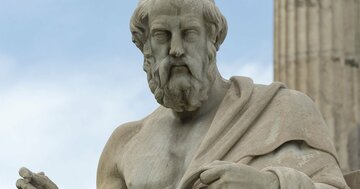熱狂を醒めた目で見ていた妻
ハーバーの熱狂を醒めた目で見ている人物がいた。彼の妻クララである。自身も化学者であった彼女は、人道的な見地から化学戦から手を引くように夫をいさめた。
しかし、彼の答えは、こうだった。「科学者は平和時には世界に属するが、戦争時には祖国に所属する。ドイツこそは平和と秩序を世界にもたらし、文化を保持し、科学を発展させる国だと私は信じる」。彼女は、ハーバーが東部戦線に塩素ボンベの視察についた夜、一人息子を残してみずからの命を絶ったのである。
ドイツ軍はイープルで第二次、第三次と攻撃を続けた。しかし、塩素に対して防毒マスクなどで対策が講じられるようになり、死傷者の数は減っていった。
それでもドイツ軍司令部は、ガス攻撃の有用性を認識し、ハーバーは新設された陸軍省化学局長の地位につき、プロイセン王国大佐に任ぜられた。ユダヤ人であるハーバーにとっては異例の出世だ。
ドイツは世界最強の化学工業の力を持っていた。ハーバーは新しい毒ガスの実験に転じる。それは毒性が塩素の一〇倍という窒息性の「ホスゲン」だった。フランスもホスゲンを準備していたが、あまりにも猛毒なので躊躇しているうちにドイツが使い始めたといわれる。ハーバーは新ガス開発だけではなく防毒法も強化するために化学者たちを集め、新しい防毒マスクが開発された。
さらには、フランスのホスゲン攻撃に対する報復として、さらに重く立ち込めるジホスゲンを投入。ついには、無色で、接触するだけで皮膚がやけどし、ひどい肺気腫、肝臓障害を起こす究極の毒ガスであるイペリット(マスタード・ガス)へと進んでいったのである。
戦争は、狂気をむき出しにしてひたすら殺し合う、凄惨なものになっていった。一九一七年にはアメリカがドイツに宣戦布告。巨大な生産力を持ったアメリカの参戦によって、戦況はフランス・イギリスなどの連合軍に有利になっていった。
アメリカもまたイペリットなどを生産しており、大戦直後には一日に二五万発とドイツをはるかに上回る大量生産能力を持っていたほどだ。さらには、びらん性・肺傷性の猛毒ルイサイトを開発。アメリカは世界有数の毒ガス開発、保有国となっていったのだ。
ハーバーは一九一八年アンモニア合成法(ハーバー・ボッシュ法)でノーベル化学賞を受けた。しかし、アンモニアから肥料をつくることで世界の農業に決定的に貢献したとしても、何千何万もの人間を毒ガスにさらしたという事実は消えない。ハーバーは人々から軽蔑の眼差しを向けられた。
とくに連合国側の科学者からはハーバーがノーベル化学賞を受けたことに不満の声が上がった。
第一次世界大戦後、ドイツは、ベルサイユ条約によって、戦前の面積・人口の一〇パーセントを失い、化学兵器の製造・使用の禁止をふくむ軍備制限を受け、巨額の賠償金(総額は一九二一年に一三二〇億マルクと正式決定)が課されるなどした。賠償金の支払いに役立てようと愛国者ハーバーは海水から金を抽出する計画を立てる。しかし、実際に挑戦してみると、海水中の金は想定していた濃度よりずっと低く、採算がとれないことがわかった。
その後、ドイツをアドルフ・ヒトラーが支配するようになると、ユダヤ人のハーバーに冷たい風が吹き始めた。カイザー・ウィルヘルム研究所の物理化学研究所長・電気化学研究所長だったが、辞めざるを得なかった。
ハーバー・ボッシュ法によって、アンモニアの合成・工業化へ導いたカール・ボッシュ(一八七四~一九四〇)は、ヒトラーとの面談で「ユダヤ系の科学者を追放することは、ドイツから物理と化学を追放することである」と警告するが、返答は「それならば、これから百年、ドイツは物理も化学もなしにやっていこうではないか」というものだった。
ハーバーはイギリスのケンブリッジ大学に迎えられたが、その冬は耐えがたい寒さだった。失意のなか、心身の疲労から健康を害し、スイスに保養旅行に出かけたハーバーは、祖国が目と鼻の先にあるバーゼルで亡くなった。
東京大学非常勤講師
元法政大学生命科学部環境応用化学科教授
『理科の探検(RikaTan)』編集長。専門は理科教育、科学コミュニケーション。一九四九年生まれ。千葉大学教育学部理科専攻(物理化学研究室)を卒業後、東京学芸大学大学院教育学研究科理科教育専攻(物理化学講座)を修了。中学校理科教科書(新しい科学)編集委員・執筆者。大学で教鞭を執りつつ、精力的に理科教室や講演会の講師を務める。おもな著書に、『面白くて眠れなくなる化学』(PHP)、『よくわかる元素図鑑』(田中陵二氏との共著、PHP)、『新しい高校化学の教科書』(講談社ブルーバックス)などがある。