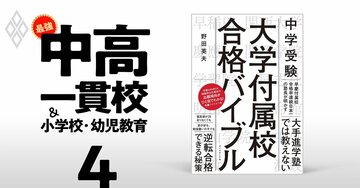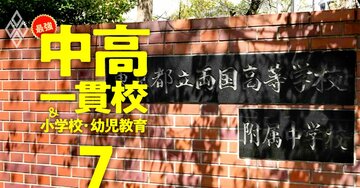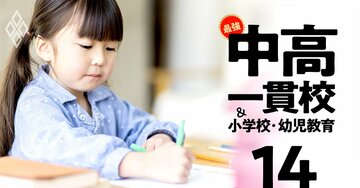21年入試の受験者増には、コロナ禍によって急きょ中学受験に走った駆け込み受験も少なからず影響したとみられている。ただし、本来であれば、中学受験の準備は小4ぐらいまでに塾通いなど対策を始めておく必要がある。そのため、小学校高学年以上に中~低学年の子どもがいる家庭の方が、公立学校への不安によって私立中学受験に、よりかじを切っているだろうことが予想できるのだ。
実際、東西の中学受験塾の関係者は、「(22年以降の受験を望む)親からの申し込みや問い合わせの数が前年を大きく上回っている」と口をそろえる。広野本部長は、そのすさまじさの一端を明かす。
「より低学年からの申し込みが増えている。昨年11月から、この4月に小学校へ入学した新1年生クラスの募集を開始しているが、すでに3分の2の校舎が定員に達し、募集を締め切った」
そもそも、近年、中学受験を目指す家庭は増加傾向にあった。その主な理由は、20年度の「大学入試改革」と16年度から始まった「私立大学入学定員厳格化」にある。受験レースの“ゴール”である大学受験の先行き不透明感に、コロナ禍以前から小学生の子どもを持つ親たちの不安が増大していた。コロナ禍は、その流れをさらに加速させたという構図なのだ。
そして、コロナ禍が中学受験にもたらした影響は、全体の受験熱にとどまらず、個々の学校の受験者数にも影響を与えている。
21年入試の受験者に広がった
「安全志向」と「越境回避」
森上教育研究所の森上展安代表は、「首都圏における21年入試のキーワードの一つが『安全志向』。難関校を狙わず、中堅校を選んで確実に合格するという動きが顕著に見られた。その結果、難関校の多くが受験者数を減らした一方、例えば、親世代のブランド校で知名度の高い非ミッション系女子伝統校の山脇学園や昭和女子大学附属昭和、実践女子学園、跡見学園などが躍進した。また、付属校でも早慶が沈静化する中、日本大学豊山などの中堅付属校が人気を集めた」と指摘する。
この受験者の「安全志向」に加えて、コロナ禍の影響とみられるのが越境受験の減少であろう。首都圏における最たる例は「千葉最難関の渋谷教育学園幕張(渋幕)。主に都内からの受験者が減った結果、受験者数は、男子が19%減、女子が15%減となった」(森上代表)。