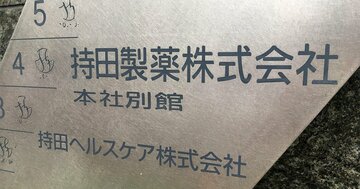Photo:AFLO
Photo:AFLO
「名は体を表す」ということわざは、こと、国内製薬業界においては親和性が薄そうだ。「大日本」と名乗った会社は、住友グループに併呑されて来春にはその名前も消滅する。「明日を照らす」とイキった会社は、発足から15年を経ても業界トップの座を奪えず佇んでいる(ちなみに2006年の売上高が107億ドルだった米アマゾンは、20年には売上高が3860億ドルへと成長した)。
そして「世界の」という形容詞を特異的に好む業界首位の会社は、M&Aを重ねてグローバル市場に橋頭堡を築くことには成功した。しかしそれも束の間、期待していた新薬が相次いで開発中止に追い込まれた結果、地歩の維持に黄色信号が灯る状況に追い込まれている。俄に、自分たちの企業活動はSDGs(持続可能な開発目標)の考え方と合致するものだなどと“ポエム”を語り始めたあたりに、自称「グローバルな研究開発型バイオ医薬品のリーディングカンパニー」が直面するのっぴきならない閉塞感が現れている。
ただし言うまでもなく、どの世界や分野にも例外は存在する。例えば、「アース(地球)」と大きく掲げた製薬企業は、企業風土改革の結実と口腔衛生や虫ケアといった家庭用品事業の快走によって、16期連続の増収を果たしている。人口オーナスが加速する国内市場の変化を考えると、強靭な成長力と言えるだろう。
自嘲気味の時代もあった
さらに例示を続けるならば、日本新薬も、「アース」とまでは行かないものの、負けず劣らずの存在と言えるかもしれない。いまから110年前の1911(明治44)年、「日本人ののむ薬は日本人の手でつくりたい」との思いを抱いた後に初代社長となる市野瀬潜氏が京都市内に立ち上げた京都新薬堂を前身とし、19(大正8)年に京都というエリアにとらわれず、「将来は大きく羽ばたきたい」との願いを込めて現在の社名に改めた。
40(昭和15)年にミブヨモギを原料とする国産初の駆虫薬「サントニン」を発売し、新薬メーカーとしての土台を築いた。さらに戦後は61年、サントニンや前立腺肥大症治療薬「エビプロスタット」など植物由来の生薬技術を応用して食品事業にも進出した。
しかし企業業績、なかんずく売上増の推進力となる新薬の上市頻度は、お世辞にも順調とは言えなかった。「新薬のない日本新薬の○○です」と、MRが自嘲しながら医局を訪問する時代が昭和の後半から平成半ばにかけて長く続いた。