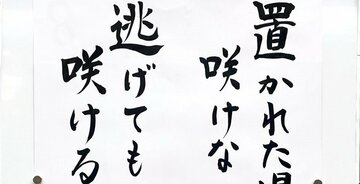バカの看板が与えてくれたもの
バカはね、とっても得なんです。何より、落語家として表現の幅が広がりました。
「笑点」に限って言っても、手をあげて指されてから「なんだっけ?」と問題を忘れちゃっても、木久蔵だからしょうがないって許されるし、そこでまた笑いがおきる。
流れと関係なく「いやん、ばかーん」なんて歌い出したり、いきなり花魁(おいらん)になって、「ここでおーたもなにかの縁~。遊んでいってクンナマシ」とやったりもできる。
バカという看板は、ぼくに自由を与えてくれたんです。それだけじゃなくて、ぼくにたくさんの入金も与えてくれました。
若い頃にいちばんありがたかったのは、地方巡業にたくさん呼んでもらえたことですね。どこかの地方で落語会をやるときに、目玉になるのは談志さんや先代の五代目三遊亭圓楽さんや三代目古今亭志ん朝さんといった古典落語のオーソリティの人たちです。そこでトリの前に舞台に出る「ヒザ(膝替わり)」として、よく呼ばれました。「木久蔵のネタだったら邪魔にならないから」って。
「ヒザ」は、トリの人がやりやすいように会場を盛り上げるのが役目です。間違っても、トリがやりそうな大ネタをやっちゃいけません。ぼくが出ると歌ったりモノマネやったりしてにぎやかしになるし、ネタがかぶる心配もない。「邪魔にならない」っていうのは、そういう意味です。
落語の世界を引っ張っている人たちですから、仕事はいくらでもある。そういう人が「木久ちゃんがいいよ」って言えば、それで決まりです。
ただ、ぼくの単価は安かったですけどね。安い分、たくさん使ってもらって回数を重ねたら、それなりの収入になります。そうこうしているうちに、独演会で営業のお仕事に呼ばれるようになったり、講演会もやるようになりました。
落語家として自分の表現をつかむことができたのも、たくさんの入金がもたらされたのも、元をただせば、すべて笑いを呼ぶ与太郎になったおかげなんです。
「笑点」が落語という芸を救った
談志さんは「笑点」がスタートした1966(昭和41)年5月から、選挙に出るからと番組を降りるまで、約3年半にわたって司会を務めました。番組が始まった頃、落語は何となく敷居が高い芸になりかけていて、談志さんはそういう状況をどうにかしたいという思いがあったんです。ご自分でも「笑点」のことを「俺の最高傑作」とおっしゃってましたね。
かつては「あんなのは噺家のやることじゃない」「落語のイメージが悪くなる」なんて言う人もいましたけど、あの番組がなかったら、落語という芸自体、はたしてどうなっていたことか。
もちろん、高座でしっかりした名人芸を見せて、その魅力を伝えていくことも大事です。でも、入りやすい入り口がなかったら、誰も興味を持ってくれません。
途中、談志さんが目指すブラックユーモア路線に大喜利メンバーが反発して、歌丸さんや圓楽さんたち初期メンバーが一斉に番組を降りるという騒動もありました。メンバーがガラッと入れ替わったんですが、その頃の視聴率は今ひとつだったようです。
談志さんをひと言で言うと「一日中起きてた人」かな。天才でもあったけど、努力家でもあった。寝るときも天井に謎かけをいっぱい貼って、それで練習する。頭の中はいつも落語のことでいっぱい。中学生の頃から詰襟で寄席に来て、一度聞いた噺は覚えちゃって帰りには口ずさんでいた。そんな落語小僧がそのまま大人になったみたいな人です。