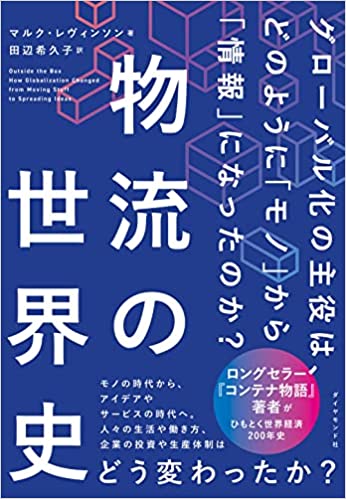ロングセラー書籍『コンテナ物語--世界を変えたのは「箱」の発明だった』(日経BP社)の著者マルク・レヴィンソンの最新刊『物流の世界史--グローバル化の主役は、どのように「モノ」から「情報」になったか?』より、その一部をご紹介する。
第一次大戦による打撃
1918年11月、休戦によって戦争は終結した。そして休戦条約の調印と同じ頃、世界中でスペイン風邪が流行して1億人ともいわれる死者が出た。さらにヨーロッパ各地で旧秩序の打倒を目指す革命の嵐が巻き起こり、大陸の国々は重い債務を負い、これから何年にもわたる復興の歳月へと向かおうとしていた。戦勝国が真っ先に目指したのは、新たな植民地の獲得、金準備の再構築、そしてドイツ、オーストリア=ハンガリー、オスマンの各帝国崩壊後の廃墟から領土を奪いとることだった。貿易・投資の回復は、優先順位のはるか後ろに回された。歴史学者のマイケル・B・ミラーによれば、第一次大戦はヨーロッパを弱体化させ、代わって日本と米国を世界経済の担い手とすることでグローバル化を促進したという。しかしその効果が現れるのは、ずっと先のことだった。
 世界中でスペイン風邪が流行(Photo: Adobe Stock)
世界中でスペイン風邪が流行(Photo: Adobe Stock)
ある意味では、むしろグローバル化を抑制することが戦後外交の目標だった。パリ近郊ヴェルサイユでの和平交渉は帝国、少なくとも一部の帝国の終わりの始まりと見られていた。米国のウッドロウ・ウィルソン大統領が一番に目指したのは「民族自決」、つまり同一言語・同一民族を国家主権の基礎に据えるべきだというあやふやな概念の実現にあった。イタリアのシドニー・ソンニーノ外相は、「この戦争は間違いなく民族意識を過剰に刺激する効果を持った」と指摘した。「米国がそうした原則を後押ししたことが、この傾向に拍車をかけたと思われる」。こうしてナショナリスティックな考え方が経済政策を支配するようになった。貿易障壁は再び引き上げられ、外国資本に疑惑の目が向けられ、商船を国が管理することが戦略上の緊急課題とされた。ロシア帝国を倒したボリシェヴィキ(レーニン率いる左派勢力)もまた、新生ソ連邦に権力を集中させようと同様の政策を採用した。ただしその動機は異なり、外国資本を遠ざけることが目的だったが。
グローバル化を測る尺度の一つは、その国の経済がどこまで世界貿易に「開かれているか」である。これを数字で算出しようとすると、当然、意見の食い違いが出てくる。例えばプラハからウィーンへの輸送は、1918年までは同じ帝国内の国内輸送だが、帝国崩壊後は国際輸送となる。これをどう反映させればいいのだろう。だがこうした技術的問題を脇におけば、根底にあるトレンドは一目瞭然だ。戦争直前の1913年には、世界のGNPの約12%を輸出が占めていた。戦後は短期間、回復へ向かったものの、1920年と1921年の戦後不況で国際貿易は大きく落ち込んだ。1924年には経済成長も貿易も回復に転じたが、1920年代後半は輸出が世界のGNPの10%程度に過ぎず、戦前の水準を大きく下回った。世界経済は、それまでより「開かれて」いない状態になったのである。
こうした結果になることは必然だった。1920年代には、どの国も国内の製造業者や農民を戦禍から立ち直らせるため関税を引き上げた。1世紀にわたって自由貿易の旗振り役を務めてきた英国では、1921年に議会で産業保護法が可決され、課税によって外国の光学機器・試験機器・有機化合物などの製品が30%以上値上がりした。この法律は、製造コスト以下で販売されていると判断された輸入品に対して政府が罰則を科すことも認めていた。この条項は26以上の国との間で条約違反に相当するものだったが、国内の産業別組合には歓迎された。米国も1921年、1922年と二度にわたって関税を引き上げた。輸入品の3分の2は関税を免除されたが、残りの輸入品は荷揚げ時点で価格が100ドルから平均139ドルに跳ね上がった。スペインの平均輸入関税率は1913年の33%から1925年には44%に、英領インドでは4%から14%に引き上げられた。ある国が新たな輸入規制をかけると、他の国も同様の規制で報復に出ることが多かった。1925年から1929年にかけてヨーロッパ26カ国のほか、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、さらに中南米の多くの国も関税を引き上げた。
運賃の低下傾向が戦前並みにまで回復していたら、関税引き上げの影響も相殺されていたかもしれない。19世紀末以来、造船は他の産業よりずっと速いペースで生産性を向上させていた。その主たる要因は、鉄の代わりに鋼を使うことで輸送能力の高い大型船の建造が可能になったことにある。こうして海上貿易のコストは低下し、ある船会社では1885年から1914年にかけてトン当たり輸送費が平均60%低下したと試算している。だが輸送費の値下がりは1920年代になるとストップした。原因については歴史学者のあいだでも諸説あるが、いずれにせよ1920年代の平均輸送費(インフレ調整後)が、1913年のそれとほとんど変わらなかったことは事実である。もはや輸送費の値下がりが貿易を促進することもなくなっていた。
国際貿易の停滞に加え、対外投資も減少した。第一次大戦前、外国人が所有する資産は国債から工場に至るまで、世界の産出量の約18%に達していた。だがこの数字は1920年代を通じて減少し続け、1930年には8%まで低下した。もちろん人目を引くような外国からの投資もたくさんあった。フォード・モーターは戦前から米国製部品を英国とフランスで組み立てるなど、長距離サプライチェーンの先駆けとして、1920年代末にはヨーロッパの13カ所に工場を所有していた。だがフォードの活動が広域に及んだことそのものが、戦間期のグローバル化に特有の限界を示している。つまり関税が高いため1~2カ所の効率の良い大工場からヨーロッパ全域に製品を輸出するのは現実的でなく、デンマークのような小国にまで工場をつくらざるを得なかったのだ。IBMなどはフランスとドイツの工場で、米国からの輸入部品を使って作表機を生産していたが、多くの外国企業は部品や原材料を輸入するより、現地工場にライセンス生産させて関税を回避する道を選んだ。例えば米国の自動車メーカーは英国の関税を免れるためカナダ経由で輸出していたが、カナダでは一定の割合で国産部品を使わざるを得ず、米国製の部品を使うと高い関税がかけられた。全体として、金融と製造業は1920年代に国際化が大幅に後退した。関税や通貨切り下げといった貿易障壁への対策が常に必要になるため、投資は国内に振り向けられがちだった。
人の移動も減った。最大の移民受け入れ国である米国は、1905年から1914年の10年間のうち6回、100万以上の移民を受け入れた。だが1924年に厳しい移民規制が導入されると、移民は年平均約30万となり、しかも3分の1近くが遠隔地でなくカナダからの移民だった。当時、ヨーロッパからの移民が多かったもう一つの国アルゼンチンでは、戦前は年間約20万を受け入れていた移民数が、1920年代には平均で半分ほどに減った。またこの時期には中国が移民の最大の供給源となり、何百万人もが東南アジアに、さらに何百万人もが日本支配の強まる満州へと移り住んだ。
大恐慌から第二次大戦へ
物資・投資・人の自由な移動が早期に回復するとの希望を完全に打ち砕いたのは大恐慌だった。1929年10月29日火曜日、ニューヨーク証券取引所で株が暴落し、取引が混乱して株価を表示するティッカーに数時間の遅れが生じた……大恐慌はこんなふうに始まったと一般には信じられている。だがそれはタブロイド紙上の話に過ぎない。ブラック・チューズデー(暗黒の火曜日)のはるか以前から、世界各地でデフレが進んでいた。最大の原因は経済政策の失敗にある。金が不足しても各国政府が自国通貨を金で固定することにこだわったため、国内金利が上昇し、経済成長が阻害され、銀行は不良債権に悩まされることになった。データが示す通り、1930年になると日本からイタリア、カナダに至る経済大国が、こぞって物価下落の長期化に苦しめられていた。
デフレは経済成長にはマイナス要因となる。物価が下がることがわかっていれば、企業は設備投資を先送りし、消費者はお金を使わなくなる。こうした状況が1930年代初めに世界中で起こり、失業があらゆる国に蔓延した。ほとんどの国でこの時期のデータは断片的とはいえ、公的統計による米国の失業率は経済が比較的安定していた1929年には約3%だったが、1930年には9%に急増している。特に農業の状況はきわめて深刻で、農場労働者の日給は部屋なし食事なしで2・15ドルと、10年前の3分の1まで落ち込んだ。ヨーロッパでも状況は似たり寄ったりで、どの国の政府も財政再建や金準備に汲々となり、失業対策は後回しになった。大恐慌以前のGNPの水準まで回復するのにオランダは8年、カナダは9年、フランスは10年かかった。ニューヨーク株式市場で最もよく知られた指標であるダウ工業株30種平均は、大恐慌以前の水準を回復するのに1954年11月までの25年間、あるいはこの間のインフレ率を調整するなら、もっと長い時間がかかった。
こうした景気後退は、もちろん貿易にはマイナスである。消費者はお金を使いたがらず、1930年には世界の輸出入はなんと8%も下落した。だがこれは序の口だった。1929年4月、米議会は苦境に立つ農業部門の訴えに応じ、新たな関税法の策定に取りかかっていた。最初は農民を助けるためのささいな措置だったが、たちまち悪循環を引き起こして制御不能に陥った。ニューヨークの株式大暴落の8カ月後に施行された「1930年関税法」、通称「スムート・ホーリー関税法」は、関税対象品目を増やし、かつ税率を引き上げるというものだった。関税率の多くは、輸入品の製品価格でなく、輸入品の重量当たりのドル価格に設定されたため、デフレの進行で物価が下がるにつれ、輸入品価格に占める関税の割合は大きくなっていった。スムート・ホーリー法により、1932年までに多くの鉱物・農産物・工業製品の米国への輸出コストは59%増加することになった。
1930年当時、米国は全貿易の約7分の1を占める世界一の貿易国だったから、貿易相手国はこの新たな関税措置に激怒した。それでなくても製造業の需要が落ち込んでいるのに、これでは輸出がストップしてしまう。カナダとヨーロッパ諸国は、対抗措置として米国の輸出品に対する関税を引き上げた。その後、1931年夏にヨーロッパ全域に銀行危機が拡大すると、各国政府は自国通貨の金への紐付けを解除し、低迷する経済に中央銀行が金融政策を行えるようにした。こうして金本位制は崩壊し、為替相場は乱高下するようになった。各国が相次いで為替管理を導入したため、輸入代金の支払いに必要な外貨を確保することは難しくなった。
世界貿易(インフレ調整後)は1929年から1933年に3分の1近く減少し、その後も思うように回復しなかった。同じ時期の工業製品の貿易は42%も減少した。外国からの投資は、各国が国民の海外送金を制限するようになったため、ほぼストップした。国際連盟の統計によれば、1931年9月1日からの16カ月間に23カ国が全面的に関税を引き上げ、50カ国が特定品目の関税を引き上げ、32カ国が輸入割当や輸入許可制度を導入した。国際連盟の報告書は、「1932年半ばまでに、国際貿易メカニズムが国際通貨システムと同様の完全崩壊の危機に立たされていることが明らかになった」と警告している。
経済危機は長期化し、国際貿易と対外投資の崩壊によって事態はさらに悪化。政策にも大きな影響を与えた。失業率の上昇と生活水準の低下を受けて、米政府とカナダ政府は異例の積極策を打ち出し、農業支援や公共事業の拡大、貧困者・高齢者・失業者への支援など、政府の介入を大幅に拡大した。経済回復はもはや民間企業だけの問題ではなくなった。ヨーロッパでは経済危機で民主政治が揺らぎ、ロンドンでもパリでも権威主義的なナショナリズム運動のデモが起き、ドイツ、ハンガリー、ポルトガルなど各地で独裁政権が誕生した。
アフリカやアジアにあるヨーロッパ列強の植民地など、農産物や天然資源などの一次産品を輸出の主力とする地域の状況は特に深刻だった。ヨーロッパや北米の富裕国が高い貿易障壁を設定すれば、一次産品の輸出国は国内製造業を育成できなくなる。もはや農場や鉱山の産品を売るしか生き残る道はないが、それも危うくなった。1929年に銅価格が暴落すると、チリの輸出額(ドル換算)は3年間で88%も急落した。コーヒーと砂糖の輸出がさかんで、製造品の輸出がほぼ皆無のブラジルでは、輸出額が3分の1にまで落ち込んだ。ゴム、羊毛、パーム油、錫などはいずれも1930年代初頭に大幅に値下がりし、輸出と引き換えに購入できる輸入工業製品の量も減った。第二次大戦前の軍備拡大で新たな需要が生まれるまで、多くの一次産品の価格は長期にわたって低迷し、貧困国の生活水準は、ヨーロッパや北米や日本のそれから大きく引き離されることになった。
1930年代後半、世界はいくつかの貿易圏に分裂した。それぞれの貿易圏内で友好国が優遇され、それ以外の国は関税によって排除された。ただし大英帝国は別枠で、カナダ、インド、オーストラリア、南アフリカの輸出品のほとんどは、帝国内で関税なしで取引できた。すでに韓国を併合していた日本は、1930年代に満州(中国東北部)を占領して日本の輸出品の主要市場とする一方、中国の対日本以外の貿易はほぼ途絶した。ドイツでは北米との貿易が消滅したためヨーロッパへと対象を切り替え、その一部の属国化を目指すようになった。イタリアも、リビアを中心とするアフリカの植民地との貿易が増え、それ以外の国との貿易は減少した。対外投資も対外融資もなくなり、国同士の経済的つながりが失われたことが、戦争への道を開いていった。1939年9月1日、ドイツ軍150万がポーランドに侵攻し、世界中のほとんどの地域を荒廃へと向かわせる血みどろの戦争が始まった。