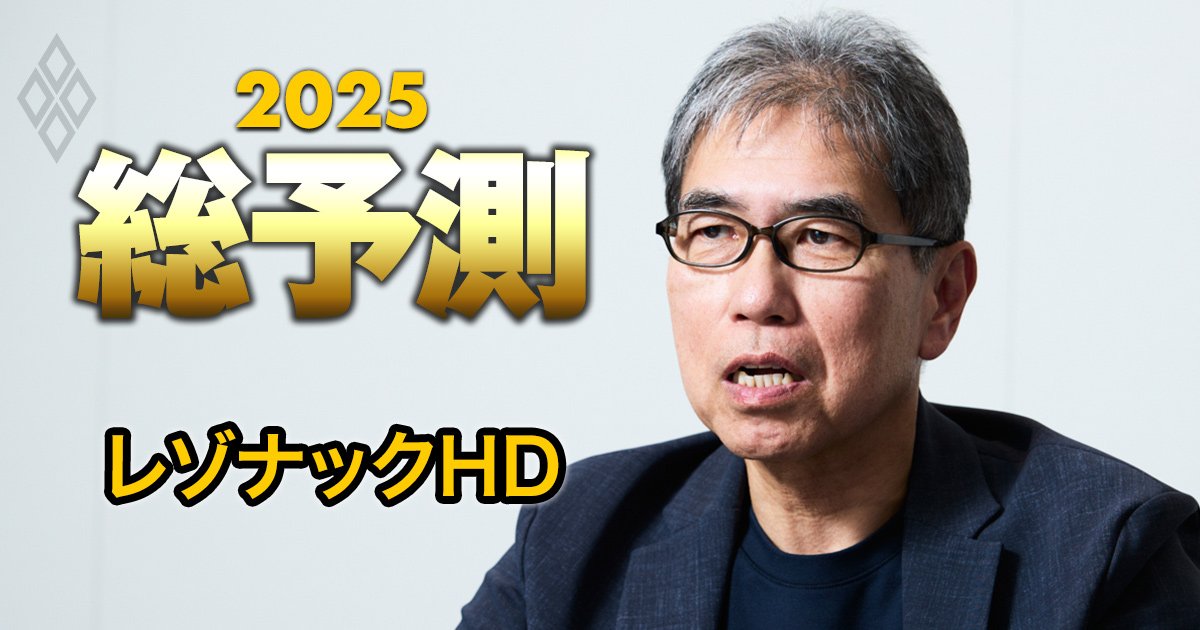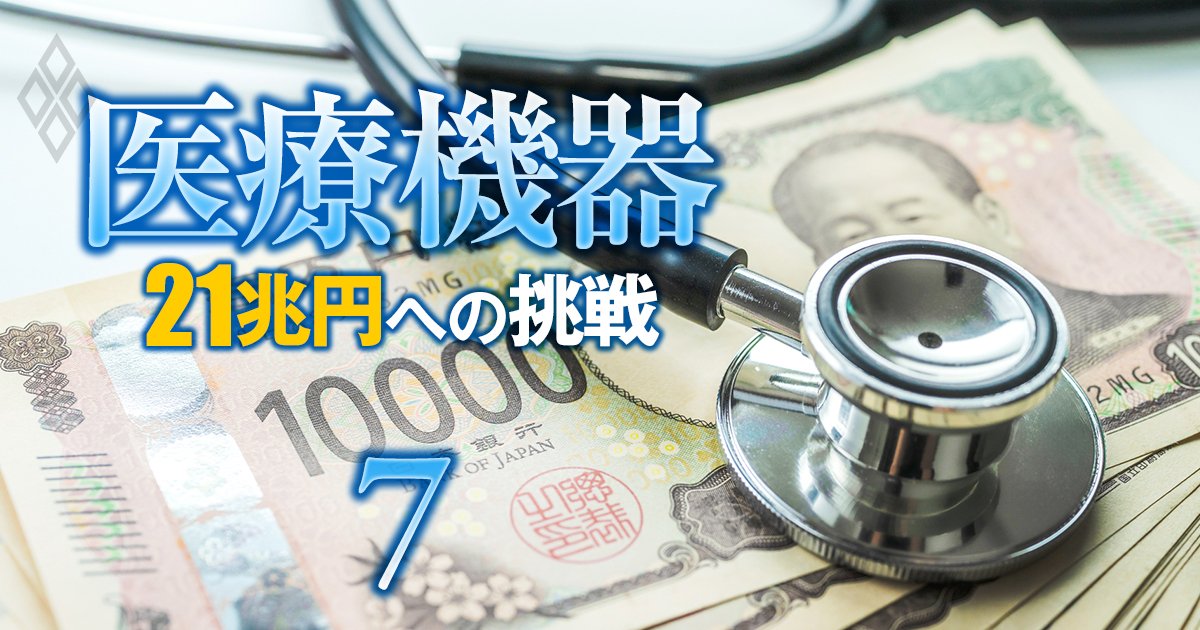なぜ、うつ傾向になると仕事がうまくいかなくなるのだろうか?(写真はイメージです) Photo:PIXTA
なぜ、うつ傾向になると仕事がうまくいかなくなるのだろうか?(写真はイメージです) Photo:PIXTA
気分が沈みがちでうつ傾向の強い人は、仕事でも人間関係でもミスやトラブルを生じがちだと言われる。「うつで仕事がうまくいかない」と嘆き、苦しむ声もよく聞く。なぜ、うつ傾向になると仕事がうまくいかなくなるのだろうか? 実は、うつ傾向と問題解決能力との間には密接な関係があることが分かっているのだ。(心理学博士、MP人間科学研究所代表 榎本博明)
問題解決能力にはエピソード記憶が関係している
人間関係や仕事での問題解決能力に記憶が関係していることは、考えてみれば当然のことなのだが、あまり意識されていないようである。特に過去の具体的な出来事に関する記憶、いわゆる「エピソード記憶」には、問題解決を助ける機能がある。
例えば、こんなケースでは、こうやったらうまくいった。このようなピンチの状況では、こういうふうにしたら打開できた。似たような状況のとき、このようにしたら失敗して痛い目にあった……こうしたエピソード記憶を参考にすることで、私たちは仕事上の問題をうまくクリアしていくことができる。
「あの人に相談したけどムダだった」「あの上司は、このように話を持っていくと、気を良くして力になってくれることが多い」「取引先のあの担当者の場合、この種の話題は地雷になるので、気を付けないといけない」。こういったエピソード記憶を参照することで、人間関係面のトラブルを避けることができるし、良好な関係を築いて仕事に生かすことができる。
心の中に貯蔵されているエピソード記憶には、「こういう状況で、こんなふうにしたら、こんな結果になった」「あの人にこんなふうに話を持って行ったら、こんな反応があった」というような具体的なエピソードがいっぱい詰まっている。
ゆえに、何か問題に直面したときは、過去の似たような状況のエピソードをかき集めて、それらを参考に対応の仕方を検討することになる。あるいは特定の人物を攻略しなければならないときは、その人物に関する過去のエピソードを引き出して、どう対応したらよいかを判断することになる。