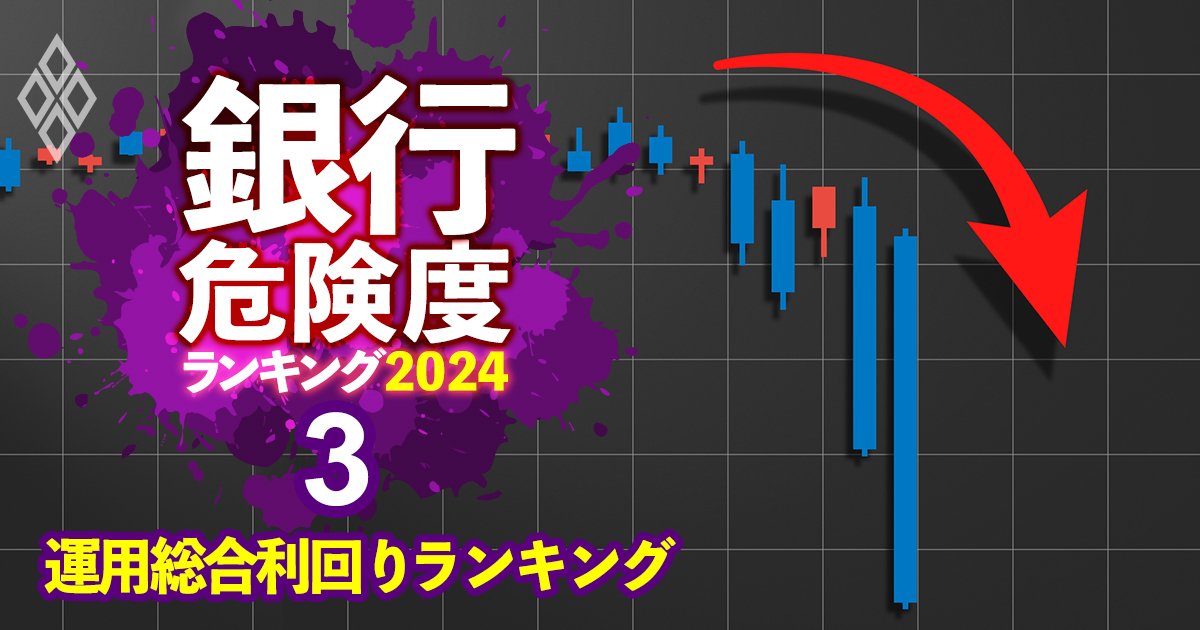虫と戯れる子どもに、親はどう接するべきか
喜んで虫と戯れる子どもに引きつった笑顔で接する親……とは、子どもがいる家庭でよく見られる光景である。親として想定される身の振り方は、3パターンが想定される。
まず、「自分は苦手だから近づけないでね」と説明することである。意外と子どもも理解してくれるので、「子どもがおぞましい虫と戯れている」というモヤモヤは残るものの、当面自分は虫との接近を回避することができる。
もう一つのパターンは、子どもが虫と戯れるのを禁じる、である。これはその虫が毒を持っていたり、著しく不衛生であると思われる場合、やるべきである。
三つ目のパターンは、子どものしたいようにやらせる、である。子どもの好奇心を育んでいくことなどを考えると、これがもっとも好ましいように思う。
この場合、親は我慢するしかないが、子の楽しみや成長を思えば可能な我慢であり、その我慢によって今回の筆者のように、新しい扉が開ける可能性はある。無理して虫を好きになる必要はないが、「子どものために無理をしたら、その結果虫を好きになった・あるいはそれほど苦手ではなくなった」というのであれば、それはその人にとって建設的な一歩であろう。
筆者宅の芋虫はすでに蛹(さなぎ)になって、生き物の神秘を垣間見せてくれている。羽化する瞬間が楽しみでもあり、別れとなるので切なくも思われる(アゲハチョウは虫かごでの飼育に適していない)。
なお、筆者が芋虫飼育の扉を開けたことにどれだけ普遍性があるのか調べてみたところ、ちらほら同胞が見つかった。子どもをきっかけに飼育し始めてみたら意外とハマった、という人たちである。
飼育が難しくなく、かわいらしく、卵から孵化(ふか)させたとしても羽化まで1カ月もかからない(ナミアゲハを夏に飼育した場合)から、飼育の責任を負う期間も限定的である。
飼育に乗り出してみなければその魅力がわからず、普通はてんで飼育する気になれないハードルの高さが芋虫飼育の悩ましいところだが、命と触れ合いたい人にはぜひおすすめしたい。
犬や猫を愛せる人なら、かなりの確率で芋虫も愛せるようになるのではないか、と踏んでいる。犬も猫も飼育して愛しまくった筆者の仮説である。