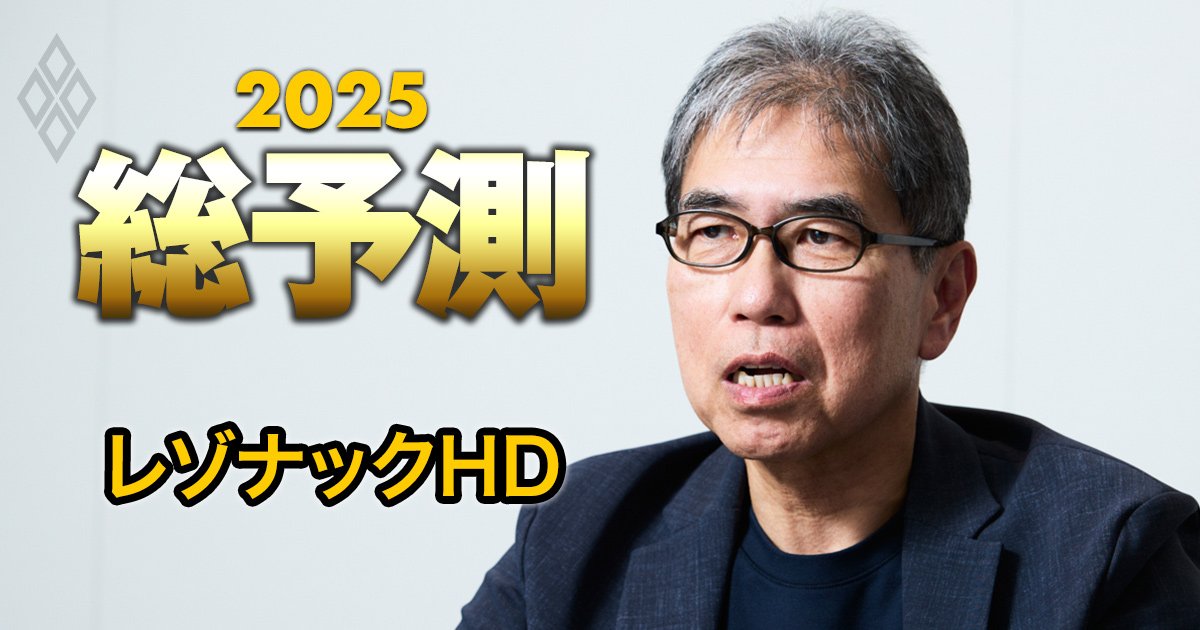写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「宗家 源吉兆庵」の包装紙に描かれた中国の詩
かなり前のことだが、いただいた和菓子の菓子折りを見た途端、目を見張った。包装紙に、盛唐時代の詩人・王之渙の詩「登鸛鵲楼」が刷られていたのだ。中国の小学生も暗唱できる「白日依山盡、黄河入海流。欲窮千里目、更上一層樓」だ。
「太陽が山の稜線に寄り添うかのように落ちていき、黄河の水が海に入り、海流と溶け込んでいく。すでにはるかな遠方を見ている目を極めたいなら、さらに高いところに上ろう」という意味だ。
その和菓子屋は、岡山県からスタートした創作和菓子の「宗家 源吉兆庵」だ。Twitter上では、なぜ包装紙に漢詩が起用されたのかという疑問を持つ人もいるが、私から見れば、おそらく以下の理由から採用されたのではないかと思う。
雄大な景色を眼下に俯瞰しながら、より遠いところを眺めたいなら、さらに高いところに上ろうよと勧めるこの詩は、すでに国内店舗が約150、海外店舗が約30の規模を持つ源吉兆庵の高遠な志を代弁しているからだ。