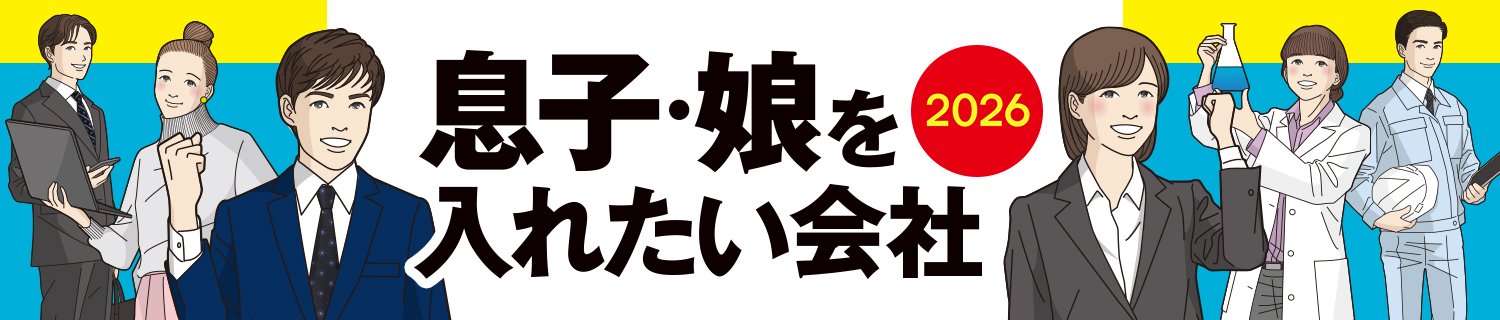将来性の手がかりは
過去の歴史の中にある
――歴史が将来性を予測する手段、というのは興味深いですね。
先が見えない時代に求められるのは「未来を想像する力」です。そしてその手がかりが、実は過去の歴史の中にある。歴史は繰り返さないけれど韻を踏むんですね。
私はよく「歴史を学ぶことは、前が見えない状態でバックミラーを見ながら自動車を運転するようなもの」という話をするんです。
バックミラーに崖が映っていれば「この崖はまだ続くかもしれない」と想像がつきますよね。もし落石が見えれば「この先にもまだ落ちているかもしれない」と警戒できるでしょう。たどってきた道を見れば、未来を想像、予測して備えることもできるわけです。
歴史を学ぶとは、そうした力を鍛えることでもあるんですね。
――先の見えない未来と向き合うには過去の歴史や今の社会の仕組みを知ることも不可欠なのですね。
そもそも人間というのは「よく分からないこと」に直面すると不安を覚えるものなんです。
私がそれを痛感したのは11年の東日本大震災に伴う福島第一原発事故のときです。みんなテレビのニュースや報道番組をかじりつくように見ていましたよね。私もそうでした。でもそうした番組で専門家に、いきなりベクレルだシーベルトだと専門用語で話されても何のことかさっぱり分からないわけです。数値ばかり並べられても、それで今は安全なのか危険なのか、どうなれば危険でどうなれば安全なのか、分からない。
よく分からないから想像できないし、想像できないから先々のことがすごく不安になるんです。
そこで同じ時期に出演したテレビ朝日の特番で、あえて「放射能と放射線はどう違う?」「ベクレルやシーベルトとは?」という基礎の基礎から解説したんです。すると視聴者から「疑問だったことが分かって少し安心できた」という声が数多く届き、視聴率も非常に高かった。世の中のみんなが「よく分からないから怖い」という不安をずっと抱えていたんですね。
このように知らない、よく分からない、不確実な知識しかないという状態は不安を増大させます。
それは逆に言えば、正しい知識を持つことが、先の見えない未来への不安を軽減し、払拭する力になるということでもあるんです。