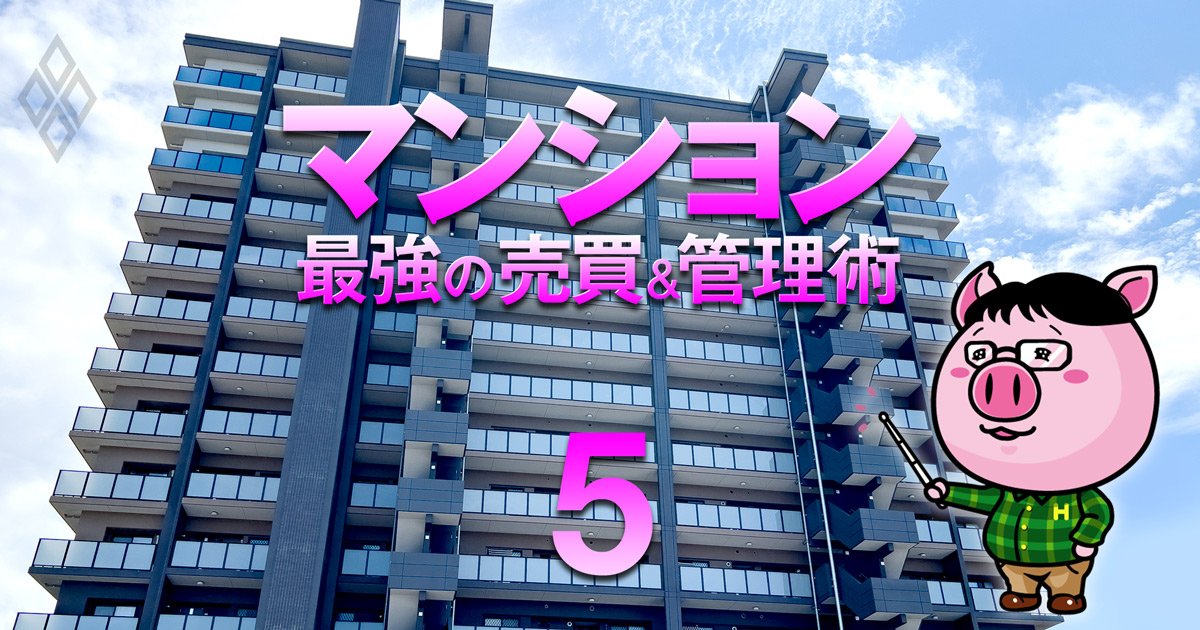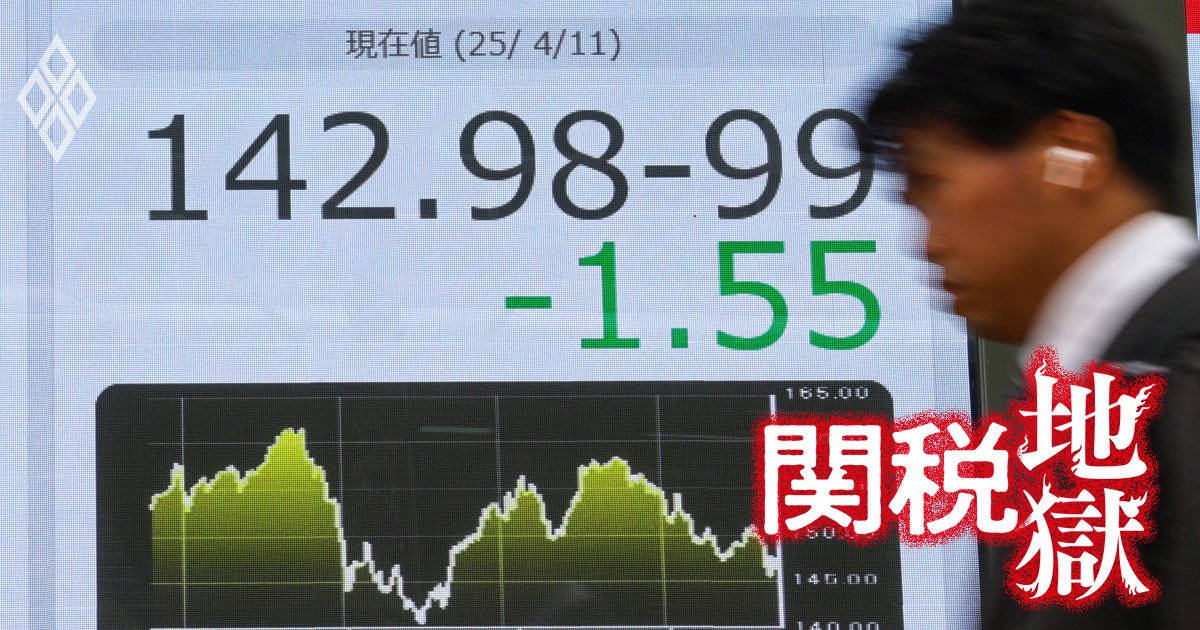ビットコインやイーサリアムに刺激を受け、自分たちで独自の暗号資産を発行しようという人がたくさん現れました。そんな人たちは、暗号資産発行の目的を記述したホワイトペーパーを発行して、「取引所へ上場前の暗号資産を安く買える」と大勢の人たちからお金を集めました。これがICOブームです。
しかし、そうやって発行された暗号資産のほとんどは、上場後にまともな値段がつかず、大半の投資家は大損することになりました。暗号資産の発行者たちは、ホワイトペーパーに書いたことを実行することなく、お金を持ってどこかに姿を消しました。後から考えれば、ICOの99%は詐欺、もしくは詐欺に限りなく近い無責任な資金集めだったといえます。
スピンドル事件もその一つです。スピンドルというのは2017年に発行された暗号資産で、(中略)ファンを対象にした投資セミナーでファンを煽りました。その結果、220億円ものお金が集まりましたが、取引所に上場後も発行元は何もせず、投資家は大損することになったのです。
ICOという言葉のイメージが悪くなって使われなくなった後、今度はIEO(Initial Exchange Offering)という言葉が出てきました。ICOは取引所上場前に、発行元が直接消費者に暗号資産を販売する仕組みでしたが、IEOでは取引所が代理店を務めるという点が異なります。発行元や取引所は「IEOは取引所による審査が入っているためICOより安全」と主張しますが、これはポジショントークにすぎません。上場後、暗号資産にきちんとした価値が付くかどうかは、発行元の行動にかかっています。ICOよりはマシかもしれませんが、IEOも非常にリスクの高い投資であることは理解しておくべきでしょう。
流行のNFTにも
リスクはある
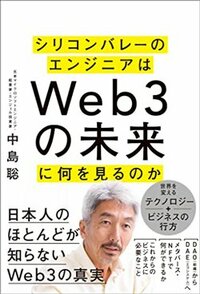 『シリコンバレーのエンジニアはweb3の未来に何を見るのか』(SBクリエイティブ)
『シリコンバレーのエンジニアはweb3の未来に何を見るのか』(SBクリエイティブ)中島 聡 著
NFTでも同様のトラブルには事欠きません。NFTプロジェクトはすべてが成功するわけではなく、NFTが売り切れなかったり、二次流通市場でまともな値段が付かないことも多々あります。それだけなら詐欺とはいえませんが、発行者によっては、NFTを発行してお金を得ながらコミュニティを盛り上げる活動を一切行なわず、姿を消してしまうこともあります。値上がりを期待してNFTを購入した人たちは、一銭の価値もないNFTを保有したまま途方に暮れることになります。
こうした行為は「Rug Pull」と呼ばれます(Rugとは玄関マットのような敷物を指します)。人が上に乗っている玄関マットを勢いよく引っ張れば、その人は転んでしまうということからできた表現です。立ち上がったばかりのNFTプロジェクトを見て、創業メンバーが真摯に価値を生み出そうとしているのか、売れたら姿を消すつもりなのか見極めるのは困難です。特に、マーケティング能力が高い人たちによるプロジェクトは魅力的に見えるもの。そうやってRug Pullを繰り返して荒稼ぎをする人たちがいるのも、現在のWeb3業界の一面だということは知っておくべきでしょう。