 日露戦争を戦った戦艦「三笠」を復元した記念艦と、戦時に連合艦隊司令長官を務めた東郷平八郎の像 Photo:PIXTA
日露戦争を戦った戦艦「三笠」を復元した記念艦と、戦時に連合艦隊司令長官を務めた東郷平八郎の像 Photo:PIXTA
夏目漱石、太宰治、司馬遼太郎…日本の近代文学史に名を刻む作家が残した作品は、なぜ「名著」と呼ばれ、時代を越えて読み継がれてきたのでしょうか。その真価や歴史的意義を劇作家の平田オリザ氏が解説します。平田氏の新著『名著入門 日本近代文学50選』の中から、今回は司馬遼太郎の『坂の上の雲』について抜粋・再編集してご紹介します。(劇作家 平田オリザ)
日本が無謀な戦争に突入した
原点を描いた『坂の上の雲』
数年前の春、大連外国語大学開催の日本語学会に招かれた。実は中国東北部を訪れたのは初めてだった。私が最も行ってみたかった場所の一つと言ってもいいかもしれない。
空港に着き、その足ですぐに大連市内を案内してもらう。旧大連ヤマトホテルなど、満州時代、あるいはそれ以前のロシア統治下のいくつかの建物を見学した。
翌日は朝から旅順、二〇三高地へ。言わずと知れた日露戦争の主戦場の一つである。
若い世代には基本的な知識もすでにないかもしれないので、念のために書いておくと、日本とロシアが戦ったこの戦争の地上戦は、ほぼすべて現在の中国東北部、かつて満州と呼ばれた地域で行われている。中国の人々にとっては、誠にはた迷惑な戦争だった。
『坂の上の雲』は、この戦争の過程が、過剰なほどに緻密に描かれている。十年ほど前にNHKでドラマ化されたので、そちらをご覧になった方も多いだろう。
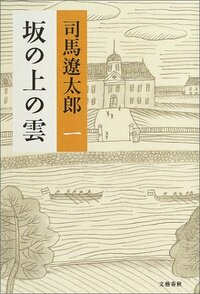 『坂の上の雲』(文春文庫)
『坂の上の雲』(文春文庫)司馬遼太郎(しば・りょうたろう)【1923~96年】
書影:文春文庫



