(4)手数料
金融商品の手数料は基本的に商品の売買時に支払いますが、保有中にも運用コストがかかる商品もあります。保有中の手数料を強く意識する必要があるのは、投資信託のような、プロに運用を任せる金融商品です。投資信託は、保有中も運用にかかる手数料が毎日日割りで差し引かれています。
日経平均株価のような参考指数に投資する「インデックスファンド」なら、手数料が低い商品を選べば問題ないでしょう。ただ特定のテーマや独自の手法などで運用する「アクティブファンド」の場合には、よく考えて商品を選ぶ必要があります。
販売用資料やレポートで投資先を確認して、類似商品と比較することはもちろんですが、日経平均やTOPIXなどのベンチマークとたいして変わらない運用をしている商品、運用方法がよくわからない商品、期待リターンに対して手数料が高すぎる商品などは論外です。
もちろん、自分で運用するには労力がかかりますから、その分の手数料を払ってもいいと思える水準は人それぞれだと思います。手数料を払う価値のある商品も当然あります。
ただ手数料が高いほど良い商品というわけではありません。基本的には手数料をかけない運用を中心に考えることで、費用の削減=収益の増加につながり、運用成果に良い結果をもたらしてくれるでしょう。
(5)実績
債券は満期保有すれば額面金額が返ってくるので「実績」という考え方にはなじみません。しかし、満期のない投資信託や株式、REITは過去の実績が参考になります。上場したばかりのものは実績がないため、様子を見たほうがいいでしょう。
ただし、ある程度の実績がわかる場合でも、過去の実績が良かったからといって将来の値動きが約束されるわけではありません。参考になるのは、過去の値動きが悪かったケースです。
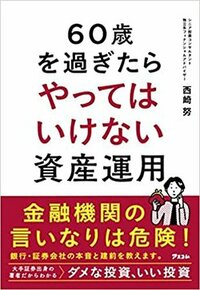 『60歳を過ぎたらやってはいけない資産運用』(アスコム)
『60歳を過ぎたらやってはいけない資産運用』(アスコム)西崎努 著
例えば、値動きはベンチマークと同じように推移しているのに、なぜか運用成果で劣る場合があります。こんなときは、「運用コストの分だけ負けているのではないか」と疑います。
また、投資銘柄が近いファンド同士を比較して想定される値動きをしていない場合は、「想定していたよりもリスクが大きいから」かもしれません。
もし新しく設定された投資信託などを検討するのであれば、目論見書に記載された運用方針通りに運用されているのかどうか、運用方針通りであっても自分の想定と合っているかどうか確認をしてからでも遅くはありません。
最低でも半年、できれば2年程度は運用の推移を確認したいところです。



