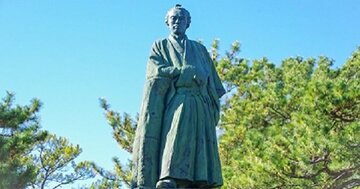Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
上杉謙信・武田信玄が刃を交えたとされる川中島合戦は、その戦いを巡る伝承の多くが「後付け」とされている。史料には両雄が一騎打ちしたという明確な証拠はなく、武田軍による奇襲作戦「キツツキ戦法」も実在したかは定かではない。本稿では、筆者が現地を探訪して得た知見を踏まえながら、歴史ファンが“拍子抜け”するであろう合戦の実態を解説する。(作家 黒田 涼)
有名な川中島合戦だが
その伝承は「出来過ぎ」だ
関ケ原、桶狭間と並んで、戦国時代の「3大有名合戦」とでも言えそうなのが川中島合戦だ。
この合戦は、武田信玄・上杉謙信の両雄が1553年から1564年まで、足掛け12年にわたって北信濃・善光寺平の覇権を争った一連の戦いを指す。
第4次とされる戦いでは、信玄の本陣に謙信が単騎で攻め込んで3度太刀を浴びせ、信玄は手にした軍配で受けたという。
しかし歴史学的にいうと、この川中島合戦はとても謎の多い合戦で、史料も極めて乏しい。特に1561年の第4次合戦では、両雄の対決があったかどうかもかなり怪しく、合戦の場所すらほぼ不明で、「まぼろしの合戦」と言ってもいいほどだ。
実際はどうだったのか、筆者が現地を訪れて得た知見を、わずかに残る史料の内容を交えながらご紹介する。
まず川中島の場所だが、「合流して信濃川になる犀川(さいがわ)と千曲川(ちくまがわ)に挟まれた場所」と聞いたことがある方も多いだろう。しかし史料で確認できる中で、実際に川中島で行われた戦いは5回のうち2回しかない。第2次と第4次である。
あとの合戦は、現在の長野市や千曲市の盆地部分である「善光寺平」の広い範囲で行われた。これらを含めた総称が、川中島合戦というわけだ。この合戦の呼び名は必ずしも間違いとは言えないが、実は歴史学者の中では「そう呼ぶべきではない」という意見もある。