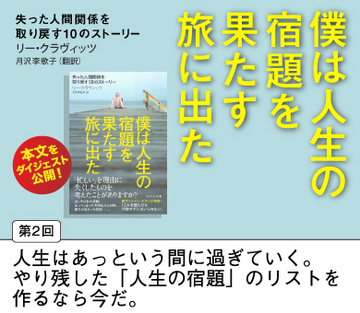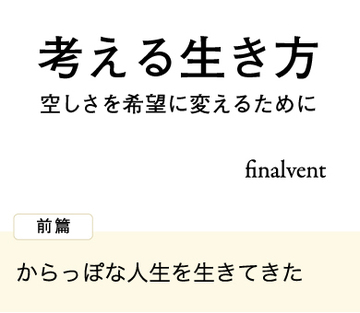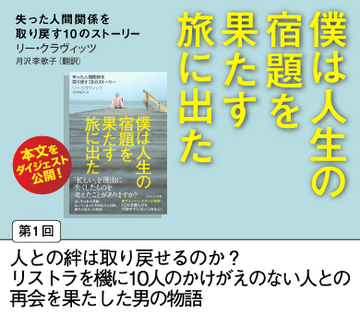その少年は13歳にも、16歳にも、
21歳にも見えた
18ヵ月前に設置されたこのキャンプには、3万7千人の難民が暮らしていた。多くが子どもかティーンエイジャーだった。
安全検査が済むと、救助員たちが袋にはいった豆、米、モロコシを、長い列を作って待つ難民の女性たちに分配した。
ケア・インターナショナル、国際救済委員会(IRC)、ユニセフといった組織からやって来た難民救済ワーカーが、キャンプ内を動き回っていた。
理想に燃えた若者たちである。訛りから、カナダ、アメリカ、フランス、オーストラリア、ギリシャなど、世界中から来ているのがわかった。
この焼けつくような暑さのなかでも、エネルギーを発し、ユーモアを忘れずにいた。
僕はこれまで別の難民キャンプを訪れたことがあるので、救助員はたいてい不満を抱えているのを知っていた。ビールの一杯でもおごってやれば、カクマには食糧や医療支援が足りないという話を聞くことができるだろう。
また、彼らは、自分たちがやっていることの価値に対する疑いを口にするかもしれないし、ここにいる子どもたちをもっと気にかけてほしいと訴えるかもしれない。
キャンプの中央を走る広い泥の道の脇に、木造の小屋でできた仮設の市場が並んでいた。なかにはコーヒーや紅茶や文房具を売っているところもあるが、ほとんどは日陰に座ってラジオを聞く場所を提供しているだけだった。
「ラ・リベリア・レストラン」「ザ・ツイン・ホテル」「テープとラジオの修理店」などを宣伝するカラフルな手書きの看板があった。
酷暑のなかを、十代の少年たちのグループが、サッカーボールを蹴っている。それを小さな子どもたちがまわりから囃したてていた。
僕は、救助員のひとりに付き添われ、近くにいたソマリアからの難民たちが集まっているところへ入っていった。そこで出会った少年の顔は忘れられない。
美しい顔ではなかった。険しい表情は、村が破壊され、母親と父親と親類を失い、徒歩と車でカクマまで長い旅をしてきたせいだろう。しかし、少年は明るく顔を輝かせて笑い、質問をした。
何歳かはわからなかった。光の加減で、13歳にも、16歳にも、21歳にも見えた。
“アフリカ'92”という文字が入った、鮮やかな黄色のTシャツを着ていた。おそらくなにかのスポーツ大会のものだろう。
少年は僕にアメリカン・フットボールについて知りたい、自分の好きなサッカーとどう違うのかと言った。
少年が親友三人と暮らしている小屋を訪れると、屋根は草をふいたもので、床は泥のままだった。少年は僕に段ボールの切れ端を差し出し、座るように言った。少年がお茶を淹れているあいだ、僕は小屋のなかを見回した。壁にはイギリスの雑誌から切り抜いた記事や広告が貼ってあった。
ほとんどが可愛い少女かサッカーの選手の写真だった。少年たちが抱く夢と、現実とのあまりに大きな違いに、胸が痛くなった。