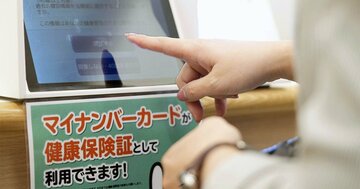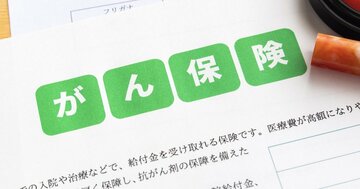所得が「一般」「住民税非課税」の人は
通院のみの高額療養費の限度額がある
<お得なポイント:2>
70歳以上の高額療養費には、通院のみの自己負担限度額が設定されている
もうひとつ、70歳以上の人の高額療養費のお得な仕組みが、外来(通院)のみの限度額の設定だ。
70歳未満の人の高額療養費は、通院・入院の区別はない。通院でも、入院でも、所得に応じて分類された5段階のいずれかが限度額になる。
たとえば、70歳未満で、年収500万円の人の高額療養費の限度額は、【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】。個人ごと、医療機関ごと、1カ月ごとに計算した医療費が、26万7000円を超えなければ、通院でも、入院でも、高額療養費は適用されない。
一方、70歳以上で、所得が「一般」と「住民税非課税」の人の高額療養費には、「世帯全体の通院+入院」の限度額のほかに、「個人ごとの通院」の限度額も設定されている。そのため、日常的な通院による医療費の負担も一定額までに抑えることができるのだ。
鈴木太郎さん(73歳)のケースで考えてみよう。
◆試算条件
医療費の自己負担割合:2割
高額療養費の所得区分:一般
高額療養費の限度額:通院(個人ごと)1万8000円
通院+入院(世帯全体)5万7600円
かかった医療費:A病院…医療費6万円、窓口負担額1万2000円
B病院…医療費5万円、窓口負担額1万円
鈴木さんは、1カ月にA病院とB病院に通院し2つの病院の窓口で合計2万2000円を支払った。世帯単位の限度額は5万7600円なので、これだけでは高額療養費の対象にはならないと思うかもしれない。
だが、70歳未満で所得が「一般」の人には、通院のみの限度額が設けられており、鈴木さんの場合は1万8000円。そのため、世帯合算の申請をすると超過分の4000円が払い戻されるのだ。
さらに、所得が「一般」の人の通院の自己負担額には、年間上限も設けられているので、1年間にかかる通院の医療費は1人当たり、最大でも14万4000円だ。
また、同一月に、同じ健康保険に加入している家族の医療費も高額になった場合は、その自己負担分も世帯合算できる。
たとえば、鈴木さん世帯の高額療養費の限度額は5万7600円なので、妻が入院して医療費が100万円かかった場合、最大でも自己負担するのは5万7600円でよい。そのため、夫が支払った通院の自己負担分1万8000円は、申請すると払い戻してもらえるのだ。
今回、見てきたように、70歳以上の人の高額療養費には、「自己負担額のすべてを世帯合算できる」「外来(通院)のみの自己負担限度額が設定されている」という、現役世代はない2つの仕組みがある。だが、せっかくのお得な仕組みも、自ら利用しなければ、そのメリットを享受することはできない。まずは、毎月かかっている医療費や、自分の高額療養費の限度額を確認し、医療費が取り戻せそうな場合は、加入している健康保険に問い合わせてみよう。