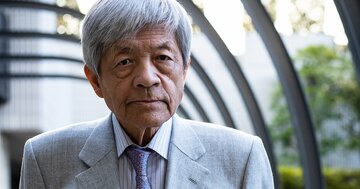新しい時代に向けて教育が育むべきは
「矛盾や葛藤に向き合う力」
 Photo by Teppei Hori
Photo by Teppei Hori
鈴木 結局、AIが出す答えというのは、そのAIを開発した人の設計思想に大きく左右されるのです。それを検証せずに、世の中に出てしまっているんですよ。
ですから、先ほどの「誰を優先して治療するか?」という問いも、どのAIを使うかによって、判断が変わってきてしまう。
つまりは、AIを使うにしても、どのAIを使うのかは、やはり人間にしか決めることができないんです。
田原 迷いながら、人間が決めるしかない。
鈴木 そして、迷ったときの指針として、フィロソフィーをしっかりと持っておく。いざというときにバタバタして考えるのではなく、平時から自分が大切にすべき価値観、決断をするときに立ち返るものを、軸として決めておきましょうと。
それは、人それぞれ違うんですよね。経営者も政治家も、それぞれ違う。学生が企業を選ぶとき、国民が政治家を選ぶとき、何に寄って立つのか、ということをあらかじめしっかりとよく考え、その考えを磨いておく。このことを私はずっと、言い続けているんです。
 Photo by Teppei Hori
Photo by Teppei Hori
田原 僕は哲学者の梅原猛さん(※)を大変尊敬しているんです。彼は生前、京都に住んでいましたが、僕は3回訪れ、梅原さんと哲学について語り合いました。
※1925-2019年、哲学者。立命館大学教授、京都市立芸術大学学長、国際日本文化研究センター所長などを歴任。ハイデッガーと実存主義に傾倒するが、のちに仏教への関心を高める。宗教、古代史、民俗学など日本文化の深層を哲学的なアプローチで研究した幾多の論考は「梅原日本学」と呼ばれ、独特の世界を切り開いた
梅原さんは、デカルト、カント、ニーチェやハイデッガーを徹底的に研究したあと、釈迦(しゃか)の考えに行き着くわけですよ。急に仏教のほうへ。「何で仏教へ行ったのですか」と聞いたのです。
すると、「人間というのは、理性だけでは生きていけない。どうしても、宗教などの、寄って立つものが必要になる」と。この言葉は鈴木さんはどう思いますか。
鈴木 まったくその通りです。デカルトやカントは、理性の重要性を主張したのですが、でも実際、人間はそんなに理性的になれやしないと。
田原 人は理性だけでは生きていけない。私もその通りだと思います。
鈴木 ですから、そこに感性や、宗教含め、哲学ですよね。最後に自分が信じるべきものを持っておくことが大事なんだと思います。私の授業では、西田幾多郎(※)を学ぶんですよ。西田は、生命というのはもともと矛盾を抱えているものなんだと、「絶対矛盾的自己同一」ということを言っています。
※1870-1945年、哲学者。京都大学名誉教授。東洋思想の地盤の上で西洋哲学を融合し、「西田哲学」と呼ばれる独自の哲学を築き上げる。近代日本における最初の独創的な哲学と評され、西洋の哲学者にも大きな影響を与えたとされる。著書に『善の研究』『哲学の根本問題』など
田原 矛盾に苦しみ、答えが見つからず、生きるのが嫌になって、自ら命を絶ってしまう人はあとを絶たないですね。
鈴木 矛盾することはいけないことだと、思ってしまうんですね。ですが、矛盾はいけないことなんかではありません。生きていれば矛盾と出あうことは当たり前なんだと、周知できれば、そこに苦しむ人は減るはずなんです。今、教育が行うべき、もっとも重要なポイントでもあります。
私は「OECD Education 2030」(※)の共同創業メンバーですが、そこで一番大事にしていることの1つが、まさに「Reconciling tensions and dilemmas」、つまり、「矛盾や葛藤に向き合う力」です。
※2015年からOECD(経済協力開発機構)が進めてきた「Future of Education and Skills 2030プロジェクト」の通称。2030年という時代を見据え、どのような教育が必要なのかをOECDの加盟国で考えていくもの。鈴木氏は文部科学大臣補佐官時代から、このプロジェクトの発足に参画している
この力が養われないと、問題に向き合ったときに心が折れてしまう。「答えが見つからない」と落ち込んでしまう。世の中にある問題なんていうのは、そんな簡単には解けないし、そもそも答えなんてないかもしれない。だから今も問題として存在しているわけです。すぐに解ける問題は、AIやロボットに任せておけばいい。
要するに、人間というのは、難題と向き合っているからこそ、人間なんだと。だから問題が解けなくても、ちっともおかしいことではない。このことを教育で教えれば、矛盾に直面して悩み過ぎることはなくなります。
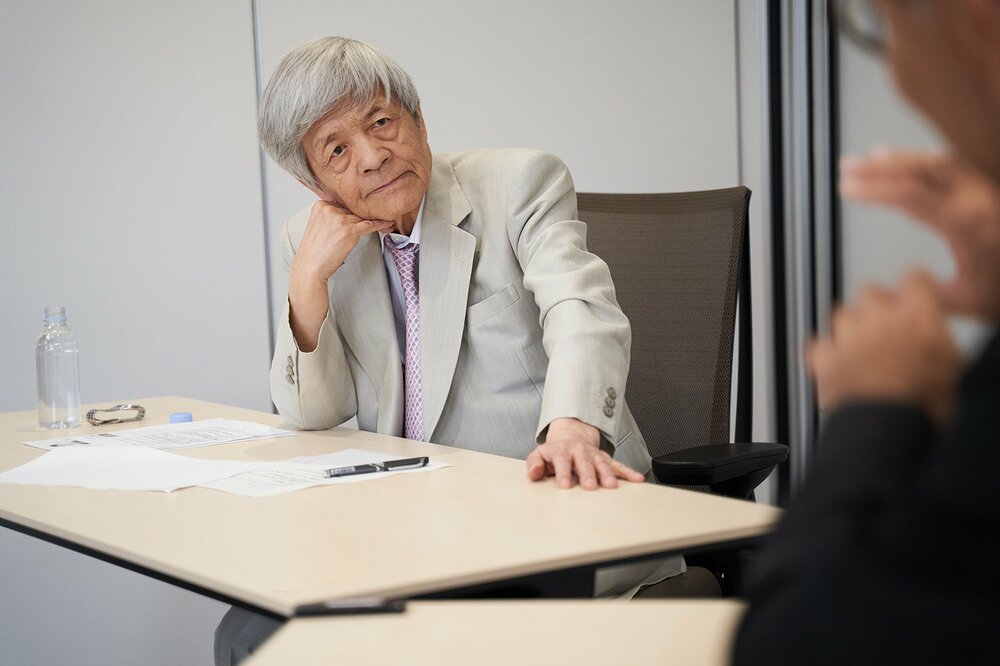 Photo by Teppei Hori
Photo by Teppei Hori
田原 そのためには、自分の好きなこと、大切にしたい価値を突き詰めておく必要がある。
鈴木 はい。大学の4年間、探し続けてもらうんです。
田原 でも、それが見つからない人もいますよね。その場合はどうするんですか?
鈴木 おっしゃる通りです。そんなにすぐに見つかるものではありません。ですので「旅に出ろ」と言っています。
もちろん、文字通りの旅もあれば、図書館で本と出あったり、いつもと違ったジャンルの映画を見たり、そうしたことも旅です。人との出会いだって旅です。東京には1300万人が暮らしていますが、「君はそのうち何人に会ったことがある?」と聞くと、同じ学校の友人ぐらいしか会ったことがなかったりします。
要するに、これまで自分の知らなかった、未知なる存在と遭遇してみる。これを続けていると、「これは自分と相性がいいな」とか「これは何だか嫌いだな」というのが、どんどんわかってくるはずです。「好きだと思ってやってみたが、意外とそうでもなかった」ということもあるかもしれません。
田原 教えて学ばせる、ではなく、とにかく好きなことを見つけてもらう。その手助けをするのがこれからの教育だと。
鈴木 そう思います。
田原 鈴木さんにとって、一生懸けてやりたい「好きなこと」は何ですか。