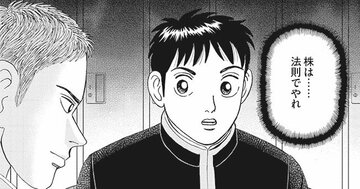『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の投資マンガ『インベスターZ』を題材に、経済コラムニストで元日経新聞編集委員の高井宏章が経済の仕組みをイチから解説する連載コラム「インベスターZで学ぶ経済教室」。第62回は、日経平均が史上最高値を更新するなど急上昇する日本株の未来を展望する。
10年前「ゴミ」と言われた日本株が…
投資部の合宿でOBたちは現役メンバーの投資スタンスを頭ごなしに否定する。特に日本株に偏るポートフォリオへの風当たりは強く、「世界と比較したら日本株なんてゴミもいいところだ!」と米国株へのシフトを促す。
日本株を「ゴミ」と言い捨てるこのエピソードが掲載されたのはおよそ10年前。その頃の日経平均株価は1万6000円前後だった。
そのさらに10年ほど前の1995年に、私は日本経済新聞社に入社し、株式市場担当記者になった。当時、日本経済は不良債権と円高の逆風に苦しんでいた。入社時の日経平均は1万5000~7000円程度。その年の夏には92年に付けたバブル崩壊後の安値(当時、1万4309円)に迫った。
途中、浮き沈みはあったものの、20年近くかけて日経平均はほぼ「行ってこい」だったわけだ。この間に数倍に跳ね上がった米国株と比較するまでもなく、日本株は「ゴミ」と言われても仕方ないほど長年低迷を続けた。
「日経平均10万円説」はバラ色の未来ではない
 『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
その日経平均は先週、
意見が一致したのは「株高の起点は伊藤レポート」という見立てだ。一橋大学の伊藤邦雄教授が中心となって2014年にまとめた報告書は、ROE(自己資本利益率)8%という明確な目標を掲げ、資本効率やガバナンス(企業統治)への感覚が鈍かった日本企業や株式市場にカツを入れた。
異次元緩和のような派手な花火ではなかったが、少しずつ日本の株式市場の体質を変える漢方薬として機能した。ガバナンス改革の下地があったらからこそ、デフレマインドの払拭という「仕上げ」が今の株高を呼びこんでいる。
藤野氏は日本経済のインフレ転換を前提に、「10年後の日経平均10万円」を見据える。浮かれた楽観論に聞こえるかもしれない。だが、それは決してバラ色の未来ではない。
企業の売上高や利益、そして株価も名目値だ。インフレが進めば数字はかさ上げされる。「日経平均10万円説」はインフレだけを頼みにした予想ではなく、日本企業が成長力を高めること、新しいビジネスが育つことが条件だ。
仮に藤野氏のシナリオ通りに行けば、日本経済は活力を取り戻すだろう。だが、その過程はミクロ、マクロの両面で不安定で不確実な時代になる。足元の変化を挙げれば、賃上げについていけない企業は人材を確保できず、淘汰される。
デフレ時代ならお金を預貯金に「寝かせる」が合理的だったが、インフレが定着すれば適宜「モノ」に置き換えたり、資産運用でリスクを取ったりと、決断とアクションが求められるようになる。
今の株高は、デフレという憂鬱だがぬるま湯的な「静の時代」から、「動の時代」への転換の予兆かもしれない。
 『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
 『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク