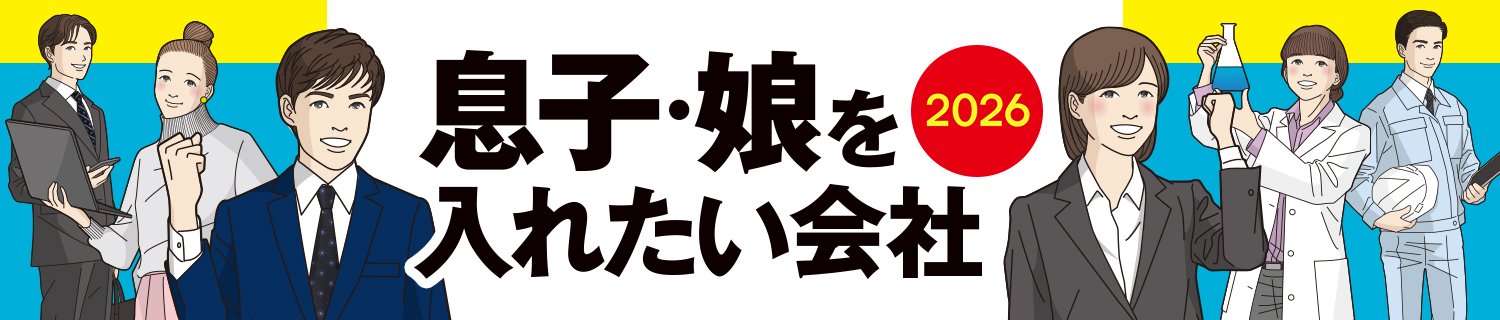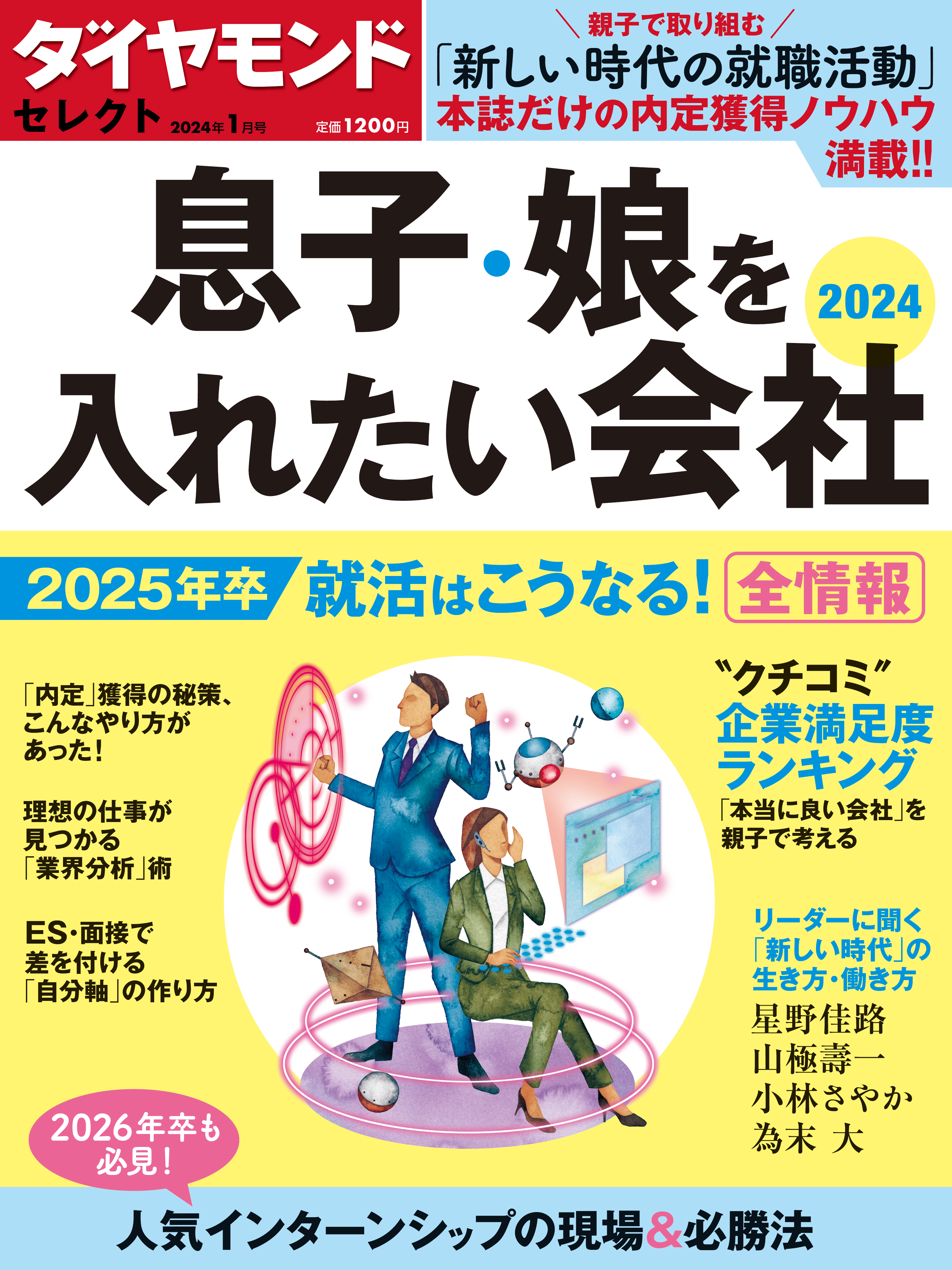持病やコミュニケーション難でも
企業が採用を決めた理由
求人サービス大手のエン・ジャパンが展開するリファレンスチェックサービス「ASHIATO」では、次のような流れでリファレンスチェックが進められる。
まず、採用企業が採用候補者へリファレンスチェックを依頼し、候補者が前職などの上司・同僚・部下に回答を依頼する。その後、上司・同僚・部下からの回答結果が採用企業に届き、その内容から採用の可否が判定される。
ASHIATOを利用したリファレンスチェックで取得できる主な情報は3つある。まず「総合信頼貯蓄」で、ビジネス思考、対人関係力、発想思考、論理思考、メンタルタフネス(5点満点評価)だ。
また候補者の前職での働きぶりも分かる。記述式の設問になっており、内容や質問数は企業が自由にカスタマイズできる。
さらに、推薦者からみた職場態度も確認ができる。コンプライアンス順守、ハラスメント傾向、勤務態度(5段階評価)が主な内容だ。
では、実際にどんなケースでリファレンスチェックが使われたのか。ASHIATOの事業責任者である小野山伸和氏に取材した。
A社では、マネージャークラス以上のポジションに採用する際に、必ずリファレンスチェックを行っている。上位の役職で誤った採用が行われると、経営に与える影響が大きいからだ。
最近、A社はデータアナリティクスのチームリーダーを採用する際にもリファレンスチェックを実施した。その際、候補者の持病が判明した。候補者は事前にそのことを告白していたが、同社が用意していた仕事の環境がかなり厳しいため、その候補者が適応できるかが不安だった。
しかし、リファレンスチェックの結果から、候補者がこれまで持病と上手に付き合いながら業務をこなしてきたことが判明した。また、必要に応じて休暇を取り、その後もスムーズに復帰していたことも分かった。候補者が入社後に担当するべき役割やミッションについても十分なイメージを持つことができたため、採用を決めた。
また、会計業務のコンサルティングを行っているB社は、相続業務のコンサルティングに専門性の高い人材を採用しようとした。
50代のある採用候補者が、初回面接では専門知識はあるものの、コミュニケーション能力が柔軟ではない印象だった。
しかし、リファレンスチェックの詳細なリポートを見ると、コミュニケーションに関しては許容範囲内だと判断され、専門性がより重要だという結論に至り採用が決まった。
入社前のリスクを事前に検知
ミスマッチが減り離職者が10分の1に
一方で、リファレンスチェックにより不採用となったケースもある。
C社の採用候補者は、2回の面接でどちらも高評価だった。そのため、内定を出す前に3人の前職関係者にリファレンスチェックを依頼したが、1人からしか回答を得られなかった。しかも、リポートでは評価が低く、いい結果ではなかった。
この候補者は、もともと営業職で話し上手だったため面接では高評価を得ていたが、リファレンスチェックの内容と照らし合わせた結果、不採用となった。
また、D社では内勤営業のポジションでリファレンスチェックを活用した。ある採用候補者について、勤務態度が不安定で課題に対して十分に取り組んでいないことが判明した。さらに、その候補者が社内の文化に適応できるか懸念もあったため、採用を見送ることにした。
このように、選考プロセスで注視すべきポイントを可視化できるようになった結果、採用時のミスマッチを減らすことができた。
「年間数十~数百人の社員を採用している企業で、以前は入社後1年以内に20人ほどが離職していたが、リファレンスチェック導入後は2人と10分の1に減少したところもある」(小野山氏)という。
人材採用におけるミスマッチをなくすのは、企業にとって永遠の課題だ。採用候補者にとっても、面接時の評価がいまいちで不採用になりかけたが、リファレンスチェックによって採用につながるという恩恵もある。
企業側が求職者の悪いところをあら探しするようなイメージを持たれがちなリファレンスチェックだが、職場環境に適した人材獲得をするうえで強力なツールの一つとなる。