*〈前編〉はこちら
ビジネスにイノベーションは不可欠である。これに異を唱える人は少ないだろう。しかしながら、「イノベーションとは何か」と聞かれて、それを自分の言葉できちんと答えられる人がどれほどいるだろうか――。
『イノベーションのジレンマ』(翔泳社、2000年)の著者として知られるクレイトン・クリステンセンは、本誌2024年夏号に掲載した遺稿「第3の解」の中で、こう記している。「イノベーションという言葉は、当たり前のように多用され、その理解は矮小化されている」と。
事実、日本においても、曖昧模糊としたイノベーションが蔓延している。「◯◯イノベーション」といった具合に、◯◯の部分には教育、街づくり、グリーン、ワークスタイルなど、もはや何でもあり。だが、何をどうするのかが明確に示されることはほとんどなく、雰囲気づくりに使われているものも少なくない。ほぼ造語競争の域ではないか。それだけイノベーションという言葉が都合のよい言葉として使われている証左だろう。
こうした状況を「何となく・何でもイノベーション症候群」と名付けて警鐘を鳴らしているのが、本誌に2号連続で登場いただく妹尾堅一郎氏だ。前号(2024年夏号)でのインタビュー前編で妹尾氏は、本格到来が迫る資源循環経済(サーキュラーエコノミー)に向けた処方箋を解説。「使い続けのモノづくり」を中心とした新たなビジネスモデルへの転換を提唱された。
それを踏まえた次なる議論が、イノベーションである。従来の線形経済(リニアエコノミー)から資源循環経済へという経済モデルのパラダイムシフトが迫る中、間をつなぐバトンゾーンで何を準備するのか、言い換えれば、ビジネスモデル変革が問われている。そのカギを握るのが、まさしく懸案のイノベーションである。日本企業の宿題ともいえるこのテーマにどう取り組み、世界の強豪たちと伍していくのか。資源循環経済という修羅の道での道標を探りたい。
日本企業が陥る
何でもイノベーション症候群
編集部(以下青文字):資源循環経済はイノベーションの宝庫であると妹尾先生は主張されていますが、多くの日本企業にとってイノベーションは大きな経営課題でもあります。そもそもイノベーションのとらえ方が人によってまちまちで同床異夢を生んでいる。先生はこうした状況を「何となく・何でもイノベーション症候群」として警鐘を鳴らしています。
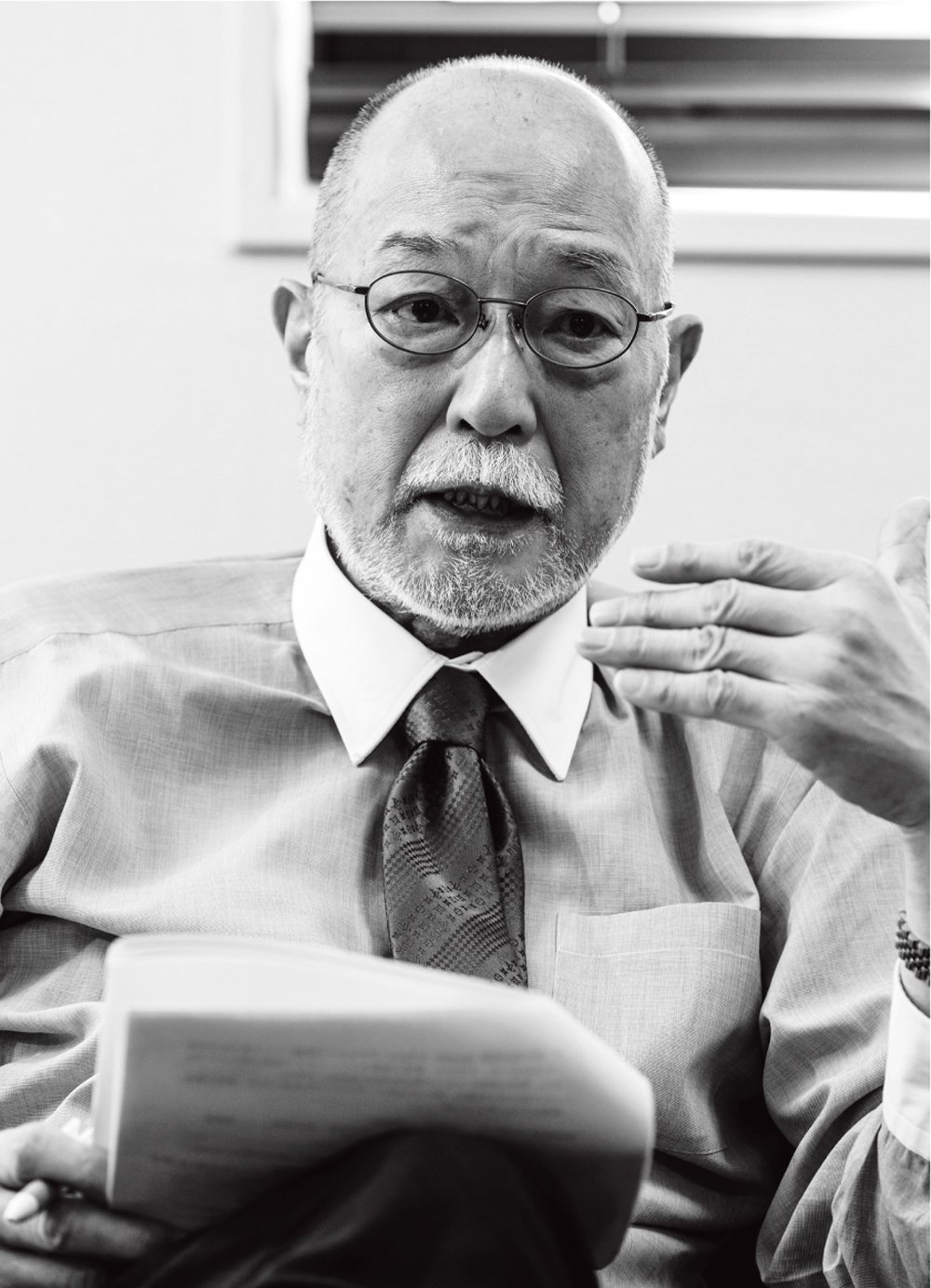 産学連携推進機構 理事長
産学連携推進機構 理事長妹尾堅一郎
KENICHIRO SENOH慶應義塾大学経済学部卒業後、富士写真フイルム(現富士フイルムホールディングス)勤務を経て、英国国立ランカスター大学経営大学院博士課程満期退学。産業能率大学助教授、慶應義塾大学大学院教授、東京大学先端科学技術研究センター特任教授、一橋大学大学院MBA客員教授のほか、青山学院大学大学院、九州大学や長野県農業大学校等、多くの大学・大学院で客員教授を歴任。現在も東京大学で大学院生や社会人を指導。また、企業研修やコンサルテーションを通じて、イノベーションやビジネスモデル、新規事業開発等の指導を行っている。内閣知的財産戦略本部専門調査会長、農林水産省技術会議委員、警察庁政策評価研究委員等を歴任。日本知財学会諮問委員(前理事)。CIEC(コンピュータ利用教育学会)終身会員(元会長)。研究・イノベーション学会参与(元副会長)。現在、日本生産性本部で「循環経済生産性ビジネス研究会」座長。そのほか、省庁や公的機関の委員、複数の企業で社外取締役を兼務。著作に『技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか』(ダイヤモンド社、2009年)、『社会と知的財産』(放送大学教育振興会、2008年)、『グリッド時代 技術が起こすサービス革新』(アスキー、2006年)、監訳『プラットフォーム・レボリューション』(ダイヤモンド社、2018年)などがある。
ご指摘のように、日本ではイノベーションという言葉が一人歩きをしている感が否めません。最近では、教育イノベーションとか街づくりイノベーションといった具合にさまざまな分野で使われるようになり、もはや濫用の域に達して、本来の意味が希薄化しているのが実情です。何をどのようにすればイノベーションといえるのか、それがまったく提示されないままに、雰囲気づくり的に使われることもしばしばです。もちろん言葉ですから、どのように使われても、どんな定義で使われてもかまわないのですが、新規事業プロジェクトなどにおいては共通の理解がないのは問題です。企業の内外でイノベーションの意味が交錯し、混乱を来しているケースを多く見かけます。それを心配しているのです。
もともとイノベーションは、経済学者のヨーゼフ・シュンペーターが提唱した概念であることは多くの人が知るところです。シュンペーターは、イノベーションとは「価値の創出方法を変革して、その領域に革命を起こすこと」と定義し、「経済的に発展をもたらすもの」であるとしました。この理論をビジネスの世界に普及させたのが、社会生態学者としてマネジメントの世界に多大な影響を与えたピーター・ドラッカーです。ドラッカーは、イノベーションとはすなわち「体系的廃棄」であると述べ、創造的破壊によって古いものを廃棄し、新しいものに置き換えていくことであるとしています。
こうしたイノベーションの本質を踏まえれば、日本企業で広く使われているイノベーションという言葉は、そのほとんどが「インプルーブメント」(改善・改良)を意味しており、既存モデルの練磨にすぎないといえます。なかには、ちょっとした製造工程の改善アイデアでもイノベーションと呼んでしまう専門家がいることにも吃驚します。それでは1970年代に日本の製造現場で隆盛を極めた「QCサークル活動」(小グループによる自主的な品質管理活動)と何ら変わらず、イノベーションと呼べるものだとは私には思えません。
また、技術開発においてイノベーションという言葉が使われることもよくありますが、それはあくまで「インベンション」(発明)であり、イノベーションそのものと呼ぶのはいかがなものでしょう。いまだに大手メディアでも、イノベーションという言葉の後に(技術革新)とカッコ付きで補足するなど、イノベーションとインベンションを混同している場合もあるようです。
このように日常の業務改善から新製品開発、新規事業に至るまで、あらゆるビジネスシーンでイノベーションが濫用されている状況に危機感を抱いた私は、「何となく・何でもイノベーション症候群」と名付けて警鐘を鳴らしているのです。
では、私自身の議論におけるイノベーションの定義とは何か。それは「既存の価値形成のドミナントモデルを転換させる新規モデルを創出・普及・定着させること」です。端的に言えば、「新たな価値の創出・普及・定着」です。ここでの新たな価値というのは、部分的または限定的な改善・改良などではなく、シュンペーターが言うように、その領域に革命を起こし、経済的発展をもたらすものでなければならない。そのためには一時的な創出だけでは不十分で、普及・定着して、初めてイノベーションと呼ぶことができる。つまり新規事業が立ち上がるだけではなく、一人前の事業になるまでをも含むはずです。社会実装という言葉が最近の流行りですが、その実装とは、普及・定着まで含まなければ中途半端ではないでしょうか。
加えて、最近私がよく使うのは、「ビジネスイノベーション。百里の道は、技術九十九里をもって、半ばとす」というフレーズです。百里の歩みの労力の半分はビジネス、特にビジネスモデルのデザインに費やさないと中途半端で終わってしまうぞ、と警告しているのです。せめて最後の一里だけでもビジネスについてしっかり考えようぜ、と。技術革新だけで終わらせず、知を駆使して実効性がある事業に昇華できるかが問われています。
かつて拙著『技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか』(ダイヤモンド社、2009年)で指摘したように、日本企業は技術力が高いとされながらもビジネス化する力が不足しています。そのため、せっかくの技術が立ち枯れたり根腐れしたりすることが少なくありません。つまり、ビジネス化がド下手だということです。残念ながら、いまも同様です。
優れた技術をてこに優れたビジネスへと昇華させるには、「技術のR&D」(T-Rand)と「ビジネスのR&D」(B-Rand)の組み合わせが重要です。それなくして、イノベーションを実現し、資源循環経済を先導・主導するビジネスへと進展させることはできない。
また、イノベーションは本来、「未開拓の無法地帯や未法領域の創出」を意味します。もちろん「違法」はいけないのですが、AIからバイオ技術まで、あるいはウーバーやエアビーアンドビーなどが象徴するように、イノベーションとは未開拓領域、すなわちブルーオーシャンですから、既存の制度や慣行で縛られてはならない。かといって野放図にするわけにもいかない。新しい価値観を体現するには、制度的な制約とともに、制度的な支援も求められる世界です。
ゆえに日本企業は、「何となく・何でもイノベーション症候群」から早く脱却すべき。ブルーオーシャンに漕ぎ出せば嫌でもイノベーションになることに気づいてほしいのです。

![[検証]戦後80年勝てない戦争をなぜ止められなかったのか](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/8/360wm/img_98a65d982c6b882eacb0b42f29fe9b5a304126.jpg)





