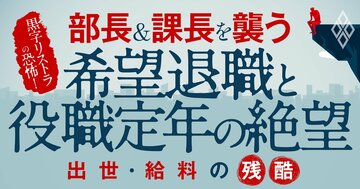田山花袋は2つの小説で
自らの恥ずかしい恋愛を明かす
そのことを如実に示すのは、『蒲団』(編集部注/田山花袋の中編小説。自分の家に下宿していた文学上の弟子である岡田美知代への恋愛感情を詳細に著し、センセーションを起こした。岡田美知代の布団の匂いを嗅いで泣く描写が有名)に続く作品である。
花袋は『蒲団』の発表後、岡田(永代)美知代とのいきさつの後日談ともいうべき小説『縁』を書いた。そこにちらっと登場するのが、田山花袋がそのあと深い仲になった向島の芸者小利(ことし)である。
『蒲団』が大きな反響を呼び、さまざまな批判や岡田美知代からの抗議もあったものの、花袋は自然主義の首魁(しゅかい)としての地位を占めるに至った。
おそらくは気分的に高揚してもいたのだろう、1907(明治40)年9月29日、山王公園の六月会(文章世界誌友の定例の茶話会)に出席したあと、赤坂の鶴川という待合に立ち寄った。そこで梅奴を名乗っていた芸者小利に出会う。
小利は文学好きで、文芸倶楽部の口絵に載っていた花袋に気がついた。花袋の方でも気にいって、六月会の帰りにはかならず赤坂に寄って、小利に会うようになる。
そして、そのままどんどんはまっていき、やがて、京都にいっしょに旅行したり、彼女の郷里を訪ねたりするまでになる。一番、深く馴染んだのは小利だが、ほかにも花柳の遊びをさかんにするようになり、その芸者遊びを新聞に揶揄されるまでになった(「よみうり抄」讀賣新聞1908年7月18日)。