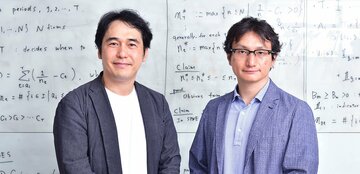![経営学は世の中にどう役立つか?(第1回)[経営学の技法]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/0/2/-/img_02343ee45c5d322693f2994585893231830178.jpg) Kiyoshi Takimoto
Kiyoshi Takimoto舟津昌平(ふなつ・しょうへい)
経営学者。東京大学大学院経済学研究科講師。1989年、奈良県生まれ。京都大学法学部卒業、京都大学大学院経営管理教育部修了、専門職修士(経営学)。2019年、京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了、博士(経済学)。京都産業大学経営学部准教授などを経て、2023年10月より現職。著書に『経営学の技法』(日経BP)、『Z世代化する社会』(東洋経済新報社)、『制度複雑性のマネジメント』(白桃書房)、『組織変革論』(中央経済社)などがある。
経営学は世の中の役に立つか。経営学とは何か。常に変化は必要か。組織変革とは何か。Z世代とは何か。世代論に意味があるのか。常識や通説を前提に話が始まることに疑問や危うさを抱き、「そもそも論」を大切にする経営学者、舟津昌平氏にベストセラー『Z世代化する社会』ほか一連の著作の執筆動機や研究姿勢についてインタビューした。連載3回で送る第1回は『経営学の技法』について聞いた。(取材・文/ダイヤモンド社 論説委員 大坪 亮、撮影/瀧本 清)
「経営学は役に立つか」の質問に
真正面から向き合った
――最初に、本書『経営学の技法』の執筆動機を教えてください。
「経営学は役に立つのですか」という質問を時々受けます。何かに役立ちそうだと一般には思われていそうですが、実際はわかりにくい。医学は人の命を救える、工学はモノを作れると明快そうな答えが用意されていますが、経営学は明確でない。その疑問にどう答えるべきかを正面から向き合ってみようというのが執筆動機です。
最初は、経営学原論のような形で教科書を書こうと思いました。その案を編集者と話し合っていると、「これならもう少し一般人向けに書けるのじゃないか」という意見をいただいて、軌道修正していきました。
――本書では、「役に立つとはどういうことか」から考察しています。
学問には専用的な使い方と汎用的な使い方があるといえます。役に立つという文脈でいわれる学問は多くが専用的です。例えば米国では軍事に関する研究に資金が集まりやすい。軍事利用は専用的な使い方の代表例ですね。
上司がリーダーシップの本を読めば部下との関係が改善されるというのも、特定の問題に対して専用的に作用するという、専用的な使い方ですね。
でも私は、それはかえって実現可能性が低い、あるいは危険なことだと思っています。この点は、本書第4章の「エビデンスベースド・マネジメント(EBM)」の項目で詳しく論じています。
また、そういう類の本は世の中に既に多くあるので、あまり言及されていない汎用的な使い方を考えてみました。それが本書のタイトルにある「技法」です。『経営学の技法』における技法は英訳すればアーツ(arts)。リベラルアーツのアーツです。
アーツを経営学から学ぶという発想で、『経営学の技法』と名付けました。ここでは思考法をより汎用的な使い方だと捉えて、技法と呼んでいます。
――具体的には3つの思考法をそれぞれの事例をもとに論じています。条件思考では「成果主義は虚妄だったのか?」、両面思考では「官僚制は悪なのか?」、箴言思考では「経営科学は役に立つのか?」という3つの問いを立てて考察しています。なぜ3つなのですか。
3つぐらいがちょうどいいからです(笑)。その程度の理由です。でも、物ごとってそれくらいの粒度で捉えてもいいよというメッセージも実はあります。
なんでも科学的とか厳密な根拠に基づいてといわれるなかで、3つぐらいっていうのはたいした理由はないけどちょうどいい。科学的かどうかはわからないけど、3つぐらいが最もわかりやすいのではないですか、というメッセージですね。
――3つの思考法の概要を順に教えてください。
まず条件思考を伝えるために、成果主義を題材にしました。一般的に興味を持たれやすいだろうけど、ほとんどの人は成果主義について深く考えたことがないと思ったからです。
20年以上前の日本企業の低迷期に、窮状の打開策として少なくない企業が成果主義を導入しますが、どちらかというと失敗し、その真相は世に理解されないままになっています。そうだとすると、再び同じことが起こるのではないか、そうならないためにどうするかを考えました。
詳細は本書に書きましたが、個人の成果と報酬を紐づけることによって動機づけ、その結果として企業業績を上げていくという仕組みは、いろいろな条件の裏付けがないと成立しません。
代表的な条件が、能力開発の機会です。人を育てる教育やその投資があってこそ社員は成果を出せるようになります。教育を一体にしないと、成果を出すことはできない。これをまず条件思考の事例として提示しています。
何か単一の施策だけで望ましい結果が得られるということは、社会において考えづらいのです。
先ほど述べた、昨今のEBMのはやりにおいては、往々にして条件思考が忘れられています。背景や文脈を単純化して、X→Y(Xが原因でYの結果となる)が成立していることのみを情報として求めている人が多い。「それは必ず条件付きだよ」ということを伝えるための話が、本書の第2章です。
――2つ目が第3章で扱った両面思考で、問いは「官僚制は悪なのか?」です。
官僚制は昔から有名な概念で、かつ多くの人がネガティブなイメージを持っているかと思います。経営学における私の専門は組織論ですが、この分野ではふって湧いたように「新しい組織(論)」が定期的に生まれてきます。ざっくり10年に1つといった頻度で、最近も「ティール組織」がはやりましたね。
もし官僚制組織が間違いで、次々と生まれる新たな組織形態が優れているならば、それらはなぜ定着しないのか、なぜ官僚制はすたれないのかという疑問が生まれます。結論を言えば、それぞれに良い面・悪い面があるからです。
組織論の変遷を振り返ると、ロバート・マートン(1910年-2003年)という著名な社会学者が「機能に対する逆機能」という考えを提示しています。個々の制度には、正の機能もあれば、負の機能もあり、両輪のように働くものです。どちらがより強く機能するかは、現実でも分からない。この点にもエビデンス主義の危険性を指摘できます。
現実には、X→Yという単一の因果関係しか起きないということはありえない。Xは他の結果の原因かもしれないし、Yは他の原因も合わさった結果かもしれないから、そうそうシンプルな図式では示せない。
――第3章の冒頭で示された「シャープの緊急プロジェクト」の事例は納得感がありました。新製品開発のために各部門から集められた同社のプロジェクト組織は脱官僚組織のように見えたが、実際は階層を維持して、その目的も人事育成に逃げずに、成果を出すことが絶対の使命とされた。官僚制はイノベーションを阻害するという通説とは異なる事例となっています。
物事には良い面と悪い面がある。しかも、その良し悪しの判断は、主体がもつ価値観に基づいた価値合理性に左右されます。社会や会社には複数の価値観が介在するために一概に良し悪しは決められないし、時とともに価値観が変わることもあります。
両面思考は、片面だけを過信して裏面の結果が想定外になってしまわないための思考法です。長い目で見て失敗を回避することの一助になるはずです。
![経営学は世の中にどう役立つか?(第1回)[経営学の技法]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/7/5/250/img_75bf8142117b4fcadc75c4a1ece8d45129202.jpg)