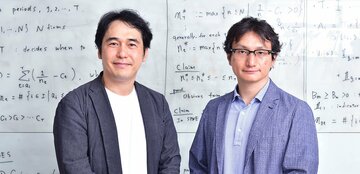ドラッカーは経営学者でなく
世の中の役に立たないか
――3つ目は箴言思考で、問いは「経営科学は役に立つのか?」。本書の第4章です。
今、経営学はすごく科学化しています。サイエンティフィックであることを求め、サイエンティフィックでないといけない、サイエンティフィックでない先人の論考は読む必要がない、という流れになっています。
例えば、「ピーター・ドラッカー(1909年〜2005年)は経営『学者』でない、科学的でないからだ」と言う人もいます。 しかし、経営学者の三橋平先生の論考で知ったのですが、ドラッカーは1998年に世界最大の経営学会である米国経営学会(Academy of Management)で基調講演をしています。学界で評価もされていたし、そうそう昔の話でもないのです。
第4章では、科学とEBMをテーマにして、科学的な言明が現実の世界に何をもたらすかについて考察しました。
題材としたのが、科学的経営の源流ともいわれるフレデリック・テイラー(1856年〜1915年)の『科学的管理法』です。
科学的管理法と名乗っていますが、テイラーの論考ははっきり言って科学的ではありません。主張している因果関係の妥当性や再現性などについては科学的手続きを満たしていないとされる点が多いのです。
ちなみに1920年の時点で既に、暉峻義等(てるおかぎとう)という日本人学者がテイラーの主張が科学的でないことを指摘しています。
テイラーは科学的管理法と銘打っていたにもかかわらず、実際は科学的でもなんでもなかった。ただ注目すべきは、その手法を導入した企業に生産性向上という成果をもたらしています。科学的でないけど、結果的には社会の役に立っている。
テイラーは経営コンサルタントで、自分の手法を社会に広めていく過程では、エピソードベースで話すことが多かったそうです。象徴的な男性従業員がいて、彼に科学的管理法を教えたらこれくらい生産効率が良くなったという「少数の事実の報告」を話すタイプのコンサルティングだった。そして結果的に、成果は出た。
こうした事実を説明する仮説として、テイラーのやったことの意味とは、「管理法を改善すれば生産性は上がる」と皆に信じさせたことではないでしょうか。理屈はどうであれ、工場側の自助努力を引き出すという点で、工場のあり方を変えたことがテイラーの功績なのです。
――対して、科学的手法に基づく今日の経営学は、なかなか成果が出ない。
なかなか成果が出ないかは別として、楽観視されるほどに簡単でないのは明白です。今日の経営学の多くは、極めて純粋なX→Yの関係を追究しています。因果推論とか因果関係の究明と言われますが、そのような純粋な因果関係は、現実には起きないことが往々にしてあります。
本でも紹介した例で、すべての物質には垂直下向きの重力が働くけれども、木の葉は大抵ひらひら舞いながら落ちる。では、木の葉に垂直下向きの重力が働いていないかというと、そんなことはない。法則と現象は違う。科学的に見つけられた因果関係と、現実に起きることはしばしば異なると言えるわけです。
また、科学的に確証された知は、「効果」が小さい可能性が高いという面もあります。例えば、新しい製品が開発されてその効果を既存品と比較するというケースを考えてみましょう。効果の改善は、100%と言えるか50%程度か……「厳密な事実として言えるのは1%」というように、厳密であろうとすればするほど、その効果は極めて小さくなっていくものです。
現代的な科学知は厳密であることを追求します。しかしどこまで厳密であったとしても、望ましい結果が発現するとは限りません。だったら、厳密な科学知から「箴言」を抽出して、受け手の自由度を高めて活用するのが良いだろうというのが箴言思考です。
箴言という言葉は少し難しいかもしれません。ある読者から「科学的事実に基づいたことわざ、ということですか」と言われました。ちょっと違いますが、まあだいたいそういうニュアンスです。
こういうことを言うとぼやかしているように聞こえるかもしれませんが、実はドラッカーや著名な組織心理学者のカール・ワイク(1936年〜)らも箴言を多用しています。
――センスメイキング理論で知られるカール・ワイクですね。
ドラッカーがこれだけ社会から支持されてきたのは、本質をついた大事なことをスパッと言ってきたと同時に、あえて細かく説明していないからだと思います。
読者が勝手に「これはわかる」とか「うちの会社もこうだ」という風に読解してくれるからこそ広がりが出ていった。中には誤解もあるでしょうが、誤読の余地がないと、世の中に受け入れられないし、役に立たないのです。
何を念頭にこのように言っているかというと、ドラッカーやワイクらの箴言を多用した言説とは対照的に、今日の科学的な論文はものすごく厳密で一義的で、誤読のないように文章を作ります。それがアカデミックライティングです。
ところが、そうして書かれた論文を、「普通の人」は読むことができない。一義的に誤解のないように一言一句正しく書かれたはずの文章を一般人は読めない。東大生であろうと、修士や博士などの研究課程で訓練を積まないとほとんどの人は理解できない。
そうしたギャップを考えると、科学を、あるいは経営学を世の中に生かすためには、箴言のように用いてもらうのが良いだろうということで、箴言思考を3つ目に置きました。
――終章で「締めくくりに、本書は決して『アンチ科学』でないことは強調していきたい」と書かれています。
そこは、悪い意味での誤解がないように書きました。まず、科学は限界を見定めることに長けています。言明できる範囲を狭めて、「これだけは言える」部分を囲い込む営為です。前述したように、結果的に言明できる領域はごく僅かになりがちです。
それを実用化するために重要なのが累積効果です。1%しか効果が明らかにできないとしても、コツコツと積み重ねていくことで大きな成果になっていく。
そして、科学は集合的であり、多義的です。アイザック・ニュートン(1642年〜1727年)の「巨人の肩に乗る」という言葉通り、過去の蓄積や他人の力を借りないと物ごとは何も分からない。
天才はそれまでの通説をすべて覆して新しいものを見つけるみたいな言い方がされることがありますが、それは逆に科学的ではない。ちなみにそういう事象を考察したのが、トマス・クーン(1922年〜1996年)のパラダイム概念ですね。
科学は先人の知を活用する前提でできていますから、それをすべて覆すというのは逆におかしいというか、何をやっているんだという話になる。
だから私が意識しているのは、古典を含めていろいろな先人の考えを紹介し、その積み重ねに乗って考察することです。それ自体がとても科学的な作業であると思っています。
最後に、科学は倫理に支えられています。科学的であるためには誠実でないといけません。忘れられがちな倫理的側面を強調してくれるのも、科学の一側面だといえます。
*明日公開の第2回は、「変革は必要なのか」から説き始める『組織変革論』についてのインタビュー記事です。