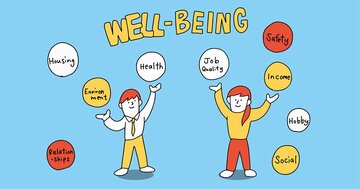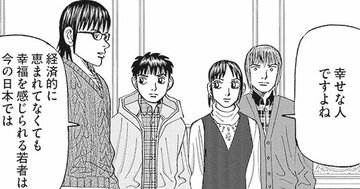どうしようもなく落ち込んでいる。その落ち込んだ気持ちを忘れたい。
その時に、話題のスポットに行ってみる、話題のレストランに行ってみる。
そうして落ち込んだ気持ちを忘れたい。
そうして、「I am happy.」と言えば何とかなる。
話題のレストランに行ってみても、夜にはなかなか眠れない。朝起きて気力が湧いてこない。
そこでまた気を紛らわすことをしてみる。消費社会はいくらでも気を紛らわしてくれるものがある。
そうしたものを沢山持っていることが幸せと錯覚する。
存在しない「幸せ」を求めて
今日も多くの人が頑張っている
本当には幸せではないが、幸せの幻想を与えてくれるのが消費社会である。だからお金が大切になる。消費社会では、お金がなければ気を紛らわす体験がなかなかできない。
今、書いたように、消費社会になったからこそ、心理的成長がますます重要になってきた。
つまり偽りの幸せを得るためにお金が必要になる。そしてお金を得ても本当には幸せになれない。
ある人は「否定的幸せ」という言葉で、それを表現している(注3)。
そしてこの「否定的幸せ」は消費社会から生じてきたという。
そして心理的に成長できていない人は、この「否定的幸せ」を得られないということで不幸になる。
「なんで自分ばかりがこうなるのだ」と世を恨む。「否定的幸せ」を得ている人と自分を比較して不公平だと恨む。
また消費社会で頑張っている人の方は、まさにイソップ物語の犬である。存在しない肉に向かって飛びつく。そしてすべてを失う。
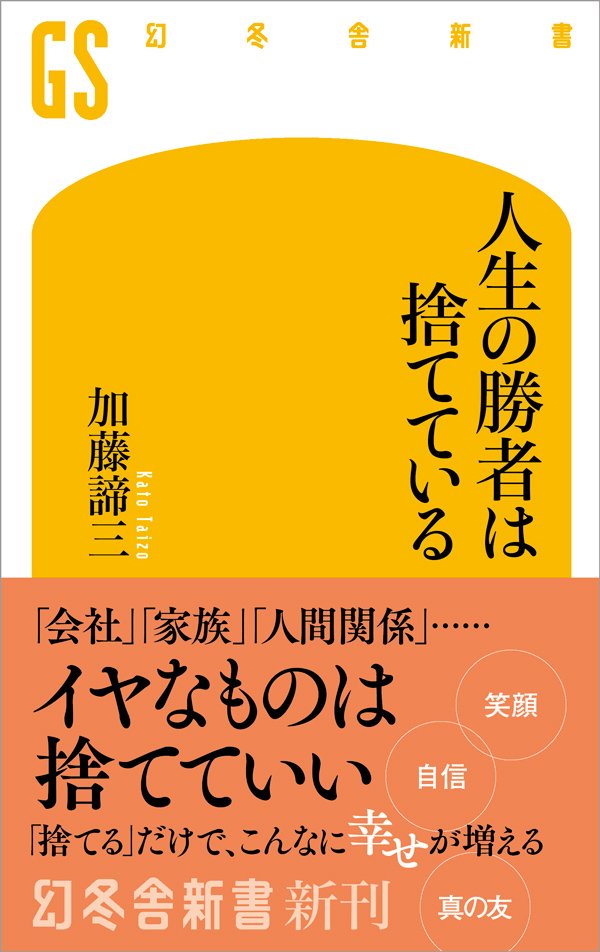 『人生の勝者は捨てている』(加藤諦三、幻冬舎新書)
『人生の勝者は捨てている』(加藤諦三、幻冬舎新書)
そんな幸せは存在しないのに、幻想の幸せを得ようとして、自らの人生を失う。イソップ物語の犬と同じである。
消費社会で成功するために頑張っている人は、幻想の幸せに飛びついて、自分の人生を失っている。
「笑顔のうつ病」と書いたハイジ・マッケンジーは、休むことなき「あるタイプの幸せ」の追求は、人を不幸にすることもあるし、うつ病にすることもあると言う。
存在しない「幸せ」という名の不幸を求めて、今日もまた多くの人が頑張っている。
消費文化が栄える今こそ、先哲の教えに耳を傾ける時なのである。